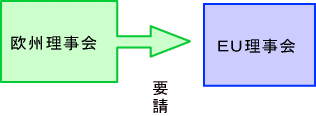EU理事会は、ECの政策を決定し、また、法令を制定する最高機関である。この意思決定機関は各国政府の代表で構成されるため、ECの政策ないし法令は、加盟国政府によって決定されると言える。つまり、ECは加盟国によって統制されているわけである( その他に、加盟国政府間のフォーラムとして、欧州理事会(European Council)が設けられている。この組織は、EU(ECではない)の機関とされることもある(EU条約第4条など参照)。
ECの機関としてのEU理事会と、その他のECの機関(例えば、EC裁判所)間の均衡を保つため、EU理事会ではなく、加盟国政府に権限が与えられている場合もある[4]。この場合、加盟国政府の代表は、EU理事会という組織的枠組みの中で行動すると解されている[5]。なお、この組織は前述した欧州理事会に類似するが、欧州委員長が参加しない点で、欧州理事会とは異なる。
EU理事会(以下では、単に理事会とする)において、各国の代表は自国の権利ないし利益を強く主張するため、審議がもつれることが多い[6]。この点において、理事会はECの機関としての性質と、自国の利益を追求したり、加盟国間の利害関係を調整する機関としての性質を併せ持っていると言える。
EU理事会は、各加盟国から1名の代表によって構成される[7]。EC条約第203条第1項において、同代表は、加盟国政府のために行動しうる閣僚級(つまり、大臣クラス)の者とされているため、必ずしも閣僚である必要はない。例えば、ドイツは、省庁の次官(Staatssekretären)を派遣することがある。それゆえ、EU理事会の代わりに、使用されることも少なくない「閣僚理事会」という名称は必ずしも適切ではない。 各国の代表は常に同一人物であるわけではない。理事会に誰を派遣するかは、加盟国政府の判断に委ねられているが、例えば、農業政策について協議する場合には、通常、各国より農相が派遣される。このような理事会は、一般に、農業理事会(ないし農相理事会)と呼ばれている。同様に経済政策・財政問題に関する場合には、各国の経済政策・財政担当大臣が派遣され、いわゆるECOFIN-Council が開催される。なお、一般的な問題(EU拡大を含む)について協議するのは、外相理事会である。現在、20以上の理事会が開催されているが、15以下に抑えることが計画されている[8]。
議長国は、同時に欧州理事会の議長国も務める。各国が議長国を務める半年間には、通常、2回の欧州理事会が議長国内で開かれ、EUの基本方針について協議される。
6ヵ月の任期中、議長国は、理事会を主導する政治的任務を負う。小国にとっては、自国を対外的にアピールする好機であるが、その負担も見過ごしえない。それゆえ、小規模国の新規加盟が中心となるEU東欧拡大に向けては、議長国選出や任期の見直し、また、前述したトロイカの再編などについて議論されている(欧州憲法による改正)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EC条約第202条は、EU理事会の任務として、 - 加盟国の経済政策を調整し、 - 決定権を行使する とのみ定めている。そのため、具体的な任務の内容については、個々の条文を参照する必要がある。なお、他の機関に同じく、理事会は、EC条約が定める権限のみを行使することができる。ある権限の行使に際して、理事会には(広範な)裁量権が与えられているため、権限を行使するかいなか、また、どのように行使するかは、その裁量判断に委ねられているが、EC条約が理事会の任務を具体的に定めているときは、その履行が義務づけられる[10]。理事会がEC条約の規定に反し、立法行為を怠るときは、不作為違法確認の訴え をEC裁判所に提起することができる(EC条約第232条)。
理事会の主たる権限ないし任務は以下の通りである。 (1) 法令の制定 前述したように、理事会はECの最高機関であり、主たる立法機関であるが[11]、現在では、欧州議会と共同で法令を制定することが多くなっている(立法手続について、詳しくはこちら)。なお、欧州委員会が法案を提出しなければ、立法手続は開始されないが(参照)、理事会は委員会に法案の作成を要求しうる(第208条)。 EC条約は、ある案件について抽象的にしか定めておらず、その具体化を理事会(または理事会と欧州議会)に委ねている場合が少なくない。例えば、アムステルダム条約 に基づき導入された第255条は、EU市民や加盟国内に住所を持つ個人のEU公文書開示請求権について定めているが、その一般手続や制限等は理事会によって定められる(第255条第2項)[12]。 制定された法令を実際に適用するために必要な規則を制定する権限は、原則として、委員会に与えられる(EC条約202条)[13]。つまり、理事会(場合によっては、欧州議会と共同で)が制定した法令の執行規則は委員会によって制定される(参照)。なお、 これらの法令を実際に適用するのは、通常、加盟国である(詳しくは こちら)。 その他、理事会はEC裁判所規程の改正権を有する(第245条第2項)。
(2) 財政 委員会によってECの仮予算案が作成されると、理事会は、欧州議会と共に、予算を決定する(第272条第3項)。
(3) ECの対外関係の構築 ECは、第3国または国際機関と条約や連合協定[14]を締結することができるが(第300条および第310条参照)、その締結権は理事会に与えられている。なお、理事会は、交渉権限を欧州委員会に与えることができる。 その他、理事会は、EUの第2の柱(共通外交・安全保障政策)の一環として採択された決議に基づき、第3国に対して経済制裁を課すことができる(第301条)。
(4) 諸評議会メンバーの任命 理事会は、経済社会評議会(第258条第2項)、地域評議会(第263条第2項)および会計検査院(第247条第3項)のメンバーを任命する権限を有する。これに対し、EC裁判所(第233条第1項)および欧州中央銀行理事会(第112条第2項)のメンバーは、理事会ではなく、加盟国政府によって任命される(参照)。なお、従来、欧州委員会のメンバーは、加盟国政府の相互承認によって指名・任命されていたが、ニース条約に基づき、この任命手続は、理事会(加盟国首脳によって構成される理事会)の特定多数決制に変更された(第214条第2項)。
(5) 諸機関のメンバーの俸給等の決定 欧州委員会メンバーと、EC裁判所判事、法務官および事務総長(Registrar)の俸給、手当や年金等について決定する権限も理事会に与えられている(第210条)。
(6) EC条約の改正 加盟国政府または委員会は、EC条約の改正を理事会に提案することができる。理事会は、欧州議会(および場合によっては委員会)の意見を聞き、諸条約改正のための政府間会議を開催するかどうかを決定する(EU条約第48条)。なお、実際に諸条約を改正するかどうかを決めるのは、理事会ではなく、加盟国である。条約の改正には、全加盟国の賛成を必要とする。
(7) 第3国のEU加盟 EU条約第6条第1項所定の諸原則を尊重する、あらゆるヨーロッパの国々は、EUに加盟することができる。加盟申請は理事会に対して行い、理事会は、委員会の意見を聞き、欧州議会[15]の同意を得て、全会一致にて決定する(EU条約第49条第1項)。なお、第3国のEU加盟申請が了承されれば、EU加盟国(EU自身ではない[16])と同第3国との間に加盟条約が締結され、同条約が全加盟国および同第3国によって批准された後に、EU加盟が実現する。批准は、各国の憲法上の規定に従いなされなければならない(前掲規定第2項)。
(8) EUの第2および第3の柱における権限 共通外交・安全保障政策の分野(EUの第2の柱)において、理事会は、欧州理事会によって決定された方針に従い、共通の行動(EU条約第14条)と、共通の立場(第15条)を決定する。 刑事に関する警察・司法協力の分野(第3の柱)において、理事会は、共通の立場や加盟国の法令・行政規則を調整するための措置を制定しうる。また、加盟国間で締結される国際条約を起草しうる(第34条)。
ECの立法手続はEC条約の中で定められているが(例えば、第250条以下参照)、主たる立法機関であるEU理事会の議決についても同様に条約内で明定されている。理事会の議決方式には、全会一致制、絶対多数決制、また、特定多数決制があるが、その詳細は以下の通りである。
(1) 全会一致 加盟国が主権の委譲に消極的な分野(例えば、租税〔第93条〕、移動労働者の社会保障〔第42条〕、EU市民への選挙権の賦与〔第19条〕、EU市民への新しい権利の賦与〔第22条〕、差別の撲滅〔第13条〕)や、一般規定(第308条)の適用に際し、理事会は全員一致で決議しなければならない。また、理事会が委員会案を修正する場合や(第250条第1項)、欧州議会との協力手続ないし共同決定手続において、理事会が議会案を修正する場合(第251条第3項、第252条第c号)も同様である。なお、出席した加盟国代表が棄権することは、この全会一致の決議を妨げない(第205条第3項)。
(2) 絶対多数決 EC条約第205条第1項は、絶対多数決を原則として定めているが(すなわち、過半数の賛成が得られれば、議案は採択される)、実際には、後述する特定多数決の方が一般的である。 (3) 特定多数決 特定多数決制度は、域内市場 に関する案件に適用される議決方式として採用されたが、現在は、その他の案件で広く用いられている。 各国の持票数は各国の人口に照らし決定されるが、国際舞台における各国の形式的平等を考慮し、修正されている(EC条約第205条第2項、詳しくは こちら または こちら)。その結果、大国に不利で、小国に有利な票数配分になっている( ブルガリアとルーマニアの新規加盟 が実現し、27ヶ国体制に発展した現在(2007年1月)、各国の持票の合計は345票である(各国の持票数は こちら)。欧州委員会の提案を受けて審議するときは、255票(全体の約74%)の賛成があれば、議案は採択される(単純特定多数決)。この票数は、大国のみの賛成によってEU法が制定されることを阻止し、また、逆に、小国のみの反対でEU法の制定が阻止されることを防ぐように定められている。 欧州委員会の提案を受けずに理事会が審議する場合には、255票の賛成と、少なくとも3分の2以上の加盟国の承認が必要となる(二重の特定多数決)(参照)。
|
|
|
なお、ニース条約 に基づき、人口を考慮する制度が導入された。これによると、各国は、法案に賛成する加盟国の人口が、EU全体の62%に達することを要求しうる(第205条第4項)。この数値による人口は、Eurosat の統計に基づき毎年算定されるが、ブルガリアとルーマニアの新規加盟 を経て27ヶ国体制に発展した2007年は、3億0550万人である(総人口は4億9280万人)(参照)。 |
|
|
|
2004年5月の 東方拡大 後、2004年10月末までは、持票数の総数は、124票であった(EC条約第205条第2項)[17]。また、理事会が委員会の提案を受けて法律を制定するときは、88[18]の賛成票が必要であり、その他の場合には、少なくとも10の加盟国の賛成を含む62の賛成票が必要とされた。
2004年10月から2006年末まで、持票数の総数は321で、232の賛成票があれば特定多数決は成立したが、ブルガリアとルーマニアの新規加盟により、2007年元旦からは、前述のように変更されている。 |
|
[1] See OJ 1993, L 281, p. 18. [2] Matthias Herdegen, Europarecht (Verlag C. H . Beck 2003, 5th edition), p. 91 (para. 114). [3] EU条約第4条は以下のように定める。 The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political guidelines thereof. The European Council shall bring together the Heads of State or Government of the Member States and the President of the Commission. They shall be assisted by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States and by a Member of the Commission. The European Council shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the Head of State or Government of the Member State which holds the Presidency of the Council. The European Council shall submit to the European Parliament a report after each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved by the Union. [5] Waltraud Hakenberg, Grundzüge des Europäischen Gemeinschaftsrechts (Verlag Vahlen 2003, 3rd edition), paras. 37-38; Herdegen, op. cit., p. 91 (para. 114). [6] この意味において、理事会の議決方式を柔軟にすることは重要であると言える。 [7] 2003年8月現在、EUには15の国が加盟しているため、理事会の構成員は15名になる。 [8] Hakenberg, op. cit., para. 24. [9] Decision of Council (1 January, 1995), OJ 1995, L 1, p. 220. [10] 交通政策の分野における権限ないし任務と、サービス提供の自由の分野における権限ないし任務との違いについて、See ECJ, Case 13/83, European Parliament v Council. [11] なお、欧州石炭・鉄鋼共同体では、High Authority (最高機関)が主たる立法機関であった。同共同体条約第26条参照。この機関は、ECの欧州委員会に完全にではないが相当する。 [12] なお、この点に関し、欧州議会と理事会はすでに規則(Regulation (EC) No. 1049/2001, OJ 2001, No. L 145, p. 43)を制定している。 [13] 例外的に、理事会は法規の執行に関する権限も行使することができる(第202条)。 [14] 連合協定は、通常の国際条約とは異なり、ECと第3国(または国際機関)間に緊密な関係を構築することを目的とした国際法で、通常は、第3国のEU加盟を前提にして締結される(第310条参照)。 [15] 欧州議会の議決には、総議員の過半数の賛成を必要とする。 [16] なお、EUは国際法人格を持たないため、国際条約を締結しえない。 [17] 各国の持票数は、以下の通りである。
新規加盟10か国の票数は以下の通りである。
[18] 東方拡大が実現する前(すなわち、15か国体制当時)、持票数は合計87で、その内、62票の賛成が得られれば、法案は可決された。この62という数字や、各加盟国の持ち票数および総票数は、各加盟国の政治力やECの政策運営方法など、種々の事項を考慮して定められている。例えば、大国2国のみの反対では、議案の採択を阻止することはできない。また中小国のみの賛成票でも議決は採択されない。 |
|
|
「EU法講義ノート」のトップページに戻る