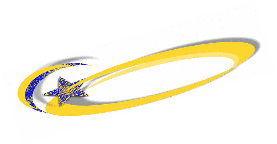
| E U 法 上 の 個 人 の 権 利 |
|
はじめに EEC設立当初、EEC条約は基本権保護ないし個人の権利保護について定めていなかった。そのため、初期のECJ判例では、基本権の保護が重視されなかった。また、ECJは、共同体法は国内憲法が保障する基本権にも優先すると判断したため(EC法の優先性)、多くの批判を浴びた。特に、ドイツ連邦憲法裁判所の態度は厳しく、EC法の効力や自律性を否定する立場を示したため(参照)、後に、ECJは、法の一般原則として、基本権保護の必要性を認めるようになった。この判例法は、1992年の マーストリヒト条約 の中で、明文化されるに至ったが(当時のEU条約第6条第2項)、もっとも、その当時、ECJに管轄権は与えられていなかった。これが与えられるようになったのは、1997年の アムステルダム条約 (発効は1999年)による。
現行EU条約は、EU自らが人権条約を締結することを可能にしているが(第6条第2項)、まだ実現していない(詳しくは こちら)。 ところで、2001年12月には、EU独自の基本権憲章 が公布された。現在、同憲章はEU条約やEUの機能に関する条約といった基本条約と同じ価値を持つ独立した法源として適用されている(リスボン条約発効後のEU条約第6条第1項参照)。 1.EU条約 (→ 第1次法) (1) EU法の基本原則としての基本権保護 EU条約第2条(リスボン条約体制)は、EUの基本原則(価値)として、①人間の尊厳の尊重、②自由、③民主主義、④平等、⑤法の支配、⑥少数派に属するもの権利を含めた人権の 保護を挙げている。同条はプログラム規定としての性格を有するに過ぎないが、EU法の解釈に際し重視されている(詳しくは こちら)。 なお、EU加盟国がこれらの諸原則の重大な違反を犯す時、EU理事会は同国に対し、制裁を発動することができる(EU条約第7条)。これによって、EU法は、基本権保護を初めとする諸原則の遵守を徹底している。
さらに、EU条約第6条第1項第1款は、EUは EU基本権憲章 で規定された権利・自由を承認すると定める。また、第6条第3項は、欧州人権条約や加盟国憲法に共通の伝統から導かれる基本権は 、一般原則として、EU法の一部になるとする。
1993年11月に発効した マーストリヒト条約 に基づき、「EU市民」が創設された(EC条約第17条、EUの機能に関する条約第20条参照)。EEC設立の初期の段階より、ECJは、加盟国だけではなく、個人をも法的主体として扱い(参照)、加盟国国民の権利や 基本的自由 を厚く保障してきたが、ここでは、加盟国国民は「EC市場において経済活動を行う者」(Marktbürger)としての性質が強かった。新たに設けられた「EU市民」という概念は、これを拡張するものである。つまり、EU・ECの発展に対応させ、加盟国国民の地位やその権利保護を、単なる経済的な側面から政治的な側面へ広げている。 「EU市民」という資格ないし法的地位は、加盟国の国民であれば誰にでも与えられる。つまり、加盟国の国籍の有無を基準としている。ある者が加盟国の国籍を有するか否かは、EU法(従来のEC法)ではなく、加盟国法による(Case C-369/90, Micheletti [1992] ECR I-4239, para. para. 10; Case C-200/02, Zhu and Chen [2004] ECR I-9925, para. 37)。なお、加盟国の国籍と第3国の国籍の両方を持つ場合であれ、EU市民権の行使が妨げられるものではない。 EUの機能に関する条約第20条(EC条約第17条)第1項第2文によれば、「EU市民」とは加盟国の国民を補充しうる概念であるが、それに代わるものではない(Case C-224/98, D'Hoop [2002] ECR I-1691, para. 28 参照)。なお、この規定は、アムステルダム条約に基づき挿入された。 EU市民には、EU条約やEUの機能に関する条約が定める権利と義務が与えられるが(EUの機能に関する条約第20条第2項)、EUの機能に関する条約第20条第2項は以下の権利を挙げている(義務については定めていない)。 ・ EU内を自由に移動し、居住する権利(第21条) ・ 定住地における地方選挙権、欧州議会選挙での選挙権(第22条) ・ 他の加盟国の外交的保護と領事保護を受ける権利(第23条) ・ 欧州議会に対する請願権(第24条第2項および第227条) ・ 欧州議会が任命したオンブズマンへの苦情申立て(第24条第3項および第228条)
これらの権利は、EU基本権憲章第5編(第39条~第46条)でも保障されているが、いわゆる政治的な権利ないし市民権にあたり、基本的自由 に代表される経済的な権利とは異なる。 なお、EU市民の権利はこれらに限定されるわけではない。また、マーストリヒト条約に基づき、「EU市民」という概念が導入される前より保障されていた権利も含まれているが(移動の自由(EUの機能に関する条約第21条)、欧州議会における選挙権(第22条)、欧州議会に対する請願権(第24条第2項))、上掲の諸権利がまとめて規定された意義は大きい。 上掲の諸権利は自然人にのみ保障されるか、または、法人に対しても保障されるかという点について、基本諸条約は明確に定めていないが、選挙権を除く、その他の権利は法人にも保障することができる。 EU市民は、上掲の権利をEU(EUの機能に関する条約第24条参照)または加盟国(第21条)に対し主張することができる。つまり、保障が義務付けられる主体は同一ではない。なお、加盟国とは、EU市民の本国に限定されるわけではないため、EU市民は他の加盟国に対しても、自らの権利を主張しうる。他方、EU法は複数の加盟国に関わらない、純粋な国内事件には適用されないため、このようなケースにおいて、EU市民は本国に対し、EU市民としての権利を主張しえない(Case -192/05, Tas-Hagen [2006] ECR I-10451)。もっとも、EU市民権の行使について、ECJは、ある事例が複数の加盟国に関わるかどうかを(基本的自由の場合に比べ)緩やかに解している(Case C-520/04, Turpeinen [2006] ECR I-10685; Case C-406/04, De Cuyper [2006] ECR I-6947)。
(3) 基本的自由 商品、人、サービスおよび資本の移動の自由は、EU法上の基本的自由と呼ばれ、厚く保障されている(詳しくは こちら)。
(4) 差別禁止 ① 国籍等に基づく差別の禁止 国籍の違いを理由に、EU市民を差別してはならない。この原則は、EECの設立当初よりEEC条約の中で謳われているが(現行EUの機能に関する条約第18条、EC条約第12条参照)、アムステルダム条約は、この差別禁止原則の適用範囲を拡張し、性別、人種、宗教、価値観、障害、年齢、性的指向等に基づく差別を撲滅するための権限をEUに与えている(EUの機能に関する条約第19条)。なお、ドイツ基本法(憲法)第3条第1項が規定するような、一般的な差別の禁止について、EU基本諸条約は定めていないが、従来よりECJは、一般的な差別禁止が法の一般原則として、EU法体系下においても適用されると判断している(参照)。 なお、差別禁止の原則は、EU法の適用範囲に限定されるため、加盟国の管轄領域においては、他の加盟国の国民を差別したり、または自国民を差別的に取り扱うことも許される。
② 職生活における男女差別の禁止 上述した一般的差別禁止の他に、ある特定の分野における差別の禁止についてもEUの機能に関する条約は定めている。特に重要なのは、職生活における男女差別の禁止である。
2. ECJの判例法における基本権 上述したように、ECJは基本権保護の必要性を認め、法の一般原則として保障してきたが(これは基本権保護に関する明文の規定が設けられていなかったためであるが、個人の「権利」として保障するのではなく、一般原則として保障するという意義もあると解される)、判例法で確立された基本権の例は下記の通りである。 ・財産権(詳しくは こちら) ・職業遂行上の自由(詳しくは こちら) ・人格権 ・表現の自由 ・私的空間および住居の不可侵 ・職業および団結の自由 ・裁判を受ける権利(詳しくは こちら)
3. 欧州人権条約や加盟国憲法に由来する基本権 基本権保護に関し、EU条約第6条第2項(リスボン条約体制)は、さらに、EUは欧州人権条約や加盟国憲法の伝統より生じる基本権を尊重しなければならないと定めるが、前述したように、これは従来のECJの判例法を明文化したものである。 欧州人権条約は、欧州評議会の枠内で締結された国際条約であるが(参照)、すべてのEU加盟国は、欧州評議会に加盟し、また、欧州人権条約を締結している。EC自身は同条約制度に加盟していないため、(少なくとも直接的には)それに拘束されないが、加盟国からECへの権限委譲に基づき、加盟国はECも人権条約に反しないよう配慮しなければならないとされる。また、欧州人権裁判所は、加盟国法の審査を通じ、EC法も間接的に審査しうるとされている(欧州人権裁判所判旨)。 ECによる欧州人権条約締結も検討されていたが(これに対し、従来のEUに法人格は与えられていなかったため、条約を締結する権限を持っていなかった)、ECJによれば、それにはEC条約の改正が不可欠とされた。これは、人権条約の締結によって、ECは欧州人権裁判所に訴えられたり、また、同裁判所がECJの判断を審査しうるようになり、EC法体系が大きく変容するためである(Opinion 2/94, ECHR [1996] ECR, I-1759)。なお、ECによる人権条約締結を可能にするため、EC条約を改正する選択肢も残されているが、実現しなかった。 これに対し、リスボン条約はECを廃止してEUに引き継がせ、EUに法人格を与えた。また、EUによる人権条約締結を可能にしている(リスボン条約発効後のEU条約第6条第2項)。
他方、欧州人権条約は、同条約を締結しうるのは欧州評議会のメンバーとしているが(第59条第1項)、メンバーになりうるのはヨーロッパの諸国(のみ)である(欧州評議会規程第4条第1項)。この問題を解決するため、2004年3月に議定書(欧州人権条約附属第14議定書)が採択され、人権条約第59条第2項(新規定)において、EUも人権条約を締結しうることが定められた。なお、この議定書はロシアがまだ批准していないため、発効していない。それゆえ、EUの人権条約締結も実現していない。 4. EU基本権憲章 4.1. 起草 EU・ECの管轄権が拡大するだけではなく、諸政策が発展するにつれ、EU・ECの措置に対する権利保護の必要性が強く認識されるようになっているが(ドイツ連邦憲法裁判所の要請については こちら)、世界人権宣 50周年(1998年12月)を契機に、欧州理事会は、1999年6月、EU独自の基本権憲章を制定することを決定した(詳しくは こちら)。そして、最初の欧州共同体、つまり、欧州石炭・鉄鋼共同体 の設立から約50年が経過した2001年12月7日、ニース欧州理事会(政府間会議)において、EU基本権憲章が布告された(OJ 2000, C 364, p. 1)。同憲章は、以下の7編からなるが(全54条)、前文では、特に、憲章を制定し、基本権を「より明確に見える」(more visible)ようにする必要性が強調されている。
EU基本権憲章は、ドイツのローマン・ヘァツォーク(Roman Herzog)元連邦大統領が率いる作業部会によって起草された。その内容は国内憲法を参考にしているが、子供の権利(第24条)や適切な行政を求める権利(第41条)などの新しい権利も含まれている(参照)。また、労働者の社会権、情報保護、生物倫理など、欧州人権条約 では規定されていない基本権も保障している。
ECの諸機関 や 加盟国 は、EC法の履行に際し、基本権憲章を尊重しなければならないが(第51条第1項)、この義務が誠実に履行されているかどうかは、ECJ やその他の機関によって審査されない。要するに、この憲章が保障する権利が侵害されても、個人は裁判所に訴えを提起しえない(see Case C-58/94, Netherlands v. Commission [1996] ECR I-2169, paras. 24 et seq.)。なお、憲章が法的拘束力に欠けることは、それがECの「官報C」(OJ 2000, C 364, p. 1)に掲載されていることからも読み取れる。確かに、欧州議会、欧州委員会 および EU理事会 は相次いで、自発的に憲章を遵守する旨の決議を採択し、また、EU一般裁判所(従来の第1審裁判所) や 法務官 によって、判断の補助的資料として用いられることも少なくないが(例えば、Case T-54/99, max. mobil Telekommunikation Service [2002] ECR II-313, para. 57; Opinion of AG Tizzano in Case C-173/99, BECTU [2001] ECR I-4881, paras. 26 et seq.)、憲章に法的拘束力を与えることは今後の課題とされた。 4.2. 欧州憲法条約内への統合 この課題を達成すため、2004年10月に締結された 欧州憲法条約 は、基本権憲章を完全に取り込み、EU第1次法の一部とした(詳しくは こちら)。また、EUは憲章が保障する基本権を承認する旨を明文で定めた(第I-9条第1項、詳しくは こちら)。もっとも、フランスとオランダの国民投票で憲法条約の批准が否決されたことをきっかけに、同条約の発効は見送られることになった(詳しくは こちら)。 ・ 部分的修正 なお、欧州憲法条約内に挿入されるに際し、基本権憲章の規定内には修正が施された。例えば、ドイツ語の "Person" (人)の概念は、それが自然人に関する場合には、"Menschen"(人間)に置き換えられた(第II-62条第1項、第II-63条第1項、第II-66条など)。
私生活や家庭生活、住居およびコミュニケーションの尊重について定める第II-67条は、本来、自然人のみを対象にすると解されるが、ドイツ語版では、自然人のみを指す
Mensch ではなく、Person という概念が用いられている。これは、法人の事務所も「住居」として保障範囲に含まれるとするECJの判例(Case
C-94/00 Roquette Frères SA [2002] ECR I-9011, para. 29.
See also ECHR, judgment of 16 December 1992, Niemitz v Germany, Serie A 251-B,
para. 37 = EuGRZ 1993, 65, 66 f.)を踏まえたものである。 また、前文が部分的書き換えられるとともに、憲章の解釈に際しては、作業部会の理事会が作成したコンメンタールを適切に考慮すべきとする規定が新たに設けられた(第5項、第II-112条第7項〔現第52条第7項〕 参照)。なお、このコンメンタールは、作成当初、何ら法的拘束力を持たないものとされていた。同時に、憲章の解釈に関する規定が新たに設けられている(第II-112 条に第4項~第7項の挿入)。 さらに、EU条約やEC条約を欧州憲法条約に統合することに伴う文言上の修正(第II-101条第4項〔現第41条第4項〕、第II-112条第2項〔現第52条第2項〕)や、従来のECが廃止され、EUに一本化されることに伴う文言上の修正(第II-111条第2項〔現第51条第2項〕)もなされている。後者の点について、第II-101条第3項〔現第41条第3項〕 も参照されたい。 その他、憲章の適用範囲や解釈・適用について、より詳細に定められるようになった(第II-111条第1項〔現第51条第1項〕 および 第II-112条第4項~第6項〔現第52条第4項~第6項〕)。 4.3. リスボン条約体制 - 独立した条約として分離 既存の第1次法を改正するため、2007年12月、EU加盟国は リスボン条約 を締結した。その際、基本権憲章を新条約の中に取り込むことはせず、独立した条約として発効させることになったが、これは、リスボン条約の中に盛り込むとすれば、同条約の批准が困難になる加盟国(イギリスとポーランド)もあると考えられたためである。もっとも、基本権憲章はEU条約やEUの機能に関する条約といった基本諸条約と同等の価値を持つ法源として明確に定められている。つまり、憲章の地位が明瞭に高められている(リスボン条約発効後のEU条約第6条第1項)。また、EUは憲章が保障する基本権を承認する(recognise)ことも同時に定められている(リスボン条約発効後のEU条約第6条第1項)。 上述したように、基本権憲章を第1次法の中に統合するのではなく、独自の条約として発効させることとなり、2007年12月12日、欧州議会の Pöttering 議長、欧州委員会の Barroso 委員長、当時のEU理事会議長国ポルトガルの Sócrates 首相によって署名された。これによって、憲章には法的拘束力が与えられ、市民は同憲章で保障されている基本権侵害を理由に提訴しうるようになった。なお、憲章の遵守義務が課されているのは、もっぱらEUであり、加盟国はEU法の実施に関し、憲章に拘束されるに過ぎない。つまり、EU法の実施に関連しない純粋な国内案件に関し、加盟国は憲章違反の責任を問われることはない(憲章第51条第1項)。また、イギリスとポーランドに対し憲章は原則として適用されず、ECJは両国の憲章違反について審査しえない旨を定める 議定書 がリスボン条約の締結に際し設けられた(その理由については こちら)。さらに、2009年10月の欧州理事会では、チェコに対しても適用を排除する方針が決定された(詳しくは こちら)。
5. ヨーロッパ社会憲章と社会的基本権に関する共同体憲章 詳しくは、こちら
6. EU基本権庁
The European Union Agency for Fundamental Rights(EU基本権庁)については、こちら
|
|
|
従来の「EU・EC法上の個人の権利」(ニース条約体制)については こちら |
|
|
「EU法講義ノート」のトップページに戻る
