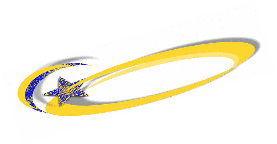
|
|
はじめに
|
 |
|
はじめに EU法によって、加盟国の国民はEU内を自由に移動し、働くことができるようになった(東欧諸国に対する例外は こちら)。また、労働者だけではなく、その家族も一緒に移動し、他の加盟国に居住することが認められている。EU法は、さらに、他の加盟国で働き、また、そこに滞在するだけではなく、社会保障も受けられるようにしている。つまり、単なる経済的自由(加盟国からの自由)だけではなく、社会的権利(加盟国に対する請求権)をEU市民に保障している(詳しくは こちら)。 この分野におけるEU法の発展は、第2次法だけではなく、EU裁判所の判例法を通しなされてきたが、他方、第1次法(EU基本諸条約)は、ほとんど改正されていない。ただし、その例外として、欧州議会の立法権限の強化を挙げることができる。また、リスボン条約は、社会保障の整備に関し、立法手続の停止を認めており、欧州統合を抑制する可能性も認めている(詳しくは こちら)。これは、EUが27ヶ国体制にまで発展し、域内の状況がますます多様化していることを表している。 1. 保障範囲 EUの機能に関する条約第45条(EC条約第39条に実質的に同じ)は、加盟国出身の労働者はEU内を自由に移動しうると定めるが、その一環として、仕事、賃金、その他の労働条件の国籍に基づく差別が禁止されている(第45条第2項)。つまり、加盟国は他の加盟国出身の労働者を自国民と同じように扱わなければならない。なお、保護されるのは加盟国の国民(EU市民)のみである。 また、EU市民である労働者には以下の権利が保障される(第45条第3項)。
これらの他の加盟国(労働を行う加盟国)に滞在する権利は、後に 第2次法 によって、労働者以外の者(その家族、年金受給者、学生、自営業者)に対しても保障されるようになった。
ところで、労働者の移動の自由や他の加盟国(労働を行う加盟国)に滞在する権利はEU裁判所の判例法を通し強化されてきた。例えば、1969年10月に下された判決において、同裁判所は、職場復帰を保障するドイツ法は他の加盟国の国民にも適用されなければならないとした。なお、このケースでは、ドイツでの職業を中断し、兵役のために本国に戻るイタリア人には、兵役終了後、元の職業への復帰が保障されるべきかが争われた(Case 15/69 Ugliola [1969] ECR 363)。 また、1975年の判決において、EU裁判所(当時のEC裁判所)は、労働者に対する差別禁止は、労働者の死亡後、その遺族に対しても適用されなければならないとし、子供の多いフランス人家族にのみ鉄道運賃を優遇するフランスの措置はEU法に違反すると判断した(Case
32/75 Cristini [1975] ECR 1085)。同様に、自国民労働者の子供にのみ奨学金を給付するドイツの制度はEU法に違反するとした(Case
9/74 Casagrande [1974] ECR 773)。さらに、この奨学金は外国人労働者の子供の住所地(厳密には、勉強をする地)に拘わらず給付されなければならないとし、ドイツ国内の大学に通う場合にのみ奨学金を給付するというドイツの制度はEC法に違反するとした(Case
C-308/89 Di Leo [1990] ECR I-4185)。
労働者の移動の自由の保障は絶対的ではなく、公序、安全・治安維持および衛生上の理由に基づき、制限することができる(第45条第3項)。ただし、安全・治安の維持を理由に労働者の移動を制限するためには、明白な危険性が存在しなければならない。例えば、過失によって他人(兄弟)を殺害し、有罪判決を受けたイタリア人労働者をドイツが本国に送還しうるためには、同人がドイツ国内に滞在すれば国内の安全が害される危険性が明白に存在しなければならない(Case 67/74 Bonsignore [1975] ECR 297)。麻薬の常習犯を本国に送還する場合も同様に、同人の滞在が国内の公序を乱す危険性が存在しなければならない(Case C-482/01 and C-493/01 Orfanopoulos [2004] ECR I-5257)。 また、公職に関しては、これらの権利や移動の自由は保障されない(第4項)。但し、実務において、この制限は、司法、警察、軍事や租税に関わる公務(本質的な公権力の行使に関わる職)、また、その他の公務の管理職に限定されている。つまり、ある加盟国の国民は、他の加盟国で裁判官や警察官として働く権利が保障されているわけではないが、医療、交通、通信業務や、公立学校における教職に関しては、他の加盟国の国民を差別してはならないとされている。オーケストラの団員を自国民に制限することも禁止される(Case C-290/94 Commission v. Greece [1996] ECR I-3285)。 なお、加盟国は、非公式の宣言によって、職探しのために他の加盟国に滞在しうる期間を3ヶ月に限定し、また、同期間終了前に、社会扶助(生活保護)を打ち切ることも可能としている。もっとも、この宣言に法的拘束力はない。EC裁判所は、職業に就く可能性が裏付けられないならば、滞在期間を6ヶ月に制限することも適切であると判断している(Case C-292/89 Antonissen [1991] ECR I-745, para. 21)。 ところで、上掲の自由に基づき、労働者の移動の自由や、他の加盟国に滞在する権利を制約する場合であれ、適切な方法を用いなければならない。また、必要以上に制約してはならない(比例性の原則)。
2004年5月1日、多数の東欧諸国がEUに新規加盟したが(2007年元旦には、ブルガリアとルーマニアの加盟も実現した)(⇒ EUの東方拡大)、これらの国より低賃金労働者が大量に押し寄せることが懸念されたため、労働者の移動の自由には特別措置が設けられた。それによれば、従来の加盟国は、マルタとキプロスを除く新規加盟10ヶ国からの労働者の移入を、最長7年間(2+3+2 ルール)、制限することができる。もっとも、イギリス、アイルランドおよびスウェーデンの3国は、2004年5月の東方拡大時より制限を設けていない。他方、スペイン、フィンランド、ギリシャおよびポルトガルは、2006年年5月より、制限を完全に撤廃している。
(1) 立法手続 前述した労働者の権利を実現するため、欧州議会とEU理事会は、通常の立法手続に従い、指令または規則を制定するものとされている(EUの機能に関する条約第46条)。なお、従来は、両機関が 共同決定手続 に従い制定することになっていた(EC条約第40条)。 ところで、他の加盟国では、労働者やその家族の社会的権利が保障されないとすれば、実際に他の加盟国に移動・移住することは困難になる。そのため、EU基本条約は、労働者やその家族、また、自営業者のために社会保障を整備することを諸機関に義務付けている。従来は、欧州議会とEU理事会が 共同決定手続 に従い、必要な措置を発するとされていたが(EC条約第40条)、現行法は、両機関が通常の立法手続に従い、制定するものとする(EUの機能に関する条約第48条)。基本条約は、特に以下の制度の導入を明示しているが、この点は改正されていない。
なお、この社会保障制度の整備に関し、リスボン条約は新たな手続を設けている。それによれば、法案によって国内社会保障制度の重要な要素(特に、適用範囲、費用または財政構造)が害されるか、または財政的均衡を損ねる場合、加盟国は 欧州理事会 に審議を委ねることができる(参照)。この場合、欧州議会とEU理事会による通常の立法手続は停止する。この停止から4週間以内に、欧州理事会は次の措置をとらなければならない(EUの機能に関する条約第48条第2項)。
(2) 第2次法の例 すでに多くの第2次法が制定されているが、その中で最も重要なものは、1968年にEU理事会が制定した規則(Regulation 1612/68)であるが(当時は欧州議会に共同決定権限は与えられていなかった)、例えば、同規則第7条第4項は、私法上の差別的な合意(労働規約など)を無効としている。また、第9条第1項は、住宅の取得に関し、他の加盟国の労働者を差別してはならないと定める。さらに、第12条は、一般教育や職業教育に関し、移動労働者の子供を差別することを禁じている。 さらに、指令(Directive 68/360)によって、労働者やその家族の旅行・滞在期間制限は廃止され、また、規則(Regulation 1251/70)では、離職した後も、引き続き、加盟国(勤務地国)内に滞在する権利が保障されている。 他方、規則( Regulation 1408/71, modified by Regulation 307/99 and Regulation No. 883/2004)は、加盟国の社会保障制度を調整し、複数の加盟国で働く労働者が不利益を被らないための基盤を設けている。つまり、複数の加盟国で働いていたため、どちらの国でも労働・年金積立期間が不足し、社会保障を請求・受給しえなくなるという問題を解消するため、全加盟国における労働・年金積立期間の合算を認める。また、年金は、どの加盟国に居住するかを問わず支払われる。なお、規則(特に、Regulation No. 883/2004)は加盟国の社会保障制度を統一・調整するものではなく、その請求・受給資格(労働期間の合算)等について定めるのみである。 |
|
