| E C 裁 判 所 (Court of European Communities) |
|
 EC裁判所 (ルクセンブルク)
|
| は じ め に |
|
EC条約(EC第1次法)や、それに基づきECの諸機関が制定する法令(EC第2次法)の内容は明確ではなく、その解釈について争いが生じることがある。また、第2次法が第1次法(いわゆる、ECの「憲法」)に反するのではないかが問題になることも少なくない。さらに、EC加盟国や個人がEC法(第1次法と第2次法)に違反しているのではないかが争われることも多い。このような法律問題に関し、加盟国の裁判所が判断を下すとすれば、裁判所の判断は加盟国ごとに異なり、EC法が統一的に解釈・適用されないことも生じうる。このような弊害を防止するために、EU加盟国はEC裁判所を設け、EC法に関する法律問題について排他的に判断する権限を同裁判所に与えている(EC条約第220条以下参照)。 |
|
|
「EC法の番人」である 欧州委員会 が、加盟国はEC法に違反していると考えるとき、同委員会は、EC裁判所に提訴することができる(第226条第2項[参照])。訴えられた加盟国は、この訴訟手続の開始や進行を阻止しえない。また、EC裁判所が委員会の見解に従い、加盟国によるEC法違反を確認する場合、加盟国は、同裁判所の判決に従い、違法状態を除去しなければならない(第228条第1項)。なお、EC裁判所は加盟国の違法措置を無効と宣言することはできない。違法状態を取り除くのは、あくまでも加盟国の任務である。もっとも、加盟国がそれを怠る場合、欧州委員会は、一定の期間内に必要な措置を講じるよう、勧告することができる。加盟国がそれに従わない場合には、委員会は課徴金額を決め、その賦課をEC裁判所に求めることができる(第228条第2項)。この課徴金の支払いを命じる判決は強制執行することができる(第244条および第256条、詳しくは、後述3. (1) を見よ)。裁判手続が強制的であることや(加盟国は裁判の開始を拒否したり、判決の効力を否認しえない)、判決の強制執行力の点で、ECは通常の国際機関よりも実効的な司法制度を有していると言える。 以下では、EC裁判所について説明する。なお、EC裁判所に関する規定は、三つの欧州共同体条約内に存するが、以下では、EC条約についてのみ言及する。 |
| 1. 組 織 |
|
|
![]() リスボン条約による改正は こちら
リスボン条約による改正は こちら
| (1) EC 裁 判 所 |
|
EC裁判所の裁判官は、各国より1名ずつ選出されるが(第221条第1項)[1]、その任命は、あくまでも加盟国政府の相互承認による。これに対し、欧州委員会のメンバーは、EU理事会によって任命される(詳しくは こちら)。加盟国政府によるか、EU理事会によるかで実質的な違いはないが、機関間(つまり委員会と理事会)の均衡を図る上で、理事会による任命には問題がある。 |
|
|
なお、EC裁判所の独立性を担保するため、裁判所長官は裁判官によって選出される。その任期は3年で、再任は可能である(第223条第3項参照)。 裁判官は、十分な独立性を有し、優秀な法律家の中から選出されなければならない(第223条第1項参照)。一般に国内上級裁判所の判事、政治家、官僚または大学教授が任命されている。 裁判官の任期は6年であるが、再任も認められる(同条第4項)。通常、3年ごとに半数の裁判官が改任ないし再任される。
|
|
EC裁判所には、その職務を補佐するため、法務官(Advocate General)が8人配置されている(第222条)。これは、フランスの最高行政裁判所(Conseil d'Etat)の Commissaire du Gouvernement をモデルにした制度である。 法務官の任命・任期は、裁判官の場合に同じである。 なお、法務官の総数は8人であるため、すべての加盟国より1人ずつ、選出されることにはならないが(なお、EU理事会は全会一致にて定数を変更することができる〔第222条第2項〕)、従来は、ドイツ、フランス、イタリア、イギリスおよびスペインの5大国より1名ずつ、また、その他の加盟国より3名、選ばれている。 法務官は、EC裁判所の任務を保佐するため、同裁判所に係属した訴訟事件の争点について検討し、「見解」を述べる(例えば、原告の主張の正当性について詳細に検討し、どのような判決を下すべきか述べる)。裁判官は、その「見解」に拘束されないが、大多数の事件では、それに従っている[2]。
EC裁判所は、8人の法務官の中から第1法務官(主席法務官)を選出する。その任期は1年である(EC裁判所手続規則第10条)。第1法務官は、第1審裁判所の判断を審査すべきかどうかEC裁判所に提案することができる(詳しくは
こちら)。
|
| (2) 第 1 審 裁 判 所 |
|
EU拡大(つまり、加盟国数の増加)やEU法の発展(つまり、審査対象の増加)によって、EC裁判所の負担が著しく増えたため、1988年、EU理事会は、EC条約旧第225条に基づき、第1審裁判所を設置した[3]。両裁判所を併せて、「EC裁判所」と呼ぶことがあるが、ニース条約は、第1審裁判所の独自性を示唆している(詳しくは こちら)。 第1審裁判所の裁判官は、各国より 少なくとも1名ずつ任命される(第224条第1項参照)。なお、第1審裁判所には法務官は設置されていないが、必要に応じ、判事が法務官としての役目を務めることができる(第224条第1項 およびEC裁判所規程第49条参照)。 第1審裁判所の管轄権は以下の通りである(第225条第1項前段)。 |
|
① |
EC諸機関の行為(法令)の無効の訴え(第230条) |
|
② |
EC諸機関の不作為確認の訴え(第232条) |
|
③ |
ECに対する損害賠償請求訴訟(第235条) |
|
④ |
EC・職員間の紛争に関する訴え(いわゆる、staff cases、第236条) |
|
⑤ |
仲裁条項に基づく訴え(第238条) |
|
|
また、ニース条約に基づき、第1審裁判所は、ある特定の分野に限り、先行判断 を下しうるようになった(第225条第3項)。さらに、新しく設置された小委員会の判断を審査しうる(第225条第2項)。 |
| (3) 司 法 小 委 員 会 |
|
EC裁判所の負担を軽減するため、1988年に第1審裁判所が設けられたが、EU拡大 やEU法の発展、また、第1審裁判所の管轄権の増加に伴い、第1審裁判所の負担も重くなっている。そのため、ニース条約は、第1審裁判所に附属する機関として、司法小委員会(judicial panels)の設置を認めている(EC条約第220条第2項、第225a条〔欧州憲法条約も同様に、ある特別な分野の訴えについて、第1審として審理しうる特別裁判所の設置を認めている(Article III-358)〕 )。これを受け、EU理事会は、EC・職員間の紛争に関する訴え(いわゆる 、staff cases)について審理する特別な裁判所(Civil Service Tribunal)を設置している(参照) (Decision 2004/752/EC of Council of 2. 11. 2004, OJ 2004, L 337, p. 7) 。 さらに、競争法やEC特許権に関する紛争を扱う司法小委員会の設置についても検討されているが、実現していない(第225a条参照)。なお、同小委員会は第1審裁判所の下に置かれるが(第220条第2項)、同裁判所には設置を要請する権限は与えられておらず、要請しうるのはEC裁判所と欧州委員会のみである(第225a条第1項)。 この新設の司法機関の判事は、現在、7名である(裁判官を選任するために設けられた特別委員会によって選ばれている)。任期は、他の裁判所の例に同じく6年である。 司法小委員会の判断に不服がある者は、第1審裁判所に控訴することができる。また、EC裁判所は、第1審裁判所のこの判断を審査することができる(第225条第2項)。
|
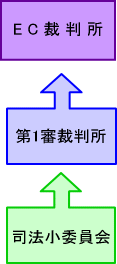 |
|
2.任 務 |
|
EC裁判所の任務は、EC条約(第1次法)の維持・解釈であるが(第220条)、これにはECの機関がEC条約に基づき制定した法規(第2次法)の維持・解釈も含まれる。さらに、一般的な法原則(例えば、基本権の保護や民主主義原則など、加盟国の憲法に一般に共通している原則)なども含まれるとされる。法の一般原則を援用することによって、EC裁判所は、EC条約の欠陥ないし不備を補うことが可能になる。 例えば、基本権保護の必要性は、当初、EC条約内に規定されていなかっため、EC裁判所は、その必要性を認めなかった。しかし、加盟国の裁判所(特に、ドイツ連邦憲法裁判所)の批判を受け、後に、これを法の一般原則として認め、ECにおいても基本権は保護されるべきであるとの判断を下した。なお、現在では、EU条約第6条において、基本権保護の必要性が明定されており、EC裁判所の管轄権も明瞭に認められている(EU条約第46条第d号)[5]。 「はじめに」でも述べたように、EC法の①適法性[6]や②その解釈について判断を下したり、加盟国のEC法違反について審査する権限は、EC裁判所にのみ与えられている(原則)[7]。加盟国裁判所が、これらの点について疑問を抱く際には、EC裁判所へ質問し、その解答を待たなければならない(先行判断制度、EC条約第234条参照)。 この手続やその他の訴訟手続の概要は、EC条約内で定められている。
EU条約に関しては、EC裁判所の権限は限定されおり(同条約第46条参照)、原則として管轄権を有さない。つまり、EUの 第2の柱 と 第3の柱 という政府間協力制度に関し、EC裁判所には原則として管轄権は与えられていない。そのため、同裁判所は、ECの裁判所であり、EUの裁判所ではないとされる。EU条約第35条第1項や第46条は、明瞭に、"Court of Justice of the European Communities" と定めている。また、他の規定からも、EC裁判所は、EUの機関ではないことが読み取れる。なお、アムステルダム条約に基づき、現在では、EC裁判所に従来より多くの管轄権が与えられている(EU条約第46条参照)[8]。 |
|
|
|
(1) 加盟国のEC法上の義務不履行確認の訴え(EC法違反確認の訴え)(第226条以下) |
|
欧州委員会は、ある加盟国がEC法に違反していると考える場合(例えば、ある加盟国が 指令 を置換期間内に置き換えなかったり、また、置換が不適説であるような場合)、その旨を同加盟国に通告しなければならない。委員会が定める期間内に、同加盟国が適切な措置を講じなかった場合、委員会はEC裁判所に提訴し、EC法違反の確認を求めることができる(第226条参照)。なお、近年、このような訴えの3分の1以上は、環境法 に関するものとされる(参照)。 |
|
|
|
同様に、各加盟国も、他の加盟国が条約に違反していると考えるときは、EC裁判所に訴えを提起することができるが(第227条)、非常にまれである。加盟国間で互いに提訴し合わない旨の合意が締結されたケースも2件ある[9]。 EC裁判所が訴えの内容を審査し、実際にEC法違反があると考えるときは、それを確認する判決を言い渡さなければならない。なお、同裁判所は、EC法に反する加盟国の措置を無効と宣言することはできない。そのため、違法状態は、加盟国自身によって除去されなければならない(第228条第1項)。 EC裁判所の判決に従い、加盟国が違法状態を除去しないとき、加盟国は新たにEC法に違反することになる(つまり、EC裁判所の判決に従う義務に違反する)。この義務違反が多発したため、マーストリヒト条約に基づき、制裁制度が導入された。つまり、委員会は、所定の期間内に必要な措置を講じるよう、加盟国に勧告しうるが(→ リスボン条約による改正は こちら)、それでも加盟国が適切な措置を取らない場合には、委員会は、EC法違反の程度、存続期間、また、違反国の国民総生産を考慮して課徴金額を決定し[10]、この制裁措置の発動をEC裁判所に要請することができる(第228条第2項)。同裁判所は、委員会が定めた課徴金額に拘束されないが、訴えられえた加盟国が当初の判決に従っていないと認定するときは、課徴金の賦課を命じることができる。なお、EC条約第244条と第256条[11]に基づき、この制裁措置に関する判決を強制執行することができるかどうは争われている。これを否定する見解は、第256条第1項第2文が、加盟国に対する強制執行を否認していることを指摘するが、①これは、EU理事会や欧州委員会の決定が加盟国に対して強制執行力を持たないことを定めたまでで、EC裁判所の判決の強制執行力まで否定すべきではないこと、また、②課徴金に関する判決に強制執行力がないとすれば、加盟国がそれに従うことはなく、制度の意義が失われる。そのため、この問題は肯定すべきである[12]。 ところで、マーストリヒト条約に基づき導入された、この制裁措置が実際に発動された事例は1件しかない[13]。もっとも、その後、EC法違反状態を迅速に改善したため、問題の加盟国(ギリシャ)は課徴金を支払わずに済んだ。 |
|
|
国内法がEC法に合致していなかったり、加盟国が指令を所定の期間内に置き換えないことを理由として、欧州委員会が加盟国を訴えるケースは少なくないが、EC法違反の事実は、委員会によって証明されるため、EC裁判所が判断に困ることはまれである。もっとも、その他の事由に基づき同裁判所の訴訟手続は一般に長期化するため、その期間中、違法状態が存続するといった欠点がある。
|
|
EC裁判所は、諸機関(EU理事会、欧州委員会、欧州議会および欧州中央銀行)が制定した拘束力のある法令の適法性について判断しうる。すなわち、勧告および意見を除く法令の審査をEC裁判所に求めることができるが、訴えの理由となりうるのは次の通りである(第230条第2項)。 ・ 権限の欠缺 ・ 重大な手続要件違反(参照) ・ EC条約や第2次法違反 ・ 裁量権の濫用 要するに、これらの何れかがEC裁判所によって確認されると、第2次法は無効と宣言される。なお、訴えは、問題の措置が①告知されたとき、②原告に通達されたとき、③それらが不可能な場合には、原告が措置について知りえたときから、2ヵ月以内に提起されなければならない(第230条第5項)。提訴期間の制限は、法秩序の混乱を回避し、また、EC裁判所の負担を軽減するためである。
|
|
|
この訴えを常に提起しうるのは、加盟国、欧州議会、EU理事会と欧州委員会のみである(特権的原告)(第230条第2項)。これに対し、会計検査院と欧州中央銀行は、自らの権利を擁護する場合に限って、訴えを提起しうる[14]。また、個人は、訴訟の対象となる法規の影響を「直接的」かつ「個人的に」受ける場合にのみ提訴しうる(同条4項 ⇒ リスボン条約による改正は こちら)[15]。なお、個人の訴えは、EC裁判所ではなく、第1審裁判所に係属する。
なお、EC条約第230条第4項は、私人は、①自らに対し発せられた「決定」、②第3者に対して発せられた「決定」であるが、自らに直接的かつ個人的に関わる「決定」や、③「規則」として制定されたものの、自らに直接的かつ個人的に関わる法令の無効宣言のみを求めることができると定める。もっとも、現在、EC裁判所は、このように法令の形式(「決定」であるか、「規則」であるか)を重視しておらず、「直接的」要件と「個別的」要件が満たされているかどうかについて検討している。例えば、ある特定の輸出業者に対する
ダンピング防止税 の賦課は、通常、「規則」の形で発せられるが、この「規則」が原告に直接的かつ個人的に関わるかどうかが審査され、これが認められると、同人の訴えは適法となる。 前述したように個人の提訴権が制限されているのは、EC裁判所に多数の訴えが係属することを防止するためである。もっとも、この要件を厳格に解し、個人の裁判所へのアクセスを制限すると、権利保護が実際に必要な者の訴えも不適法となり、ECの権利保護制度は形骸化しかねない。そのため、EC裁判所は、かつて、この要件を緩やかに解釈したことがある[18]。また、2002年、第1審裁判所は、一般人を対象にしたEC法規であれ、それによって、原告の権利が侵害されていることが明らかな場合には、訴えを許容した[19]。また、同様のケースで、法務官も訴えの適法性を緩やかに解釈すべきとの意見を述べたが、EC裁判所はこれに従わず、前掲の第1審裁判所の判旨の妥当性も実質的に否認した[20]。欧州人権裁判所も、EC裁判所による審査(国内裁判所による先行判断の付託に基づく)の可能性が排除されていない限り、欧州人権条約第6条(公正な裁判を受ける権利)や第13条(実効的な救済を受ける権利)の侵害は存在しないと判断している(詳しくは こちら)。
EUの立法機関である理事会が多数決によって法律を制定する場合、 議決に敗れた加盟国はEU法の有効性を争い、提訴することが少なくない。加盟国の提訴は、その他に、提訴権が制限されている個人(自国民)の権利保護という役割を持っている。
(3) 不作為違法確認訴訟(第232条) |
|
欧州議会、EU理事会、欧州委員会または欧州中央銀行が、EC法に反し、ある行為を取らない場合には、EC裁判所にその不作為の確認を求めることができる(第232条)。被告となるのは、これらの機関に限られる。 他方、原告になりうるのは、加盟国、すべての機関と欧州中央銀行である。その他、私人も訴えを提起しうるが、もっとも、これは、ECの機関が勧告や意見以外の拘束力のある法令を同人に対し発することを怠り、それがEC法に違反する場合に限られる(第232条第3項)。万人に適用される法令の制定を怠ったとして訴えを提起することは許されない。 |
|
|
なお、提訴に先立ち、問題の諸機関に作為を要請する必要がある。それより2ヵ月以内に、回答が得られない場には、それから2ヵ月以内に訴えを提起しなければならない(第232条第2項)。 EC裁判所が、EC諸機関の不作為が違法と判断するときは、その旨を確認する判決を下さなければならない。なお、EC裁判所は不作為の違法性を確認するのみで、諸機関に作為を命じることはできない。不作為の違法性が確認された場合、諸機関は、この違法状態を除去しなければならない(第233条第1項)。EC裁判所の判決にもかかわらず、諸機関が適切な措置を講じない場合は、再度、不作為確認の訴えを提起することができる。なお、諸機関の不作為に対し、損害賠償 を請求することもできる(第2項、第288条第2項)。 (4) 先行判断手続(第234条) EC法の適用・執行は、主として、加盟国の行政機関によってなされる。例えば、ECがある輸入品の関税に関する規則を制定する場合、それに基づき、関税を徴収するのは、加盟国の役割である。そのため、輸入業者がこれを不服として訴える場合は、徴収する国の裁判所に提起しなければならない(なぜなら、加盟国が徴収しているためである)。受訴裁判所が、関税の取り立てに関するEC法の適用や有効性に疑義を抱く場合は、自ら判断してはならず(これは、加盟国の裁判所が判断すれば、各国で判断が異なり、EC法の適用の統一性が害されるだけではなく、そもそも、国内裁判所は外部の法の有効性について審査する権限を持っていないことなどによる)、EC裁判所に判断を求めることになる。そして、EC裁判所の判断に従って、国内裁判所は判示することになる。このように、国内裁判所が自らの判断に先立ち、EC裁判所に判断(先行判断)を求める手続を先行判断手続という(EC条約第234条)。 |
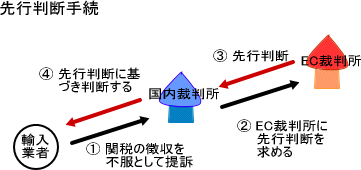
国内の最終審は、EC裁判所に判断を求めなければならない(第234条第3項)。他方、下級審は、EC法の解釈に関しては先行判断を求めなくてもよいが(第2項)、EC法の有効性については求めなければならない。なぜなら、EC法の有効性は、EC裁判所のみが判断しうるためである[23]。 なお、アムステルダム条約に基づき、EC条約内に挿入された司法協力に関する規定(第61条以下)については、国内の最終審のみが先行判断を求める権限を有する。 |
|
|
EC裁判所の手続には、国内訴訟手続の当事者、全加盟国政府、また、欧州委員会やその他の機関も参加し、意見を述べることができるが、裁判所は抽象的に判断する。そのため、先行判断は、それを求めた国内裁判所だけではなく、判例法として、事後の事件にも拘束力を持つ。
(5) 損害賠償請求訴訟(第235条、第288条) ECの機関やその官吏の職務行為よって損害が生じた場合、加盟国や個人は、EC裁判所または第1審裁判所に訴えを提起し、その賠償を請求することができる(第235条、第288条第2項)。例えば、EC法の適用によって損害を受けた者は、第1審裁判所に提訴し、その賠償を請求することができる(バナナ市場規則の適用より生じた損害の賠償請求)。ただし、損害の原因となるEC法が違法であること(重大な法令違反、つまり、裁量権の濫用が明白かつ著しい場合でなければならない)、また、その法令の適用と生じた損害との間に直接的な因果関係が存在しなければならない(参照)。これらの証明責任は原告が負う。 |
![]() 損害賠償請求が認められるための要件
損害賠償請求が認められるための要件
|
① |
ECの行為が違法であること |
|
② |
損害が発生していること |
|
③ |
違法行為と損害の発生に因果関係があること |
|
個人は第1審裁判所に、また、加盟国はEC裁判所に訴えを提起しうる。なお、裁判所は、上掲の要件の充足を順番に審査する必要はない。つまり、何れかの要件が満たされないことが明らかになるときは、他の要件について調査することなく、訴えを棄却しうる(Case C-146/91, KYDEP [1994] ECR I-4199, paras. 19 and 81; Case T-170/00 Förde-Reederei [2002] ECR II-515, para. 37)(参照)。 なお、EUの第2、第3の柱 において、損害賠償請求請求は認められない。つまり、共通外交・安全保障政策 および 刑事に関する司法・警察協力 に関する措置によって損害を被った者は、EC裁判所(第1審裁判所)に訴えを提起し、損害の賠償を請求することができない(詳しくは こちら)。
(6)「意見」手続(第300条第6項) EU理事会、欧州委員会または加盟国は、ECが締結を予定している国際条約とEC法の適合性をEC裁判所に審査させることができる(第300条第6項)。 なお、ニース条約に基づき、欧州議会も意見を求めることができるようになった。 EC裁判所の「意見」(鑑定)は、拘束力を持ち、EC法との矛盾が指摘された条約は締結することができない。実際に、EC裁判所の「意見」が求められたケースは少ないが(参照)、その中で下された判断は、比較的大きな注目を集めている。
(7) 仲裁手続(第238条、第239条) ECが第3国と締結する条約や、EU加盟国間の合意に、EC裁判所を仲裁裁判所とする旨の条項が含まれている場合、同裁判所は仲裁判断を下すことができる(第238条、第239条)。実際には、これは、第1審裁判所の管轄に属するが、同裁判所は、仲裁条項で定められた法令(国内法であってもよい)を適用することになる。
(8) EC・官吏間の訴訟手続(いわゆる、staff cases(第236条)) EC官吏規則に基づき、EC裁判所は、ECと官吏間の訴えについて審理しうる(第236条)。なお、実際には、この訴えの管轄権は 、前述した Civil Service Tribunal に委譲されている。
さらに、第1審裁判所には、1996年より、EC商標に関する訴えの管轄権が与えられている。
EC裁判所や第1審裁判所の訴訟手続は2年以上継続することが一般的であるが、訴え(例えば、法令無効の訴え)の提起によって、審理される法令の適用は停止しない(違法と考えられる法規も、実際に違法性が確認されるまで適用され続ける)。実効的な権利救済を可能にするため、両裁判所は、仮処分を行うことができる(第243条)。 |
|
4.リ ン ク |
| ・ EC裁判所の公式サイト ・ EUの司法制度 |
|
脚注 (本文中に戻るときは、行頭の注番号をクリックしてください) |
|
これは、各加盟国の法制度をECの司法制度ないし司法判断に反映させることによって、EC裁判所の信頼やその判断の正当性を高め、EC裁判所の判例が各国に受け入れやすくするためである。 |
|
|
EC裁判所が法務官の「意見」とは異なる判断を下すのは、15%未満であるとされる。Cf. Streinz, Europarecht, C.F.
Muller Verlag, Heidelberg, 5th edition, 2001, para. 328. |
|
|
第1審裁判所を設置するための理事会の決定 88/51(1988年10月24日)を参照されたい。なお、この決定はニース条約によって廃止された。 |
|
|
注3内の決定(1993年6月8日改正)第3条を参照。 |
|
|
EU条約制定当時は、第6条の基本権保護に関するEC裁判所の権限は否認されていたが、アムステルダム条約に基づき、これが認められるようになった。 |
|
|
例えば、ECの機関が制定した法律(第2次法)はEC条約(第1次法)に反するため、無効であるかどうかが問題になる。 |
|
|
その例外は、仮の権利保護制度において認められる。これは、EC裁判所の判断を待っていては、実効的な権利保護がなしえないことに基づいている。もっとも、その場合、加盟国の裁判所は、EC裁判所に判断を求めなければならない。 |
|
|
削除 |
|
|
Case 141/78, France v. UK [1979] ECR 2923; Case C-388/95, Belgium v. Spain [2000] ECR I-3123. |
|
|
Cf. OJ 1996, C 242, 6 and OJ 1997, C 63, 2. See also Case C-387/97, Commission v. Greece [2000] ECR I-5047, paras 84-99. なお、課徴金額は、総額であってもよいし、条約義務違反が改善されるまでの、一日当たりの額を定めることもできる。 |
|
|
第244条は、EC裁判所の判決は、第256条に従い強制執行することができると定める。 |
|
|
Arndt, Europarecht, 6. Auflage (Heidelberg 2003), S. 62. |
|
|
2000年6月4日の判決において、EC裁判所は、環境指令の置き換えを怠ったギリシャに、一日当たり、2万ユーロの支払いを命じた。Case C-387/97,
Commissionv. Greece[2000] ECR I-5047. |
|
|
なお、従来、欧州議会も、同様に、自らの権利を擁護する場合に限り、訴えを提起することができたが、ニース条約に基づき、このような制限は撤廃された。 |
|
|
加盟国内の地方公共団体の原告適格も、個人(この場合は、法人)に準じる。Case T-607/97, Regione Puglia, [1998] ECR II-4051, paras. 15-17; Jointed Cases T-132/96 and T-143/96, VW Sachsen, [1999] ECR II-3663, paras. 81. |
|
|
Case 59/83, Biovilac [1984] ECR 4057. |
|
|
Case 25/62, Plaumann [1963] ECR 213 (238). |
|
|
Koenig and Haratsch, Eurparecht, 4th edition, Mohr 2003, para. 386. |
|
|
Judgment of 3 May 2002, Case T-177/01, Jégo-Quéré v. Commission [2002] ECR II-2365, para. 51. |
|
|
Judgment of 25 Juli 2002, Case C-50/00 P, Union de Pequen Agricultores [2002] ECR I-6677, paras. 34 et seq.; Case C-263/02 P, Jégo-Quéré, EuZW 2004, 343, para. 36. |
|
|
Case C-106/96,UK v. Commission [1998] ECR I-2729, para. 41. |
|
|
Case C-295/90, Parliament v. Council [1992] ECR I-4193, paras. 26-27. |
|
|
これは、EC条約で定められているわけではなく、EC裁判所の判例によって確立された原則である。Case 314/85, Foto-Frost [1987] ECR 4199.
|
|
|