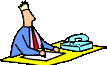|
「EU域内におけるサービス自由化」 |
はじめに 2. サービス市場の自由化に関する諸原則 3.将来の課題 ※ 参照リンク |
(1) サービス取引の重要性
EUのGDPの70%はサービスで占められているが、加盟国間にまたがるサービスは20%に過ぎない。これは、経済統合の発展にもかかわらず、国内の規制が依然として残されており、国境を越えたサービス提供の自由が阻害されていることによるとされている(
域内市場の完成というEC条約上の目標を達成するだけではなく(EC条約第14条参照)、新しい雇用を創出するため、サービス市場を自由化する必要性は、リスボン戦略 の中でも確認されている(参照)。
(2) ECの政策やEC法上の意義(基本的自由の保障) EC条約はECに多くの権限および責務を与えているが、商品、人、サービス、資本が自由に移動しうる 域内市場 の創設は、最も重要な政策課題の一つにあたる。サービス市場の自由化は、この課題を実現する上で、極めて重要である。 このような政策的観点からだけではなく、法的観点からも、サービス市場の自由化は非常に重要である。つまり、商品、人、サービス、資本の移動の自由は、EC法上の基本的自由として厚く保障されなければならない。なお、詳しくは後述するように、サービス提供の自由とサービス市場の自由化は完全に同一ではない。
欧州委員会は、域内市場を以下のように分類している。
・Single Market for goods 商品 ・Single Market for services サービス ・Single Market for capitel 資本 人?
これは、域内市場では、商品、人、サービス、資本の移動の自由が保障されるという理念に沿っているが(EC条約第14条参照)、以下の点に注意を要する。
① 「人の移動の自由」は、(a) 労働者の移動の自由と (b) 開業の自由に分類される(詳しくは こちら)。これらの自由は、Single Market for services の中で保障される。
② 「サービス」とは、自営業者のサービスを指す。非自営業者の場合は、①(a) の労働者の移動の自由として保障される。
③ 運輸・交通サービスは、Single Market for services の中に含まれない(第51条参照)。 他方、金融サービスはSingle Market for services に含まれる(Single Market for capitel の対象ではない → EC条約は、資本の移動を伴うサービスについて詳細に定めていない)。
まとめ: Single Market for services とは、EC条約が別個に規定している分野を除く産業部門を対象とし、自営業者ないし非自営業者が自由に役務を提供し、また、経済活動を行うことを目的とした法人ないしその施設の設立が自由に行える空間を指す。なお、欧州委員会の管轄は、自営業者と非自営業者で分かれている。
サービス市場について調べるときは、「サービス提供の自由」だけではなく、「人の移動の自由」(労働者の移動と開業の自由)についても見る必要がある。
ECは、加盟国の国民が域内で自由にサービスを提供し、また、法人を設立することを保障している。詳細は以下の通りである、
① 自由化の恩恵を受けるのは、EU加盟国の国民(EU市民)のみである。 サービス提供の自由に関しては、さらに、EU内に居住していなければならない。
→ 第3国の国民がEC企業で働くときは、同人も保障の対象となる。
② サービス市場の自由化は、主として、国籍に基づく差別を禁止している(内国民待遇)。 つまり、他の加盟国の国民が自国内で自由にサービスを提供し、または、開業することを保障する。ECが加盟国の市場を自由化ないし民営化することは、むしろ例外的である(→ ある加盟国で民営化が実施されていない場合には、他の加盟国の国民は参入しえない)。 EC条約上、国籍に基づく差別の禁止が義務付けられているのは加盟国であるが、私人もこれが義務付けられることがある(私人間効力)。また、加盟国は、差別を禁止するだけではなく、法益の実現を阻害する要因を除去しなければならない。
③ サービスを提供することだけではなく、サービスを受けることも保障される(参照)。
④ EC法上の自由は、複数の加盟国間にまたがってサービスが提供される場合に保障される。一国内での事象は対象外である。
⑤ EC条約では、人、サービス提供、開業の自由の諸原則(例えば、内国民待遇)について規定しているが、具体的な政策は、第2次法(指令)の制定を通じなされる。第2次法が制定されない場合は、EC条約内の規定が直接的に適用されうる(直接適用性、直接的効力)。
第2次法は、国内法の調整を目的としている(国内制度を統一するわけではない)(参照)。
⑥ EU市民が他の加盟国でも自由に働くことができるよう、学位や職業資格の相互承認制度が整備されている。資格に関しては、原則として、本国(取得国)の法令が適用される(本国法主義)。
⑦
他の加盟国内で働くEU市民の社会的側面(賃金や勤務時間など)についても、本国法主義によるが、受入国(労働地国)は、自国の法令(私人間の労働協約を含む)を同時に適用することができる(
⑧ 公権力の行使を伴う職業については、他の加盟国の国民のアクセスを制限しうる。また、公序、公安ないし公衆衛生上の理由に基づき、加盟国は他の加盟国の国民の参入を制約しうる。 ・ 開業の自由 ・ サービス提供の自由
① EC法体系の簡素化 サービス市場の自由化を保障するため、これまで、ECは多数の法令を制定してきたが、これを整理・統合し、EC法体系を簡素化する必要性が認識されている。
・ 資格の相互承認
② 国内障壁の削減 EC条約は、主に、国籍に基づく差別を禁止しているが(前述参照)、自国民と他の加盟国の国民を平等に扱うのでは不十分な場合がある。経済活動の開始や継続に関する行政手続を簡素化し、サービス提供と開業の自由の保障を実効的にする必要がある。
2004年5月の東方拡大以降、労働者保護水準の低い東欧諸国より、同水準の高い西欧諸国に労働者が大量に押し寄せ、従来のEU加盟国内の労働市場をますます悪化させることが懸念されている(→ 欧州憲法条約の批准に関する国民投票にも影響を与えた)。サービス市場の自由化の前提として、ヨーロッパ型社会モデルの形成ないし域内労働水準の格差を是正することが必要とされている。
|
| (参照) |
「EU法講義ノート」のトップページに戻る