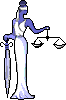 |
E. 訴 訟 の 審 理
|
1. 当事者主義と職権主義 1.1. 当事者主義 民事訴訟手続では当事者双方(原告と被告)が積極的ないし主導的に主張・活動し、裁判所は中立的な立場から双方の主張について判断を下す。このような審理方式を
当事者主義 と呼ぶ。この原則の下、当事者には、①訴訟の開始と終了、また、訴訟の対象を特定する権限と責任だけではなく、②裁判の基礎となる事実や証拠の提出に関する権限と責任が与えられている。①を
処分権主義 と言い、②を 弁論主義 と言う。 |
|
|
(1) 処分権主義 前述したように、処分権主義とは訴訟の開始・終了や訴訟対象の特定に関し、当事者に決定権を与える原則を指す。これは、民事訴訟の対象となる私人間の法律関係には
私的自治の原則 が適用されることを民事訴訟制度に反映させたものであるが、後述する 職権調査主義 と対比する概念である。 |
|
① |
訴訟の開始 近代法は、国家は個人の自由を尊重し、私人の生活にみだりに介入してはならないという考え(自由主義の原理)に基づいている。それゆえ、国の司法機関である裁判所が自発的に私人間の紛争に干渉することは許されず、裁判は当事者の申立てがあった場合にのみ開始される。これを「訴えなければ裁判なし」ないし「不告不理の原則」と呼び、民事訴訟手続の基本原則の一つとなっている(参照)。民事訴訟法は、この原則について直接的に定めていないが、「裁判所は当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」と定める第246条は、前掲の原則を前提にしている。
|
|
② |
判断対象の特定 当事者が申し立てに対し、量的に多くの、また、質的に異なる裁判をすることは許されない(第246条)。
例えば、AはBに1000万円の債権を有しており、その内の600万円についてのみ訴求するときは、裁判所は600万円の支払いについてのみ判決を下すことができ、1000万円全額については判断しえない。なお、裁判所は審理の結果、600万円のうち、300万円の支払いのみを認容することができる(一部認容判決) 。請求額の一部であれ、訴えが完全に退けられるよりは原告にとって有利であり、また、600万の債権が争点になったのであるから、その一部を認容する判決は、被告にとっても不意打ちにはならない(当事者の裁判を受ける権利を保障するため、裁判手続で争われなかった事項について判決を下してはならない)。 原告は無条件で売買代金を支払うよう求めているのに対し、被告が商品の引渡しがあるまで支払いを拒むと主張するとき(同時履行の抗弁)、裁判所は請求を棄却するのではなく、商品の引渡しという条件付で給付判決を下すべきとされている(請求を棄却しても、紛争が解決されるわけではないため)。
前述したように、裁判所は、申立てより多くの権利・利益を当事者に与えることは処分権主義に反し、許されないが、土地の境界の確定や、共有物分割の訴え (民法第258条)に関し、裁判所は原告が主張する境界線や分割方法に拘束されない (そのため、裁判所は原告により有利になるような境界線を確定したり、原告に有利に共有物を分割することができる)。これは、これらの訴えが非訟的性格(参照)を有するためである。
|
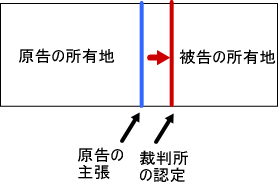 |
|
|
ところで、離婚の訴えが認められる理由は民法第770条で列記されているが、裁判所による権利ないし法律関係の形成(非形成)の基準が法律で定められていない場合がある。例えば、前掲の土地の境界確定、共有物の分割(民法第258条)、また、父の決定(民法第773条)などであるが、これらを目的する訴えを 形式的形成訴訟 という(参照)。
当事者が土地所有権の確認を求めている場合(確認の訴え)、裁判所は、その明け渡しを認める判決(給付判決)を言い渡してはならない。その逆も同様である。
|
|
|
③
|
訴訟の終了 当事者は訴えの取下げまたは上訴の取下げにより、訴訟手続の全部または上訴審手続を 遡及的に消滅させることができる(第261条、第262条、第292条、第313条)。また、請求の放棄や認諾、訴訟上の和解により訴訟を終了させることもできる(第266条および第267条参照)。 |
|
(2) 弁論主義 弁論主義とは裁判に必要な事実に関する資料の収集は当事者の権能かつ責任であるとする原則を指す。後述する 職権探知主義 に対峙する概念である。
|
| ① | 当事者が主張しない事実は裁判の基礎にしてはならない。 |
|
② |
当事者間で争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない。 |
| ③
|
当事者間で争いのある事実の認定は、当事者が申し出た証拠に基づき行わなければならない(⇒職権証拠調べの禁止)。 |
|
当事者主義に対し、裁判所に権限と責任を認める原則を 職権主義 と呼ぶ。 手続の進行は、他の手続利用者の利害にも関わるため、当事者の自由には任せず、裁判所が指揮する(詳しくは こちら)。 訴訟上の案件(訴訟法上の問題)や、適用される実体法の選択・内容について(参照)、裁判所は当事者の申立てをまたずに、自ら進んで調査し、判断する(しなければならない)。これを職権調査主義と呼ぶが、当事者の申立てがなくても調査される点で、前述した
処分権主義 に対比される。職権調査の対象となる事項を職権調査事項と言うが、その例は以下の通りである。
当事者は合意や責問権の放棄によって、これらの調査を省略させることはできない。なお、これらの調査に関する異議の申立ては、時間的に制限されない。 人事訴訟については、真実を発見する必要性が高く、また、判決の効力が第三者にも拡張されるため、判断の基礎となる資料は裁判所によって収集される(職権探知主義〔人事訴訟法第20条、第19条第1項参照〕)。また、通常の訴訟においても、公益性の強い案件(裁判権や 訴訟能力 など)については同様である。訴訟資料を裁判所が収集し、裁判所は当事者が提出しなかったものまで、裁判の基礎にすることができるという点で、前述した
弁論主義 に対比する。 |
|
|
なお、裁判所は職権で探知した事実や証拠調べの結果を当事者に開示し、その意見を聞く必要がある。そうでないとすれば、当事者に不意打ちな判決となるためである(人訴第20条但書、行訴第24条但書)。 当事者の申立てがなくとも、裁判所が職権で調査しなければならない事項(→ 職権調査事項)の多くは、裁判所が職権で資料を収集するが(→ 職権探知主義)、当事者がその収集について責任を負う事項もある(→
弁論主義)。例えば、任意管轄、訴えの利益、また、当事者適格の有無は、いずれも裁判所が職権で調査しなければならないが、その判断の基礎となる資料は当事者が提出しなければならない(裁判所は当事者が提出した資料に基づき判断する)。 |
|
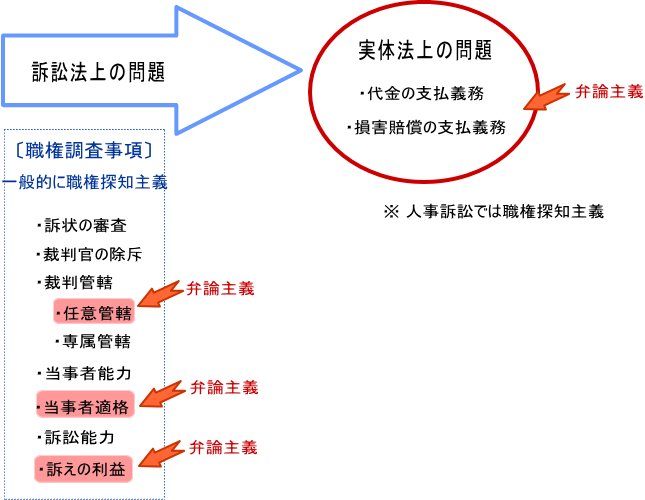
|
|
「民事訴訟法講義ノート」のトップページに戻る