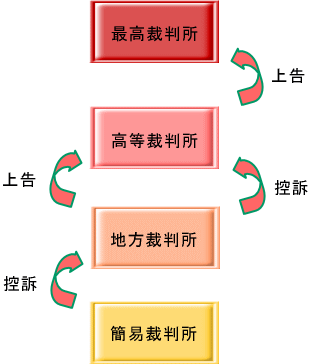| 準 拠 法 と し て の 外 国 法 の 適 用 |
|
1. 問題の所在 ある外国の法令が準拠法に指定されるとき、裁判所は、その法令について調査した上で、適用しなければならないが、それは非常に困難な場合がある。例えば、準拠法国との間に国交が樹立されておらず、調査がスムーズに行えないことがある。また、そもそも外国には適用されるべき法令(ないし法制度)が存在しない場合もありうる[1]。 準拠法に指定された外国法の内容を解明しなければならないのは誰か(裁判所か、それとも当事者か)、また、その内容が判明しない場合には、どのようにすればよいであろうか。さらに、裁判所が外国法を誤って適用した場合には、上告しうるかどうかという問題もある。本来、これらは 国際民事訴訟法 の問題であるが、準拠法の決定を使命とする国際私法にも密接に関係するため、国際私法総論でも検討することにする[2]。
2.外国法の内容の主張・証明責任 - 外国法の法的性質
準拠法
となる外国法の内容の確定に責任を負うのは誰か。この問題に関しては、以下のような見解が主張されている。 ・ 国内の裁判手続において、外国法は単なる事実にすぎず、その主張・証明は当事者の責任であるとする見解 この理論によれば、外国法の内容が明らかに ならないとき、当事者は敗訴する。
・ 旧民訴法第219条(明治23年)はこの立場に立っていたが[4]、大正15年の改正の際に削除された。 ・ この見解は、特に、内外法平等の原則に反する( つまり、国内法の内容の確定は、裁判所の責任おいてなさなければならないが、外国法については、これとは異なる取り扱いがなされる)として批判される。
(2) 外国法法律説(我が国の通説・判例) 「裁判官は法を知る」という格言に基づき、裁判官が外国法の内容を調査する役目を負うと解する立場であるが、その理由付けに関しては、以下のように見解が分かれている。
① 条理説 (我が国の従来の多数説・判例[5]) 法欠缺の場合に同じく、条理によって補充するとする見解 この見解に対しては、条理とは何であるのか、また、外国法における条理の確定は困難であることから、結局は日本の条理が基準となり、これは内国法の優先につながるとして批判されている。 ② 最近似法適用説(近似の学説・判例) 準拠法に最も類似する法秩序(すなわち第3国法)を探求して、これを適用するとする立場。 この説によれば、準拠法の決定に際し、裁判所の恣意的な判断は排斥されるが裁判所の負担を増すだけではなく、比較法的アプローチによって結論がでるとは限らないといった欠点がある。
死後認知に関する問題の準拠法が北朝鮮法とされたケースにおいて、東京地裁は、大韓民国(韓国)の法律を適用せず、北朝鮮と同じ社会主義的法類型に属するチェコスロヴァキア、ポーランド、ソ連の判例を考慮して判示した(東京地判昭和51年3月19日)。
国内法の適用違背については、上告が明文で認められているが(民訴法第312条第3項、第318条第1項参照)、準拠法となる外国法の適用を誤った場合の取り扱いについては、見解が対立している。
なお、我が国の国際私法(適用通則法)が誤って適用されたために、(誤った)外国法が準拠法として適用された場合には、上告をなしうることは明らかである。なぜなら、これは、我が国の法律(すなわち適用通則法)の適用違背にあたるからである。 ① 上告否定説
外国法の内容の判断に関する上告を認めることは、上告審の負担を増やし、また、上告審が誤判を犯す場合には、その権威を損なうため、上告を許容しないとする見解である。 ② 上告肯定説(判例[6]・多数説) 内外法を平等に扱うべきであるため、上告を認めるべきとする立場である。外国法の適用の誤りは、外国法の適用を命じる国際私法(適用通則法)の適用を誤ったことと解されるから、我が国の法律の適用を誤ったものとして上告できるとみる立場もある[7]。
また、国内裁判所の判断を統一するため、さらに、上告審にはより優れた調査手段が備わっていることから、上告を認めてよいとする。この場合、民事訴訟法の規定に従い、上告する必要がある(民訴法第312条および第318条第3項参照)。
[1] その他に、準拠法が定まらない場合はどうすればよいかという問題もある。この点について、後述する大阪地判昭和35年4月12日を参照されたい。 [2] この点につき、道垣内「ポイント国際私法 総論」231頁以下参照。 [3] 大阪地判昭和35年4月12日、外判例百選26頁以下参照。 [4] 「地方慣習法、商慣習及ヒ外国ノ現行法ハ之ヲ証ス可シ裁判所ハ当事者カ其証明ヲ為スト否トニ拘ハラス職権ヲ以テ必要ナル取調ヲ為スコトヲ得」。この規定からも明らかなように、裁判所は、外国法の内容を職権で調査することができるが、それは義務ではない。同旨大判明治38年10月30日(民録11輯(しゅう)1439頁)。 [5] 長野家裁審判昭和57年3月12日、前掲渉外判例百選28頁以下(根元)参照。 [6] 最判昭和56年7月2日 前掲渉外判例百選30頁以下(桑田)参照。 [7] 江川英文『国際私法』113頁参照。
|