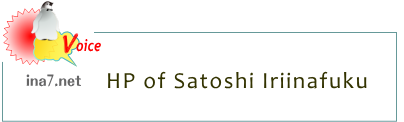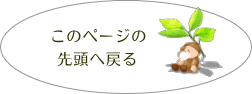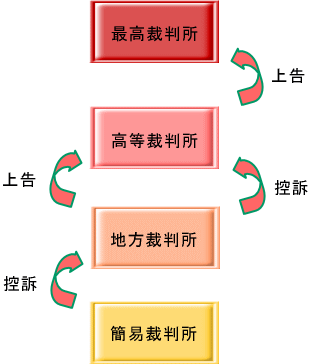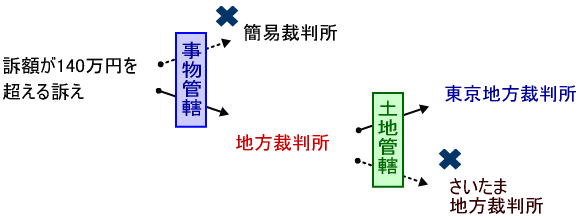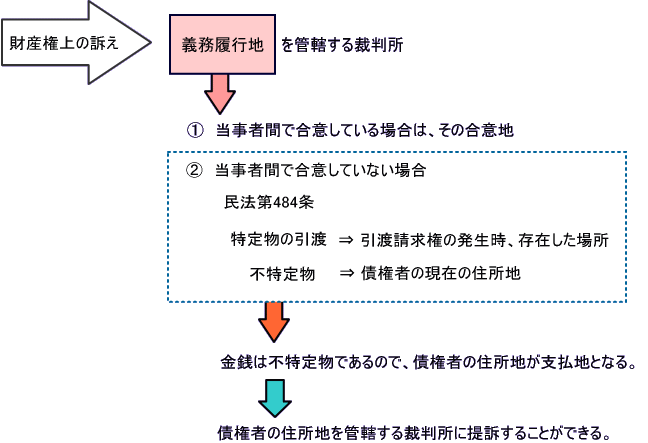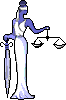 |
B. 受 訴 裁 判 所
|
1.1. はじめに 我が国には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という5種類の裁判所が設けられている(憲法第76条第1項、裁判所法第2条第1項参照)。最高裁判所は東京都千代田区に1つのみ設置されているが、それ以外の下級裁判所は全国に多数設置されている。
1.2. 管轄の種類 裁判所は異なる職務を行うが、その配分に関する定めを職分管轄と呼ぶ。例えば、判決手続は受訴裁判所が行い、執行手続は執行裁判所の職分となる。
(2) 事物管轄 簡易裁判所と地方裁判所の職務は事件の内容に応じ配分されるが、事件の内容を基準にして定まる管轄を事物管轄と呼ぶ。
(3) 土地管轄 事物管轄により、例えば、地方裁判所が第1審裁判所に決まると、次は、国内のどの地方裁判所に訴えを提起すればよいか検討する必要がある。裁判所間の管轄区域(地理的な職務担当範囲)は予め定められており、例えば、東京都内は東京地方裁判所、埼玉県内はさいたま地方裁判所の管轄となる。
民事訴訟法第4条によれば、被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することができる。そのため、被告の住所地が東京都内にあれば、東京地方裁判所に提訴しうる。このように、同種の裁判権を行使しうる裁判所間の地理的な職務分担に関する定めを
土地管轄 と呼ぶ。また、土地管轄を決定するための基準(例えば、前述した被告の住所地)を 裁判籍 と言う。
前述したように、民事訴訟法第4条は、被告の住所地を管轄する裁判所に管轄権を与え、これを原則的な管轄としている。これは、被告の住所地の裁判所に出頭しなければならないとすると、原告は慎重に行動し、むやみに訴えることを慎み(濫訴の防止)、また、自らの住所地で裁判するならば、被告は自らをより良く防御しうる(被告の防御権の保護)との考えに基づいている(被告の住所または居所を普通裁判籍にする理由)。
被告の住所地を管轄する裁判所への提訴を原則とする点で、被告の住所地を普通裁判籍 と呼ぶが、民事訴訟法は以下の特別裁判籍を認めており、それに基づき決定される裁判所に提訴することも認められるとしている(第5条以下参照)。つまり、受訴裁判所訴としては複数の裁判所が考えられ、その内のどの裁判所に提起するかは原告の判断に委ねられる(なお、同一の訴えを複数の裁判所に提訴することは禁止される(二重起訴の禁止)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||