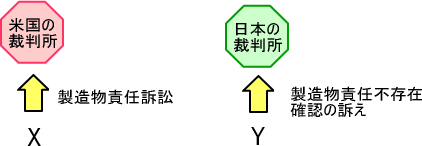1�D�͂��߂� �@����܂ł̎��Ƃł́A���ۖ����������������ꍇ�A�ǂ̍��̍ٔ����ɑi�����N����悢���Ƃ������i���ۍٔ��NJ��Ɋւ�����j�ɂ��Đ��������B�ٔ��NJ��Ɋւ��ẮA�䂪���̖����i�ז@�̒��ɂ��K�肪���邪�i��4���ȉ��j�A�����͍��������Ɋւ��ēK�p�������̂ł���A�O�����ɂ͓K�p����Ȃ��Ɖ�����Ă���B�]���āA���ۍٔ��NJ��ɂ��ẮA�����ҊԂ̌�����ٔ��̓K���E�v�����ȂǂƂ��������ɏƂ炵�Ĕ��f����̂������ł���Ƃ����B�����Ƃ��A�����i�ז@���̍ٔ��NJ��Ɋւ���K��̓��e���������Ɍ�����Ƃ������̂ł͂Ȃ����߁A�����̋K����Q�ނ��č��ۍٔ��NJ������肵�Ă��悢�ƍl�����邪�i�ō��فu�}���[�V�A�q�������v�Q�Ɓj�A�������A����ł͓����҂̌����ɔ�������A�܂��͍ٔ��̓K����v�����Ȃǂ̗v���ɔ�����Ƃ������s�s����������ꍇ�ɂ́i���Ȃ킿�A���i�̎��������ꍇ�ɂ́j�A�𗝂ɏƂ炵���肷��Ƃ����B�]���āA���{�̖����i�ז@��A���{�����̍ٔ������NJ�����L���A���{�̍ٔ����ɊNJ�����^���Ă��s�s���������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�䂪���̍ٔ������ٔ����Ȃ�����ƌ�����B �@���̂悤�ɁA�����@�̋K��ɏ]���č��ۍٔ��NJ������肳���Ƃ���A�䂪���̖����i�ז@���������ٔ����̊NJ�����F�߂Ă��邩��A�i���������̍ٔ����ɒ�N����邱�Ƃ����肤��B�܂��A���ۑi�����ɂ����ẮA�ȉ��̂悤�Ȏ��Ⴊ���ۂɐ����Ă���B
�@ �@�i���������̍ٔ����ɌW�����邱�Ƃ��i�����Ƃ����B������
�Ƃ�������肪������B���������āA���i�@��142���́A�d�����đi���邱�Ƃ��֎~���Ă���i��̓I�ɂ́A��i��s�K�@�Ƃ��Ă���j�B���K��́A���������Ɋւ��Ă̂ݒ�߂Ă���Ƃ���邪�A��q�����i�����̌��_�́A���ێ����ɂ����Ă͂܂�B�]���āA���ێ����Ɋւ��Ă��A��d�N�i���K������K�v�����w�E����Ă���B����ɑ��A��d�N�i�̋K���ɏ��ɓI�Ȍ������咣����Ă���B�ȉ��ł́A�w����ٔ���ɂ��Č�������B 2�D�K�����ɐ� (1) ���S�H���� �@�O�f�̃P�[�X�ɗގ����鎖���ɂ����āA���n�ق́A���i�@����231���i�V��142���j�̒�߂�i�����͐����Ă��Ȃ��Ɣ�������[1]�B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ����u�ٔ����v�Ƃ͍����ٔ������w���A�O���̍ٔ����͂���ɂ͊܂܂�Ȃ����߂ł���B�]���āA�O���̍ٔ����ɂ����āA����̌����E�`���W�ɂ��đ����Ă���ꍇ�ł����Ă��A��d�N�i�Ƃ��ċ֎~����Ȃ��Ƃ���B���̑��A���Q�E�x��������邽�߂̈ڑ��Ɋւ���K��i��17���j�́A�O���̍ٔ����ɌW�����������ɂ͓K�p����Ȃ����ƁA�܂��A���ՂɊO���̍ٔ����ɌW������O�i��D�悵�Ă��悢�Ƃ͌���Ȃ����Ƃ��A��d�N�i�̋K���ɔ����鍪���ɂȂ��Ă���[2]�B �@�Ȃ��A�{���ɂ����āA���n�ق́AY���i�̔������������B�����A�A�����J�̍ٔ����́AY�ɑ��Q�������̗��s�𖽂��锻�����o�������߁iY�̔s�i�����j�A���ė����ŁA����̎��Ăɂ��Ė������锻�����������Ƃ������Ԃ��������B����AX���A�����J�������̏��F�E���s�����߂đ��n�قɑi�����N�����Ƃ���A���n�ق́A��������F���Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�������́A�䂪���̍ٔ����̔����ɖ������Ă���A��������F����A�䂪���̖@�����𗐂����ƂɂȂ邽�߂ł���i��118���m����200���n��3���j[3]�B
�@�K�����ɐ��̍����Ƃ��ẮA�ȉ��̓_����������B�Ⴆ�A�i�����������Ă��邩�ǂ����̒����́A�E����������[4]�ł���Ƃ���ƁA�����̍ٔ����͉ߓx�̕��S���B�܂��A���̂��߂ɍٔ����x�������˂Ȃ�[5]�B �����Ƃ��A�K�����ɐ��ɂ��ƁA������G���锻����������邱�Ƃ�����B���̖��́A���{�̍ٔ����̔�����D�悳���邱�Ƃʼn������邱�Ƃ��\�ł��邪�A���̂悤�ȏ����̎d���́A���ێi�@�����̍l���ɔ����邵�A�܂��A�O�������̑��d�Ƃ����O�������̏��F�E���s���x�̎�|�ɔ�����B����ɁA�����i�̍ٔ����錠���j���\���ɕی삳��Ȃ��Ƃ��������Ԃ���������B
�@���̂��߁A���ۑi�ׂɂ����Ă��A��d�N�i���֎~����Ƃ����l�����L�͂ł��邪�A�K���̕��@�ɂ��āA�ȉ��̂悤�Ȍ�����������Ă���[6]�B
�@���̌����́A�O���ٔ����̑O�i�������m�肵�A���ꂪ�䂪���ɂ����ď��F����邱�Ƃ��m���ȏꍇ�ɂ̂݁A�i�䂪���̍ٔ����ɌW�������j���i��s�K�@�Ƃ��ׂ��Ƃ���[7]�B �@���̗��_�ɂ��A�K�����ɐ��̌��_���������邱�Ƃ��ł��邪�A�����Ƃ��A�ȉ��̖�肪������B
�@����䂦�A�O�i�������������܂ŁA��i�葱�����~���ׂ��Ƃ���l��������Ă���B �A�K�Ȗ@��n�� �@����́A�ǂ̍ٔ����������f����̂��K���ǂ������l�����āA�s�K�@�ƂȂ�i�������肷�ׂ��Ƃ��錩���ł���B�p�Ė@��̃t�H�[�����E�m���E�R���r�[�j�G���X�̖@���ƍl�������ʂɂ��A���Ă̓��ꐫ���l�����đi�������K������Ƃ������̗��_�ɂ��A��̓I�Ó����ɕx�މ������}���邪�A�ȉ��̖������@�����Ȃ��B
[1] ���n�����a48�N10��9���A����728��76�ŁB [2] �����n���Ԕ����������N5��30���������i�ז@����S�II�i�V�@�Ή���Łj50�ŎQ�ƁB [3] ���n�����a52�N12��22���A���^361��127�ŁB�Ȃ��A���n�ق́A�O���ٔ����̔����̊m�肪��ɉ�����Ă��悤�Ƃ��A��ɓ��{�̍ٔ����̔������D�悷��Ɣ��f�����B [4] �E�����������Ƃ́A�����҂̐\�����Ă��Ȃ��Ƃ��A�ٔ���������I�ɒ������A�K�v�ȏ��u���Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���鎖���ł���B�Ⴆ�A�i�חv���̏[���A�ٔ����̍\���Ɋւ����@���i���i�@��312���2���j�A�����٘_�̌��J�i����5���j�A���s�K��̏���A���ˌ����̗L���i��23���1���j�A�����ɓK�p���ׂ����̖@�K�̒T���Ȃǂ���������B��d�N�i�̋֎~�ɐG��邩�ǂ����́A�i�חv���̏[���Ɋւ�����ł���̂Łi�܂�A�i��Q�v�������݂��邩�ǂ����Ɋւ�����ł���j�A�E�����������Ƃ���Ă���B [5] ���̑��̗��R�ɂ��A�ΐ쁁�����u���ۖ����i�ז@�v�i�я��@�A1994�N�j75�ňȉ��B [6] �w���ɂ��A�ΐ쁁�����E�O�f��76�ňȉ��Q�ƁB [7] ���̍l�����̗p����ٔ���Ƃ��āA�����n���Ԕ����������N5��30���������i�ז@����S�II�i�V�@�Ή���Łj50�ŎQ�ƁB [8] �䂪���ł́A�ʏ�A�i�W���́A�퍐�ɑi���B���ꂽ�Ƃ��ɐ�����Ƃ���Ă��邪(��������Q���j�A�i�ٔ����ɒ�o���ꂽ�Ƃ��A�܂��A�i�חv���̏[���Ɋւ���ٔ����̐R�����I�������Ƃ��ɌW������ƒ�߂�O���@������B |