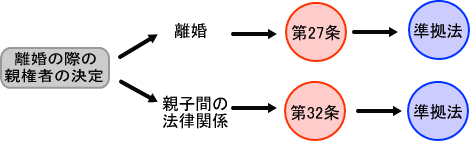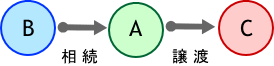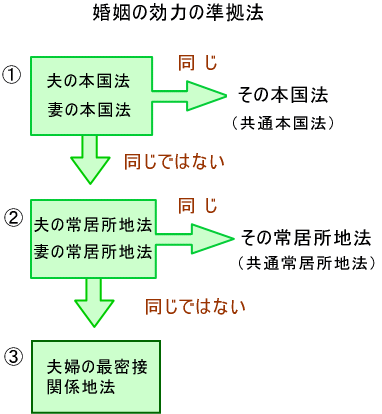すでに説明したように、適用通則法に従い準拠法を決定するには、まず、ある具体的な法律問題は、いかなる単位法律関係に該当するか検討しなければならないが(詳しくは こちら)、特別な考察を必要とする場合がある。例えば、以下のケースについて考えてみよう。
例:離婚する夫婦(両者の国籍は異なるものとする)に未成年の子がいる場合、 その親権者または監護権者を決定する必要がある。親権者または監護権者の決定に関する準拠法は、どのようにして指定されるべきであろうか。この問題については、以下の2つの見解が考えられる。
◎ その他の例:
このような法律関係の性質決定に関する問題は、1891年、カーン(Kahn)によって初めて指摘されたとされる[2]。
① 法廷地法説 これは、法律関係の性質は法廷地の実質法に従って決定すべきとする見解である[3]。 この立場は、外国法を適用し、自国法の適用を制限することは主権の制限にあたるだけではなく、外国法に基づき法律関係の性質を決定することは主権の放棄にあたるという理論に基づいているが、このような考えは適切ではない。 また、この見解によれば、内国法(自国法)が優先されることになり、これは国際私法の大原則(内外法の平等)に反する。
② 準拠法説 次に、準拠法として指定された実質法に従い性質を決定すべきであるとする見解が唱えられている(ポルトガル民法第15条参照)。 もっとも、この説による場合、準拠法をどのようにして決定するか(法律関係の性質が決定しなれば、適用通則法を適用し、準拠法を指定することはできない)という問題が生じる。
③ 国際私法自体説 さらに、法律関係の性質決定は、国際私法の適用に際し生じる問題であるから、国際私法の観点からなされるべきであるとする見解が主張されている(実質法からの解放)。 法律関係の性質決定は、抵触規定の解釈の問題であるため、国際私法それ自体に基づいて決定するという理論には説得力があり、広く支持されている(我が国の通説)。 なお、性質決定の具体的な方法に関しては、以下のように争われている。
① 前述した離婚の際の親権者または看護者の決定に関し、東京地裁[4]は、「離婚の際の親権の帰属問題は、子の福祉を基準にして判断すべき問題であるから、法例第21条の対象とされている親権の帰属・行使、親権の内容等とその判断基準を同じくすべきである」として、法例第21条(現在の適用通則法第32条)を適用し、準拠法を決定した。
② 離婚そのものに基づく慰謝料の請求について、横浜地裁[5]は、「離婚に伴う財産分与及び離婚そのものによる慰謝料請求については、いずれも離婚の際における財産的給付の一環をなすものであるから、離婚の効力に関する問題として」扱うべきと判断した。 これに対し、夫の暴力行為に対する慰謝料請求は、不法行為の問題として扱うべきである(通説)。また、夫が別の女性と不貞行為を行ったことが離婚原因となり、妻が同女性に慰謝料を請求(第三者による婚姻侵害に基づく慰謝料請求)も同様に、不法行為の問題として扱うべきである(出口『基本論点国際私法』(第2版)229~230頁参照)。 【参考文献】 中西康「法律関係の性質決定」渉外判例百選(第3版)4頁以下 [1] ここでは、離婚の問題か(適用通則法第27条)、それとも、離婚の原因が配偶者の暴力行為にあるとすれば、不法行為の問題か(第17条)が問題になる。 [2] また、この問題は、フランス人のバルタン(Bartin)によっても指摘されているが、この点につき、溜池「国際私法講義」121頁以下または櫻田「国際私法」(第2版)67頁以下参照。 [3] 京都地判昭和31年7月7日 [4] 東京地裁平成2年11月28日判決(渉外判例百選(第3版)4頁)。 [5] 横浜地裁平成3年10月31日判決(渉外判例百選(第3版)4頁)参照。 |