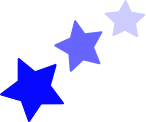
| E C 法 の 効 力 |
|
1. 総論 EC法は国際条約である第1次法と、それに基づき制定された第2次法からなるが(参照)、加盟国の立場からすれば、これらは国際法である。もっとも、その効力ないし法規範力が強いという点で、一般の国際法とは異なる (一般の国際法としてのWTO諸協定の効力については こちら)。 なお、EUの第2の柱 と 第3の柱において採択された法令(EU法)は、第1の柱(EC)の法令のような特殊性を備えていないため、一般国際法として捉えることができる(参照)。 |
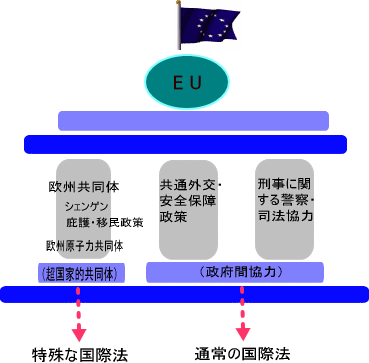
他方、国際機関であるECの内部において、EC法は、いわば国内法としての性質を有する。 これに対し、国際慣習法やECによって締結された国際条約は、いわば、ECの国際法に当たる( |
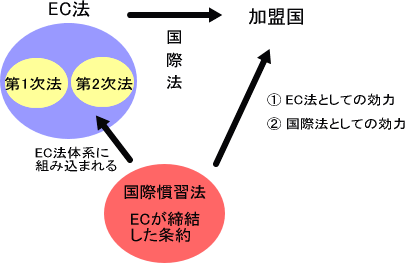
|
なお、ECによって締結された国際条約は、第2次法にあたる。これは、EC条約に基づき、EC諸機関によって締結されるためである(ECによる国際条約の締結については こちら)。 2. 各論 加盟国におけるEC法の適用・効力について、以下の問題が生じる。
|
「EU法講義ノート」のトップページに戻る