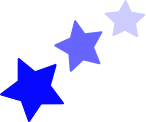|
EUは「3本柱構造」からなるが( 参照)、それらに関する法をまとめてEU法と呼ぶ。 参照)、それらに関する法をまとめてEU法と呼ぶ。
これに対し、EC法とは、「第1の柱」に関する法を指す。対象が「第1の柱」の法に限定されるため、狭義のEU法と呼ぶこともある。ECはEUの基礎であり(EU条約第1条第3項)、第2、第3の柱に比べ、法令も発展している。そのため、EU法の授業では、主として、「第1の柱」の法について説明することになる。
「第1の柱」の法
すなわち、EC法 |
 |
狭義のEU法 |
|
|
 EU法とEC法(狭義のEU法)違い EU法とEC法(狭義のEU法)違い
EU法とEC法(狭義のEU法)は、その対象だけではなく、効力に関しても違いがある。すなわち、後者は、超国家組織の法として、通常の国際法(EU法)よりも強力な効力が与えられており、また、加盟国法と矛盾抵触する場合は、それに優先して適用される(→
参照)。これに対し、EU法は 直接適用性 や 直接的効力 を有さず、また、国内法に対し、常に優先的に適用されるとは限らない(→ 例外)。
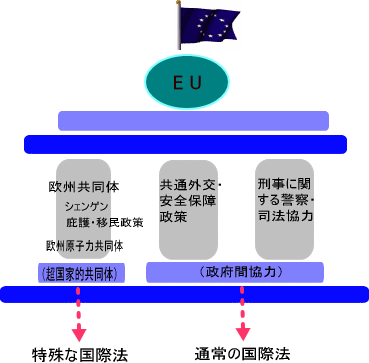
3つの柱の法令や政策は、互いに矛盾が生じないよう、調整されなければならないが、EU条約第47条は、原則として、EU条約は、EC条約の内容を改変しえないと定める(例外として、EU条約第8条から第10条参照)。そのため、EUは、EC法の実効性(前述した強力な効力)を否認することはできない。
(参照) EC裁判所の Pupino 判決
 広義のEU法とは 広義のEU法とは
EU(厳密には、EC)は、第3国や他の国際機関と密接な関係を築いている。そのような過程で形成された法令を広義のEU法と呼ぶことがある。その例としては、欧州評議機会加盟国によって制定された欧州人権条約(1950年制定)やその附属議定書( 参照)、また、欧州経済領域協定(EEA協定、1992年制定)などが挙げられる。 参照)、また、欧州経済領域協定(EEA協定、1992年制定)などが挙げられる。
|