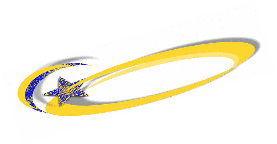
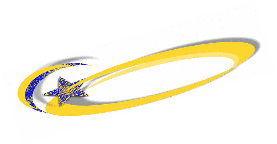 |
|
�@EU�́A���������^����ꂽ�����݂̂��A��{�����߂�����ɏ]���s�g������i�ʓI�����̌����AEU����5���1����1������ё�2���j�B�Ⴆ�A�d�ł̕���ł́A�Ԑ��łɊւ��錠���͗^�����Ă��邪�A�����łɊւ��錠���͗^�����Ă��Ȃ��iEU�̋@�\�Ɋւ������113������ё�114���2���Q�Ɓj�B���������āAEU�́A�ԐڐłɊւ���@���݂̂𐧒肵����B�������A�������̊Ԑڐł��������錠���͗^�����Ă��炸�AEU�́A���������������ɉ߂��Ȃ��B
�@�@�@�@�@ �@
�@�⊮���̌����̎�|�́AEU�̌�������剻���邱�Ƃ�h�����Ƃɂ���AEU�iEC�j�ɂ܂��܂������̌������Ϗ�����邱�ƂɂȂ��� �}�[�X�g���q�g��� �̐���ɍۂ��������ꂽ�B�������{�ɂ�鐭���}�����A�n���̎��含��ٗʌ��d���錴���̐��_�͘A�M���Ƃ̊�{�����̈�ɂ����邪�A�A�M���Ƒ̐����Ƃ�h�C�c�̃C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â��A�܂��A�C�M���X�̋����x�����AEU�@�̌n�iEC�@�̌n�j�ɂ��������ꂽ�B �@�ڂ����͌�q����悤�ɁA�⊮���̌����iEC����5���2���k����3b���2���l�j�́A�A���X�e���_����� ��A�������� ���B���@����A�܂��A2009�N12���ɔ������� ���X�{����� �ɂ���ĕ�[����Ă���B
�@�⊮���̌����̓K�p�ɍۂ��ẮA�ȉ��̓_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| (1) | EC�Ɍ��������S�ɈϏ�����Ă��Ȃ��Č��ł��邩�i�Q���j �@�⊮���̌����́AEU�Ɍ��������S�ɈϏ�����Ă��Ȃ������i�Q���j����K�p�����B�܂�A��������EU�Ɍ��������S�ɈϏ��������ʁA�������͓Ǝ��̐�������{�����Ȃ��Č��Ɋւ��ẮA�⊮���̌����͓K�p����Ȃ��B�Ȃ��A����������EU�ւ̌����Ϗ���EU�̌����͑�1���@���Œ�߂��Ă���i�Q���j�A�⊮���̌����Ɋ�Â��AEU�ɐV���Ȍ������Ϗ����ꂽ��A�܂��́AEC�������������킯�ł͂Ȃ��B�܂�A�⊮���̌����́A�����z���Ɋւ��錴���ł͂Ȃ��AEC�̌����s�g�ɂ��Ē�߂錴���ł���B �@�A���X�e���_�����i�����ɂ́A�����ɓY�t����Ă����c�菑 �� EC�����30�c�菑�j�́A�⊮���̌����̃_�C�i�~�b�N�Ȑ����ɂ��ĐG��Ă���B�܂�AEC�̊����͈͂́A�K�v���ɉ����Ċg�債����A���������iZiffer 3�j�B�������A�ς�肤��̂�EC�̊����͈͂ł���A�����ł͂Ȃ��B �܂�A�\�ߖ��m�ɋK�肳�ꂽ�����͈͓̔��ŁAEC�̊�������́A�K�v�ɉ����A�ω�������B
|
||||||
| (2) | �����������{����̂ł́AEU�̐����ړI���\���ɒB������Ȃ����� |
||||||
| (3) |
�[�u�̋K�͂܂��͌��ʂ̖ʂŁAEU�����{����������ǂ����ʂ�������ƍl�����邱��
|
||||||
| (4) |
EU�̑[�u�͕K�v�Ȕ͈͓��Ɍ��肳��Ă��邩�i��ᐫ�̌����j |
|
|
| EC�ٔ����̔���@�ƕ⊮���̌��� |
|
�@�����A�⊮���̌����iEC����5���2���j���ٔ����ɂ��@�ߐR���̊�ɂȂ邩�ǂ��������Ă����BECJ���A�⊮���̌����ɏƂ炵����2���@�̐R���ɏ��ɓI�ł��������A�ߎ��͏ڍׂɌ������Ă���iCase
C-491/01, British American Tabacco [2002] ECJ I-11453�j�B�܂��A�i�@�R���������I�ɂ��邽�߁A���@�҂́A��2���@�̑O���ɂ����āA�⊮���̌����̓K�p�Ɋւ��錩���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���iCase
C-233/94, Einlagesicherung [1997] I-2405; Case C-377/98, Biopatent-RL
[2001] ECJ I-7079�j�B
|
| �����c��ɂ�铝�� |
|
|
|
�i�Q�Ɓj |
�E |
�⊮������є�ᐫ�̌����̓K�p�Ɋւ���c�菑�i�A���X�e���_������c�菑 �� EC�����30�c�菑�j |
| �E | EU�ɂ����鍑���ٔ����̖����Ɋւ���c�菑�i�A���X�e���_������c�菑 �� EU�����9�c�菑�j |
|
| �E | �]���̕⊮���̌��� |
|
| �E | Subsidiarity Monitoring Network of the Committee of the Regions |
|
|
�uEU�@�u�`�m�[�g�v�̃g�b�v�y�[�W�ɖ߂�