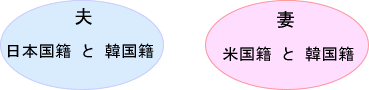| 重 国 籍 者 の 本 国 法 |
|
ある者が複数の国籍を有する場合、 どの国の法令を本国法とすべきか。適用通則法第38条第1項本文によれば、①まず、複数の国籍国に当事者が常居所を有するときは、その国の法が本国法とされ、②複数の国籍国の中に常居所がない場合には、その者に最も密接に関係する国の法令(最密接関係地法)が本国法となる。
ただし、当事者の国籍国の中に日本が含まれる場合には、日本法が本国法となる(第38条第1項但書、 内国法優先主義)[1]。このような取り扱いは、内外法の平等の原則に反するが、これは、重国籍者の国籍の一つに日本国籍が含まれる場合に、日本法が優先させるに過ぎず、あらゆるケースで日本法の優先を認めているわけではない。 なお、重国籍者の本国法は、例えば、婚姻の成立要件や効力、親子間の法律関係、相続 など、本国法が準拠法に指定されている場合に決定する必要性が生じる。これに対し、不法行為に基づく債権の成立・効力 のように本国法が問われないときは、決定する必要はない。
適用通則法第4条第1項のように、当事者の本国法が準拠法となるが、同人が無国籍者であり、本国法が決定しえない場合には、本国法の代わりに常居所地法を準拠法とする(適用通則法第38条第2項本文)[3]。もっとも、常居所地法が同人の本国法になるわけではない。それゆえ、第25条(第26条第1項と第27条の場合も含む)や 第32条 が定める 段階的連結 において、無国籍者の常居所地法と、相手方の本国法が同一であっても、その本国法が準拠法になるわけではなく、国籍に次ぐ連結点をもとに準拠法を決定する。第38条第2項但書はその旨を明定している。
難民は無国籍者ではないが、国籍国(本国)との関係が事実上絶たれているか、または難民がそれを望んでいるため[4]、国籍によって属人法を決定するのは妥当でない。このような理由に基づき、難民条約第12条第1項は、難民の属人法を住所地法とする。 難民条約は、「住所」の概念について定めていないため、これは締約国の判断に委ねられる。我が国では、これを「常居所」として捉える立場が有力である。
難民に関し、住所地法は、本国法に代わるものである。従って、適用法通則法が「本国法」によると定める場合(例えば第4条)、「住所地法」が準拠法となる。
[1] このような内国法優先主義の根拠として、櫻田「国際私法」(第3版)80~81頁を参照されたい(「このような内国国籍優先主義は諸国の立法において採用され、国籍法が公法であり絶対に内国で遵守されるべきこと、国籍の存否が明らかで確定に便宜であること、自国法の適用を導き出せることなどを根拠としている。しかしこのような根拠は私法の基礎としては適当ではなく、属人法の基礎として常に内国がその者と密接に関連しているとはいえないこと(例えば移民やその子孫でなお日本国籍を留保している場合や外国で生まれ育っている日本国民の子にはついてはその日本国籍は形骸化している)、内外法平等を基礎とする国際私法の建前と合致せず、各国がこの主義によるときには国際私法の統一が無に帰すことから、立法論としては当事者に最も密接な関係を有する国籍によるべきである。しかし、法例改正に際しても戸籍実務上の必要性からこの立場が維持された」)。 引用文が指摘するように、内国法優先主義は、①内外法平等の原則に反すること、②当事者と日本との結びつきが強いとは限らないこと、また③国際的裁判調和の観点から批判されている。この点について、国友明彦・渉外判例百選第3版18頁参照。 [2] この場合、韓国法が共通の本国法となるが、適用通則法第38条1項但書によると、日本国籍が優先されるので、共通の本国法がないものとして処理される。 [3] 旧法例は住所地法を本国法としていたが、改正法例は、他の規定と同様に、常居所を連結点にしている。 [4] 難民の定義については、「難民の地位に関する条約」を参照されたい。 また、国連難民高等弁務官事務所のサイトを参照されたい。 |