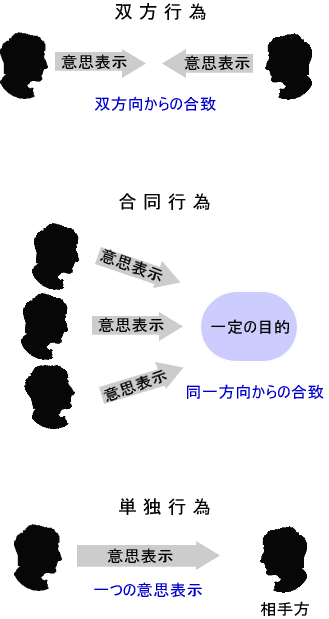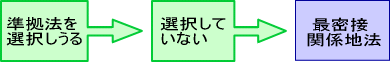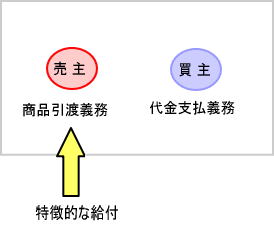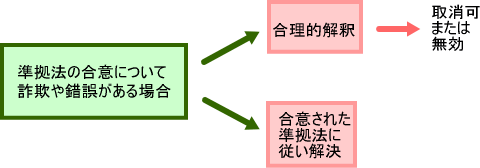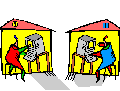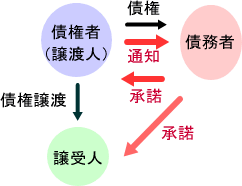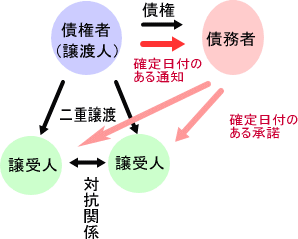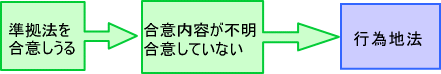|
2.1. �@���s�ׂƂ�
�@�@���s���Ƃ́A�s�҂̈ӎv�\����v�f�Ƃ��A�ʏ�A�����W�̕ϓ���������s�ׂ��w���B���̍ł���ʓI�ȗ���_���ł���B�_��́A�Ⴆ�Δ����_��ɂ����锄��Ɣ���̍��ӂ̂悤�ɁA�Η����铖���҂̈ӎv�\���̍��v�ɂ���Đ������邪�i�o���s�ׁj�A���Ε�������̈ӎv�\���̍��v�ł͂Ȃ��A������������̈ӎv�\���̍��v�ɂ���Đ�������@���s�ׂ������s���Ƃ����i�Ⴆ�Βc�̂̐ݗ��₻�̌��c�Ȃǁj�B����ɑ��A���҂̈ӎv�\���Ƃ̍��v��K�v�Ƃ����A��̈ӎv�\���݂̂ɂ���Đ�������@���s�ׂ�P�ƍs�ׂƂ����i�Ⴆ�A�_��̎���A�����A�ǔF�A���E�A�⌾�j�B
�@
2.2. �����@�̌���@�| �� �@�K�p�ʑ��@��7���`��9���́A�@���s�ׂ������������ɂ��āA�܂��A��10���́A�@���s�ׂ������ɂ��Ē�߂�B����ɁA�@���s�ׂ̓���Ƃ��āA����Ҍ_��i��11���j����јJ���_��i��12���j�ɂ��ĕʌA�K�肪�݂����Ă���B
�@�Ȃ��A�@���s�ׂ̐����ƌ��͂��� �@���s�ׂ̎��� �ƌĂсA�@���s�ׂ̕����Ƌ�ʂ��邱�Ƃ������B �@ �@�����i�����s���j��A�g���@����@���s�ׁi���� �� �{�q���g�Ȃǁj�Ɋւ��ẮA���ʂ̋K�肪�݂����Ă���̂Łi�K�p�ʑ��@��13���A��24���ȉ��Q�Ɓj�A��7���`��12���̑ΏۂƂȂ�̂́A���I�@���s�ׁi���s���A��Ƃ����_���j�ł���B
(1) �����҂ɂ��I�� �@�@�K�p�ʑ��@��7���́A �@���s�ׁi�Ⴆ�A�_��j�̐����ƌ��͂ɂ��ē����҂͏����@���w�肵����ƒ�߂�[1]�B����͎��@�̑匴���ł��铖���Ҏ����i���I�����j�������@�̑I���Ɋւ��F�߂���̂ł��邪�A�����҂ɂ�鏀���@�̌���́A�����܂ł���7���������ɂ���B�܂�A�����҂͍��ێ��@�̓K�p��r�����A���珀���@�����肷�邱�Ƃ͋�����Ȃ��i���ێ��@�̋��s�@�K���j�B
�@�Ȃ��A��8���2������ё�3���i�܂���12���2��
����ё�3���j�́A�Ŗ��ڊW�n�@�𐄒肵�Ă���ɉ߂����A��������Ƃ��\�ł���B�܂�A���̑��̒n�̖@�߂��Ŗ��ڊW�n�@�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B����͓����҂��咣�E�ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����_�ɂ��ēK�p�ʑ��@�͒�߂Ă��炸�A����̉^�p�Ɉς˂��Ă���i�Q���j�B
�A�@�@���s�ׂ̐����ƌ��͂���̏����@�ɂ�炵�߂�̂́A���҂͈��ʊW�ɂ���A���ڂɊ֘A���Ă��邽�߂ł���B�Ȃ��A�ߎ��́A�����ƌ��͂̏����@���Ďw�肷�邱�Ƃ�F�߂鍑������B���̂悤�ȕ����w�肪�\�ȏꍇ�ɂ́A�����F�߂錩�����䂪���ł��L�͂ł���[3]�B
�B�@����_��̎����������Ȃǂ̒P�ƍs�ׂɂ��ẮA�������������s���҂�����I�ɏ����@���w�肵����Ƃ���̂͌������Ɍ����邽�߁A������Ƌ��ɑI�����ׂ��Ɖ������B�Ȃ��A�����@���w�肳��Ă��Ȃ��Ƃ��́A���̌_��i�������ꂽ��A���������@���s�ׁj�̏����@�ɂ��Ƃ����َ��̍��ӂ��������Ɖ��߂�����B �C �����@�̑I���́A�Ⴆ�A�u�{�_��̏����@�̓C�M���X�@�Ƃ���v�Ƃ��A�u�{�_��̕����͓��{�@�ɏ]���ĉ��߂����v�Ƃ����悤�Ȗ����̒�߂��_���ɐ݂����Ă���ꍇ�Ɍ��炸�A�َ��I�ł����Ă��悢[4]�B �D�@�����@�́u�@���s�ׂ̓����v�ɂ����đI�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i��7���j�B�܂�A�_��̒����ߒ��ɂ����Ď�茈�߂�K�v�����邪�A������ł���A�������I������ꍇ�́u�@���s�ׂ̓����v�ɂ�����Ɖ������B����ɑ��A�������瑊���̊��Ԃ��o�߂��Ă���Ƃ��́A���͂�u�@���s�ׂ̓����v�ɂ͓�����Ȃ����A��9���́A����I�ȏ����@�̕ύX��F�߂Ă��邽�߁A���̂悤�ȏꍇ�ł���A�����҂ɂ�鏀���@�̑I���͗L���ł���B �E �����@�w��̍��ӂ��L�����ǂ������ɂȂ邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A����̓����҂̍��\�����Ɋ�Â��A�����@���I�����ꂽ�ꍇ�ł������A����͍��ێ��@�̍����I���߁i�Ȃ������ێ��@�ɂ���������@�I�����j�ɂ���Ĕ��f���ׂ��Ƃ���̂��]���̑������ł���[5]�B �@����ɑ��A�����҂��w�肵�������@�ɏ]���Ĕ��f��������Ȗ��ł���A�����҂̈ӎv�ɂ����v����Ƃ��錩�����L�͂Ɏ咣����Ă���i1955�N�̃n�[�O�u�L�̓��Y�̍��ۓI������L���锄���̏����@�Ɋւ�����v��2���2���Q�Ɓj�B�K�p�ʑ��@�̐���ߒ��ł��A���̂悤�Ȏ戵���̐��������ꂽ���A�x�������ɂ͎���Ȃ������B
�@ (2) �����@�̎���ύX�i��9���j �@�O�q�����悤�ɁA�����҂͖@���s�ׂ̓����ɏ����@��I�������邪�i��7���j�A����I�ȕύX���F�߂���i��9���j�B�܂�A�K�p�ʑ��@�́A�����@�̑I��ύX�ɂ��āA�����҂̈ӎv�i�����Ҏ����j�d���Ă���B�������A����I�ȕύX�ɂ���đ�3�҂̌������Q�����Ƃ��́A���̑�3�҂Ƃ̊Ԃɂ����āA�ύX�͔F�߂��Ȃ��i��9��A���j�B �@�@�@ �@�����@���ύX�����ꍇ�A�V���������@�͑k�y�I�ɓK�p����邩�A�܂��́A�ύX��̎����ɂ��Ă̂ݓK�p����邩�Ƃ����_�ɂ��ēK�p�ʑ��@�͖����̋K���u���Ă��Ȃ����A�����Ҏ����d����K�p�ʑ��@�̐��_�Ɋӂ݁A�����҂����肵����Ɖ������B
�@ �@
2.4. �@���s�ׂ̕����i�K�p�ʑ��@��10���j (1) �K�p�͈� �@�@���s�ׂ̕����Ƃ́A�@���s�ׂ��L���ɐ������邽�߂ɕK�v�Ȉӎv�\���̊O���I�\�����@���w���B�Ⴆ�A�y�n�̔����Ƃ����@���s�ׂ��L���ɐ������邽�߂ɂ́A���ʂłȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���I�@�ւ̏ؖ����K�v���ǂ����A�܂��͓͏o���K�v���ǂ������ɂȂ�B �Ȃ��A�@�����̕����ɂ��ẮA��24���2������ё�3�� ���A�A�⌾�̕����ɂ��ẮA�u�⌾�̕����̏����@�Ɋւ���@���v���A�܂��A�B��`�E���؎�s�ׂɊւ��ẮA��`�@��89���1���A���؎�@��78���1�����K�p����邽�߁A�K�p�ʑ��@��10���͓K�p����Ȃ��B �@���@�e���W�@���s�ׂ̕����ɂ��ẮA��34�����Q�Ƃ��ꂽ���B (2) �����@ �| �����̏����@ �@ �������@���s�ׂ̐����v���̈�ł���i�܂�A�������K�@�łȂ���A�@���s�ׂ͐������Ȃ��j�A�����Ɋ֘A���鎖���ł��邱�Ƃ���A�K�p�ʑ���10���1���́A�����͐����̏����@�ɂ��Ƃ���i����ɑ��A�@���8���1���͌��͂̏����@�ɂ��Ƃ��Ă����j�B�܂�A���s�� [7] �ł���Α�7���ȉ��ɏ]���A�܂��A�����s�� [8] �ł���A��13���ɏ]���A�����̏����@�����肳���B
�@�Ȃ��A�O�q�����悤�ɁA��7���́A�����ƌ��͂���ʂ����A�܂Ƃ߂ċK�肵�Ă���i�ڂ����� �������j�B���̂��߁A�����������̏����@�ɂ��ƒ�߂Ă��i�K�p�ʑ��@��10���1���j�j�A�܂��́A�����̏����@�ɂ��ƒ�߂Ă��i�@���8���1���j�A�����I�ȈႢ�͐����Ȃ����A�����҂͐����̏����@��č��@�A�܂��A���͂̏����@����{�@�ƕ������Ďw�肷�邱�Ƃ��ł���i�����w��j�B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�����͐����̏����@�ɂ��̂��A����Ƃ��A���͂̏����@�ɂ��̂��ō��ق�������B �A �O�q�����悤�ɁA�����҂͐����̏����@��ύX������i�Q���j�B�@���s�ׂ̐������Ɏw�肳�ꂽ�����@�ɂ��Ε����͗L���Ƃ������̂́A�V���������@�ɂ��Ζ����Ƃ����̂ł���A�@���s�ׂ̈��萫���Q����B���̂悤�Ȃ��Ƃ�����邽�߁A��10���1���́A���ʓ��ɂ����āA��ɐ����̏����@���ύX�����悤�ȏꍇ�ł���A�u�ύX�O�̖@�v�ɂ��ƒ�߂�B�Ȃ��A�����@���AA���@ �� B���@ �� C���@�Ɛ���ύX�����ꍇ������B�ύX��̏����@�ɂ���ĕ����������Ƃ����s�s����������邽�߁A��10���1���́u�ύX�O�̖@�v�Ƃ́AB���@���w���̂ł͂Ȃ��AA���@�i�@���s�א������ɂ����鏀���@�j���w���Ɖ����ׂ��ł���B (3) �s�גn�@ �@ �����́A�����̏����@�����ł͂Ȃ��A�s�גn�@�ɂ�邱�Ƃ��ł���B�܂�A�@���s�ׂ̍s�גn�@�ɓK����������͗L���ƂȂ�i��10���2���j�B����́A�@���s�ׂ�e�Ղɂ���Ƃ������z���Ɋ�Â��Ă��邪�A�Â�����A�u�s�ׂ̕����͍s�גn�@�ɂ��v�Ƃ����������x������Ă����B �@�Ȃ��A�����s�� [8] �ɂ��ẮA�����ς�A�����̏����@�i�܂�A�ړI���̏��ݒn�@�j�ɂ��A�s�גn�@�������@�Ƃ��邱�Ƃ͔F�߂��Ȃ��i��10���5���j�B����́A�ړI���̏��ݒn�@�ɂ��Ȃ���A�����s�ׂ̕����i�Ⴆ�A�o�L���K�v���ǂ����j�Ɋւ��闘�v���ی삳��Ȃ����ƂɊ�Â��Ă���B �A �قȂ鍑�ɑ؍݂���҂̊ԂŁA�ʐM�ɂ���Č_��i���u�n�I�@���s�ׁj�����������悤�ȃP�[�X�ł́A�s�גn�͂ǂ̂悤�ɂ��Č��肷��悢�ł��낤���B
�@ �@���̓_�ɂ��āA��10���4���́A�\���݂̒ʒm�����n�̖@���A�����̒ʒm�����n�̖@�̂����ꂩ�̕��������Ă���悢�ƒ�߂�B�Ȃ��A��10���1���ɏ]���A�����҂��w�肵���@�ɂ�邱�Ƃ��ł���B �@�\���݂̔��M�����ҁi���Ȃ킿�����ҁj���A�\���݂̔��M�n��m�肦�Ȃ��Ƃ��ɂ��āA�K�p�ʑ��@�͓��ɒ�߂Ă��Ȃ����A�@���9���2���́A�\���҂̏Z���n���s�גn�Ƃ݂Ȃ��ƋK�肵�Ă����B���҂́A�\���҂͂��̏Z���n���甭�M���Ă���Ɛ��肷�邱�Ƃ������I�ł���Ɖ�����邽�߂ł���B �@�Ȃ��A�\���ɕύX�������������́A�u�V���Ȑ\���v�Ɖ�����ٔ��Ⴊ����[6]�B �@�B ��10���4���́u�_��v�ɂ��Ē�߂Ă��邽�߁A��3�����P�ƍs���i����I�ӎv�\���m�Ⴆ�A�_��̎��������Ȃǁn�j�Ɋւ��Ē�߂Ă���Ɖ�����邪�A����ɂ��A�ʒm�����n���s�גn�Ƃ݂Ȃ����B
(4) �@���s�ׂ́u�����v�ƑR�v�� �@����@���s�ׂ̑R�v���Ƃ��āA����̕������v�������ꍇ������B�Ⴆ�A �䂪���̖��@��467���ɂ��A�����n�̑R�v���Ƃ��āA�@���҂ɑ��Ă͏��n�l�i���ҁj����̒ʒm�܂��͍��҂̏������A�܂��A�A���҈ȊO�̑�O�҂ɑ��ẮA�m����t�̂���؏��i�Ⴆ�A���e�ؖ��X�ցj�ɂ��ʒm�⏳�����K�v�ɂȂ�B
�@���̊m����t�̂���؏��ɂ��ʒm�́A�@���s�ׂ������Ƒ����邱�Ƃ��ł��邪�A�K�p�ʑ��@�́A�����n�̑�O�҂ɑ���R�͂ɂ��ē��ʂ̋K��������Ă��邽�߁i��23���j�A����͑�10���̒�߂�u�����v�ɂ͂�����Ȃ��B �@�����ݒ�i�Ⴆ�A����a������ΏۂƂ��鎿���̐ݒ�j�̑�O���҂���т��̑��̑�O�҂ɑ���R�v���Ƃ��āA�m����t�̂���؏��ɂ��ʒm�܂��͏��F���K�v�Ƃ����ꍇ���i���@��364���Q�Ɓj�A�����̖��Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���̖͂��Ƃ��Ĉ����B �@���l�ɁA�����s�ׂ̑R�v���Ƃ��ėv�������o�L����n���A�����̖��ł͂Ȃ��A���́i�����̎����j�̖��Ƃ��Ĉ����B�]���āA�K�p�ʑ��@��13���Ɋ�Â��A�����@�����肷��B
�@
�@ [1] �O��������A�N�Z�X�ł���C���^�[�l�b�g�͍��ې��������B ���̂��߁A����̏ꍇ�ɔ����A���p�K��̒��ŏ����@���w�肳��Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��i���j�B�Ȃ��A �@���s�ׁi�Ⴆ�Δ����j�Ǝw�肳�ꂽ�����@�Ƃ̊ԂɊ֘A�����Ȃ��Ă��悢�B [2] �Ȃ��A�@���7���2���́A�����҂̈ӎv���s���ȏꍇ�͍s�גn�@�ɂ��ƒ�߂Ă����B����́A�����҂́A��ʂɍs�גn�@�������@�ɂ��Ă���ƍl�����邱�Ƃ�A�s�גn�@��m�邱�Ƃ͗������҂ɂƂ��ėe�Ղł��邱�ƂɊ�Â��Ă��邪�A���I�ȋK��̎d���ɂ͔ᔻ�����������i�s�גn�@�����Y�@���W�ɍł����ڂɊW����n�̖@�ł���Ƃ͌���Ȃ������ł͂Ȃ��A�s�גn�@�̓��肪�e�Ղł͂Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ��w�E����Ă����j�B���̂��߁A�O�q�����悤�ɁA�V�@�͍Ŗ��ڊW�n�@�������@�Ɏw�肵�Ă���B �@�@�@�@ [3] �����n�����a52�N5��30���A�O����S�I�i��3�Łj72�ŎQ�ƁB [4] �O�q�����悤�Ɂi��2�Q�Ɓj�A�@���7���2���́A�����҂̈ӎv���s���ȏꍇ�͍s�גn�@�ɂ��ƒ�߂Ă������A���ۂɁA�����@�����m�ɒ�߂��Ă��Ȃ��ꍇ�A�����ɓ����҂̈ӎv���s���ł���Ƃ��āA�s�גn�@��K�p����ׂ��ł͂Ȃ��A�_��W�̏��ʂ̎���i�_��̌^�E�����A�_��̖ړI���A�ٔ��NJ��A�_�Ŏg�p����Ă��錾��ⓖ���҂̍��ЁE�Z���Ȃǁj���瓖���҂̈ӎv�𐄒肵�āA�����@��T�����ׂ��ł���Ƃ���Ă����i�]���̒ʐ��j�B����́A�����@�����I�ɍs�גn�@�ɂ���ƁA�X�̎���̓����ɑ����Ȃ��Ƃ��������Q�������邤�邩��ł���B�����n�����a52�N4��22���A�O����S�I�i��3�Łj74�ŎQ�ƁB�����Ƃ��A�����@�̎w�肪���m�łȂ��ꍇ�ɁA�����ɍs�גn�@��K�p�����ٔ��Ⴊ�����B�D�y�n�����a49�N3��29���A�O����S�I�i��3�Łj76�ŎQ�ƁB [5] �Ⴆ�A�����@�̑I���Ɋւ��A�d��ȍ����A������̍��\�E����������ꍇ�́A�����҂ɂ���đI�����ꂽ�����@�ɏƂ炵�A���̗L�����ɂ��Ĕ��f����̂ł͂Ȃ��A���ێ��@��A���̂悤�ȏ����@�̑I���́i���R�Ɂj�����܂��͎���������ƍl����B [6] ���n���吳10�N3��11���B [7] �����ҊԂɍ��E���W��������s�ׁi�Ⴆ�A�����_��Ȃǁj�B [8] �������̂̐ݒ�E�ړ]�ڂ̖ړI�Ƃ���@���s�ׁB�Ⴆ�A�y�n�̔����_��Ɋ�Â��A�y�n�̏��L�����ړ]������A�܂��x�������m�ۂ��邽�߁A����̍����ɒ����ݒ肷��s�ׂȂǂł���B �@
|