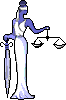|
1. はじめに
買主が代金を支払わないとき、売主は自らの権利(代金請求権)を実現するため、裁判所に訴えを提起することができる。それによって、売主は、① 代金の支払いだけではなく、②
利息の支払いを請求することもできるし、代金については、全額ではなく、一部を請求することもできる。また、このような 給付の訴え を提起する代わりに、将来の紛争予防に備え、買主の支払義務の確認を裁判所に求めることもできる(確認の訴え)。このように、訴訟の開始や審判対象の特定について、当事者には主導権が与えられているが(処分権主義、第246条)、このことは訴訟の終了に関しても当てはまる。つまり、一端、訴訟手続が開始されたとしても、当事者は以下のような方法で訴訟を終了させることができる。
① 訴えの取下げ: 原告が訴訟物に関する審判請求を撤回すること
② 請求の放棄 : 原告が自らの請求に理由がないと認めること
③ 請求の認諾 : 被告が原告の請求に理由があると認めること
④ 訴訟上の和解 : 両当事者が互いに譲り合い、紛争を解決すること
これらの方法により訴訟が終了する割合は高く、第1審裁判所が判決を下す事件は半数にも満たない。
2. 訴えの取下げ
2.1. 定義と手続
訴えの取下げとは、原告が自ら提起した訴えの全部または一部を撤回する訴訟行為である。提訴後、当事者間に和解が成立したためになされることが多い。訴えの取下げは、控訴審や上告審でも認められる(第292条、第313条参照)。
裁判所が訴訟上の請求について判決(本案判決)を下した後であれ、それが確定する前であれば、訴えを取り下げることができる(第261条第1項)。例えば、判決に不服がある原告や、判決言渡し後に和解が成立するとき、原告は訴えを取り下げてもよい。
ただし、相手方がすでに本案(原告の請求の理由の当否に関する弁論・裁判)について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述し、または、口頭弁論をしているときは、相手方の同意を必要とする(第261条第2項)。これは、積極的に争う姿勢を見せた相手方も勝訴判決を受ける正当な利益があるため、その同意なしに、一方的に訴えを取り下げうるとすれば、公平に反すると解されるためである。
慎重を期すため、訴えの取下げは書面で行わなければならないが、口頭弁論等の期日においては口頭でもなしうる(第261条第3項)。
第1審の口頭弁論期日等に当事者双方が欠席し、その後1ヶ月以内に期日の指定を申立てなかったときは、訴えの取下げが擬制される。双方が2回連続して欠席した場合も同様に取り扱われる(第263条、詳しくは
こちら)。
2.2. 効果
(1) 訴訟係属の遡及的消滅
訴えが取り下げられると、訴訟は初めから係属していなかったものとみなされる(第262条第1項)。そのため、訴えの提起による時効中断の効果は、取下げによって消滅する(民法第149条)。
なお、上訴が取り下げられると、上訴審における訴訟手続が終了し、上訴期間の経過時に遡って原判決が確定する(詳しくは こちら)。
(2) 再訴の禁止
前述したとおり、訴えは終局判決が下された後でも、確定するまでは取り下げることができるが、終局判決が下された後に訴えを取り下げるときは、再び同一の訴えを提起することは許されない(再訴の禁止、第262条第2項)。これは、判決に不服のある原告が訴訟係属を消滅させ、新たに同一の訴えを提起することを防ぐためである。また、本案判決を受けたにもかかわらず、自ら訴えを取下げることによって裁判による紛争解決の機会を排除した原告に対する制裁の意義も併せ持つ(最判昭和52年7月19日、民集31-4-693)。
 重複起訴の禁止との関係 重複起訴の禁止との関係
|
|
終局判決が確定する前に訴えを取り下げ、後日、改めて訴えを提起しても、重複起訴として禁止されない。なぜなら、訴えを取り下げると、初めから係属していなかったものとして扱われるためである。このような不都合を解消するため、第262条第2項は再訴を禁止している。つまり、終結判決が確定する前に訴えを取り下げ、後日、同一の訴えを提起することは禁止される。
|
 訴えの同一性の判断 訴えの同一性の判断
|
※
|
第1審の終局判決(本案判決)が控訴審によって取り消され、第1審に差し戻された後、第1審が終局判決を下す前に訴えが取り下げられるときは、再訴禁止効は生じない。
|
3. 請求の放棄・認諾
請求の放棄とは、原告が自らの請求(訴訟物)に理由がないと認める陳述を行うことを指す。他方、請求の認諾とは、被告が原告の請求(訴訟物)に理由があると認める陳述を行うことを指す。請求の放棄・認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要があるが(第266条第1項)、上掲の期日に欠席しても、放棄・認諾を行う旨の書面が提出されているならば、陳述がなされたとみなすことができる(第2項)。
請求の放棄・認諾が口頭弁論調書に記載されると、調書の記載は確定判決と同一の効力を持つ(第267条)。つまり、終局判決によって訴訟が終了する場合と同じ効果が発生し、既判力も生じる(請求の放棄について、既判力を否認する学説もある)。
なお、当事者の自由な処分が認められない事項(例えば、身分に関する問題や公益性の強い案件)については、請求の放棄・認諾も認められない(人事訴訟法第19条第2項参照)。ただし、婚姻事件については、認諾はできないが、放棄は許されると解されている。
請求の放棄・認諾は、本案判決の言渡し後であれ、確定するまでは認められる。錯誤や詐欺等があった場合について、判例は、無効・取消しを認めている(後述の裁判上の和解を参照)。
4. 訴訟上の和解
4.1. 定義
和解とは両当事者が互いに譲り合い、紛争を解決する契約を指すが(民法第695条)、これが訴訟係属中、口頭弁論等の期日においてなされれば、訴訟上の和解と呼ぶ。
|
※
|
両当事者が互いに譲り合わず、例えば、被告が原告の見解を全面的に受け入れる場合は 請求の認諾 であり、訴訟上の和解ではない。
|
訴訟係属中であれ、期日外でなされれば、裁判外の和解であり、後述する訴訟法上の効力は与えられない(実体法上の和解の効力を有するのみである)。
|
※
|
簡易裁判所における 訴え提起前の和解 について、第275条を参照されたい。なお、この訴え提起前の和解と、訴訟上の和解を併せて、裁判上の和解とよぶ。
|
なお、訴訟上の和解の性質には争いがあるが、通説・判例は、①私法上の和解契約としての性質と、②訴訟行為としての性質の両方を併せ持つと捉えている(両性説、最判昭和31・3・30、民集10-3-242、最判昭和3・2・12、民集17-1-171)。②より、和解内容には既判力が生じるが、錯誤や詐欺など、意思表示の暇疵によって私法上の和解の効力が消滅すると、訴訟法上の効力(既判力)も発生しない。
|

|
訴訟行為と私法行為
訴訟行為とは、訴訟法上の効果の発生をもたらす当事者の行為であり(なお、広義では裁判機関の行為も含める)、訴訟の提起、事実の主張、攻撃防御方法の提出、訴えの取下げなど、訴訟の開始、進行および終了に関わる。訴訟法上の効果の発生を目的とする点で、私法行為とは異なり、①条件や期限、また、②詐欺や錯誤といった意思表示の暇疵に関する私法規定(民法第94条以下など)は適用されない。これは、例えば、②については、意思表示の暇疵に基づき訴訟行為が取消されたり、無効になるとすれば、手続の安定性が害されるためであり、また、訴訟行為には裁判所が関与しており、意思表示の暇疵を防止しうると考えられるためである。
なお、訴訟上の和解を訴訟行為として捉えるならば、意思表示の暇疵を理由に和解の成立・効力が害されることはないが、前述したように、私法上の性質を(併せ)持つと考えるならば、この私法的性質に基づき、意思表示の暇疵に関する私法規定が適用される。
|
4.2. 手続・要件
訴訟係属中、裁判所はいつでも和解を勧めることができる(第89条)。また、両当事者に和解条項を示すことができる。
和解の対象は、そもそも当事者が自由に処分しうる事項でなければならない。起訴前の和解も認められていることから(第275条)、訴訟要件の具備は不要である。
訴訟上の和解を成立しやすくするため、以下の手続も導入されている。
① 当事者が遠隔地に居住するなどの理由により出廷が困難と認められる場合には、同人が予め裁判所(または受命裁判官、受託裁判官)から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、出廷した相手方当事者がその和解案を受諾したときは和解が調ったものとみなされる(第264条、規則第163条)。
② 両当事者が裁判所(または受命裁判官、受託裁判官)の定める和解条項に従う旨を書面で、かつ、共同で申し立てるときは、裁判所は事件の解決に適切な和解条項を定めることができる(第265条、規則第164条)。
4.3. 効力
訴訟上の和解が成立すると、もはや判決を言い渡す必要性がなくなり、訴訟は終了する。
和解内容が調書に記載されると、確定判決と同一の効力が生じる(第267条)。つまり、一方の当事者が和解内容に任意に従わない場合、相手方当事者は強制執行を申立てることができる。
|