|
農 業 政 策 の 分 野 に お け る 立 方 手 続 |
共通農業政策の分野では、年間、3000以上にも及ぶ法規が制定される。これらの法規の大半は、農産物の価格、補助金また輸入農産物の課徴金等について定めているが、市況の変化に適時に対応させる必要性から、短期間の内に更新される。法規の数が膨大に上るのは、このことに由来している。
EC条約第37条第2項によれば、農業法規は、委員会の提案に基づき、また、欧州議会の意見を聴聞した後、理事会によって制定される。理事会は、特定多数決により議決する(特定多数決制度について)。
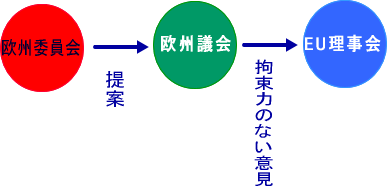
農業規則の立法手続 |
|
アムステルダム条約 発効以前のEC条約(第43条第2項)によれば、移行期間の第2段階が終了するまで(つまり、1965年末まで)は全会一致制度が、また、その後は 特定多数決制度 が適用されることになっていたが、その移行はスムーズに実現しなかった。その背景には、多数決によるならば、ある加盟国が反対票を投じたとしても法案は採択されうるが、これによって自国の主権が制限されることにフランスが強く抵抗し、1965年7月より約半年間、理事会への出席を拒否し続けたことがある。フランスの理事会欠席によって生じたECの機能麻痺に対処するため、加盟国は、国益に特に重要な案件に関しては、従来どおり全会一致制度が適用されることに合意した(いわゆる「ルクセンブルクの妥協」(1966年1月))。この議事手続は1966年より約15年間援用されたが、現在では多数決制度が適用されている。
(参照) ルクセンブルクの妥協
|
|
|
なお、理事会によって制定されるのは、農産物の市場規則(この点については後述参照)等の重要な法規とこれを実施するための一般的な法規のみであり、これらを実際に執行するために必要な規定は、委員会によって発せられる(EC条約第211条参照)。
|
委員会の立法手続には、いわゆる「行政部会手続」が適用される。同手続によれば、委員会は法案を加盟国の代表で構成される「行政部会」に提出し、その意見を聴聞しなければならない。同部会が委員会案に賛成するときは、委員会は直ちに法規を制定しうる。また同部会が委員会案に賛成しない場合であれ、委員会は、法案を採択することができるが、この場合、委員会は理事会に通知し、理事会に最終的判断を仰ぐことになる。この手続は、農業政策の分野において1962年より適用されている特殊な手続である。
| (参考) |
入稲福智「EU法上の諸問題とマーストリヒト条約の修正(2・完)」『平成国際大学論集」第4号(2000年3月)39頁以下 |
|
|
|
 欧州議会の権限 欧州議会の権限
欧州議会の立法権限は一般に強化されているが、農業政策の分野において、議会は依然として拘束力のない意見を述べうるに過ぎない(同意見に理事会は拘束されない)(諮問権限)。これは、農業政策は加盟国の利益に関わる重要な政策分野であるため、議会の関与を制限し、自らが直接統制しようとする加盟国の意志の表れである。なお、アムステルダム条約の制定作業においても、議会の権限強化の必要性が指摘されたが、特にフランスの反対により、何ら改善されずに終わった。
 その他の政策との関係 その他の政策との関係
ECの農業法規は、原則として、前述した手続に従って制定される。もっとも、法令には、農業政策だけではなく、通商政策や途上国の発展援助政策の遂行に必要な規定も盛り込まれることがあり、このような場合でも、法令はEC条約第37条のみを根拠として制定されうるかどうか、またはその他の規定(例えば、EC条約第26条、第94条、第95条、第133条、第181条、第308条ないし第310条)をも援用しなければならないかどうかが問題になる。根拠条文によって、立方手続(特に、理事会の議決制度や欧州議会の立方手続への関与の程度)が異なる場合には、非常に重要な問題となるが、EC裁判所は、農業政策に重点が置かれる場合には、第37条に基づき法規を制定しうると判示している[1]。また、農産物の第3国からの輸入に関する規定は、本来ならば、通商政策上の措置であるが(従って、立方手続はEC条約第133条による
が、同条は欧州議会の参加について規定していない)、それがEC内における価格の安定化やEC産品(EC内で生産された農産物
)の保護に不可欠である場合には、農業政策上の規定として、同第37条に基づき制定されうる[2]。
|