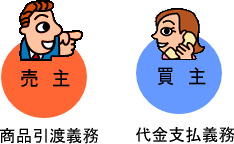前述したように、国際裁判管轄は条理に照らし決定しなければならない。この決定は、①当事者間の公平、②裁判の適正と③迅速性を考慮し、また、個々の事例の特殊性を勘案し、個別的に行う必要があるが(参照)、各事件の類型ごとに、ある一定の基準を設けることも有益である。例えば、財産関係事件については、以下のように考えることができる。 (1) 普通裁判籍による裁判管轄 民訴法第4条は、被告の住所地を基に普通裁判籍を決定するが(参照)、この規定は国際裁判管轄の決定に際しても適用してよいと解される。なぜなら、同条の趣旨である被告の保護を重視することは、公平の観念に適うからである。もっとも、「住所」の概念は、国際民訴法上の概念として捉える必要がある。なお、被告の保護という観点から、外国に住所がある場合には、国内に居所があっても、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきではないとされている[1]。 法人に関しては、主たる事務所や営業所が国内にある場合には、我が国の国際裁判管轄権が認められる。従たる営業所や事務所については、訴えが、同営業所や事務所の業務に関連する場合には、民訴法新第5条第5号の特別裁判籍として考慮される。
(2) 義務履行地の裁判管轄 民訴法第5条第1号が義務履行地の裁判所に管轄権を与えているのは、その地で履行を請求されることが債務者にも予測できることや(被告の予見可能性)、判決に基づき義務履行地で義務を履行することは契約の趣旨に合致して いるためである。これらの点を考慮すると、同規定に基づき、国際裁判管轄権の所在を決定してもよいと解されるが、学説や判例の立場は必ずしも統一されていない。
不法行為に基づく損害賠償義務については、履行地の管轄は一般に認められていない。これは、不法行為には特別の裁判管轄が認められること(民訴法第5条第9号および後述参照)、当事者の予測可能性や裁判の適正・迅速性などの観点から適切ではないと考えられるためである[2]。
他方、契約上の義務の場合には、例えば、商品を引渡地の国際裁判管轄を認めるものの、代金の支払義務(金銭債務)の履行地の国際裁判管轄は認めないとする立場が有力である。これは、特に、代金支払地と裁判管轄地(法廷地)との関連性が薄いことに基づいている(なお、後述の双務契約を参照されたい)。契約義務違反より生じた損害の賠償請求については、学説は賠償義務履行地の 国際裁判管轄を一般に否定しているが(前述の不法行為の場合と理由は同じである)、これを認める裁判例も少なくない。 なお、双務契約の場合は、どの義務の履行地の裁判所が国際管轄権を有するかどうかが問題になる。例えば、ある商品の売買契約より、商品の引渡義務と代金の支払義務が発生するが、どちらの裁判所が管轄権を有するかを決定しなければならない。この問題について、ブリュッセル条約第5条第1号は、商品の提供地(役務の場合は提供地)をこの義務履行地としている。
さらに、「義務」の内容ないし「履行地」の特定に困難な場合がある。契約準拠法(契約の成立、内容または効力について定める法令)により、持参債務になったり、取立債務になったりする債務の場合には(民法484条参照)、義務履行地に基づき、国際裁判管轄を決定すべきではないと解される。当事者間で履行地が定められていないケース(被告の債務不履行より生じた損害の賠償請求)において、東京地裁は、「法廷地国〔日本〕の国際私法により選択された契約準拠法の適用によって初めて義務履行地が我が国内にあることを唯一の根拠として我が国の国際裁判管轄を認めるのは、多くの場合、被告において予測が困難であって、当事者の公平に反するおそれがあるし、原告の主張するところによれば、結局原告の住所地が日本国にあるような場合には契約上の紛争のほとんどについて我が国の国際裁判管轄を認めてしまう結果になる」との見解を示した後、本件訴訟当事者間の契約は英文で作成されていたこと、また、決済はポンドで行われていたとう事情を考慮すると、債務不履行責任の準拠法が日本法であり、民法第484条に基づき、義務履行地が日本とされる場合であれ、我が国での応訴を被告に強いることは当事者間の公平の理念に反するため、我が国の国際裁判管轄を否認する特別の事情があると判断した(東京地裁平成10年11月2日判決、判タ第1003号292頁)。 (3) 財産所在地 被告の財産が、請求の目的物である場合には(例えば、買主が売主に対して、売買契約の目的物である車の引き渡しを求める場合)、目的物の所在地を基準に国際裁判管轄を決定しても良いと考えられる(民訴法第5条第4号参照)。なぜなら、この場合には、被告の保護(予見可能性)、裁判の適正や給付判決の実現可能性の要請が満たされるからである(参照)。 他方、請求と直接関係のない被告の一般財産をも管轄原因として考慮することは、過剰な管轄権の決定であるとして批判される[3]。もっとも、原告の権利実現の実効性を確保する観点から、給付の訴えに限り、請求額と問題となる財産の価値の均衡を考慮して、財産所在地国の裁判管轄を認めるとする見解がある。ただし、この見解は、最高裁のマレーシア航空事件判決 の趣旨と合致しない。 (4) 不動産所在地 不動産所在地を国際民事事件における専属の管轄原因とすることは(民訴法第5条第12号参照)、国際慣習法として定着している。このような実務運営は、不動産の登記または登録制度、また、証拠調べなどの観点から、国際民訴法の条理にかなうと言える。
(5) 不法行為地 不法行為地の裁判籍(民訴法第5条第9号)は、原則として、国際民事事件にも適用される。なぜなら、不法行為地では証拠の収集が容易であるり、裁判の適正や迅速性の要請に適い、被害者の迅速かつ容易な権利実現にもかなうからである[4]。また、加害者(被告)は不法行為地での応訴を予測しうる 。
第5条第9号の規定によれば、不法行為地の裁判所に訴えを提起することができるが、この「不法行為地」には、事故発生地だけではなく、損害発生地(すなわち、被害者の住所地)も含まれると解されている。
身分関係事件においても、当事者間の公平や裁判の適正・迅速性といった手続法上の理念を考慮する必要があるが、身分法上の特殊性も勘案しなければならない。例えば、日本の法令に基づき裁判を行う場合にのみ(すなわち、準拠法が日本法である場合にのみ)、日本の国際裁判管轄を肯定するという見解も成り立つ。
判例は、被告の住所地に照らし国際裁判管轄を決定するという前提に立っているが[5]、ある事件の特殊事情を考慮して、紛争解決の妥当性を確保している。例えば、最高裁は、原告である妻が行方不明の夫に対して提起した離婚請求訴訟につき、「原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」には、被告(夫)の住所が日本にない場合あれ、我が国の国際裁判管轄を認めた[6]。 (2) 親子関係事件の国際裁判管轄 親子関係事件においては、子の保護を優先すべきであるから、子の普通裁判籍を基準にして、国際裁判管轄について定めるべきである(人事訴訟手続法第27条参照)。
[1] 大阪高判平成4年2月5日、判タ783号350頁。 [2] 例えば、東京地判昭和62年6月1日(金融商事790号32頁)は、不法行為に基づく損害賠償債務の履行地(裁判が行われる場所)の予測は被告にとって困難であり、当事者の公平に反するおそれがあるため、義務の履行地を基準に国際裁判管轄を決定すべきではないとする。 [3] なお、ハワイ所在の不動産売買の仲介手数料の請求事件において、被告の不動産が日本国内にあることに基づき、国内の裁判管轄権を認めたものとして、東京地判平成3年5月22日、判タ755号213頁。 [4] なお、遺族の生活の本拠地を不法行為地として捉える見解もある。例えば、民訴判例百選I(新法対応補正版)41頁(渡辺)参照。 [5] 基本的には、人事訴訟手続法1条を基本にして、国際裁判管轄について決定すべきであるとする見解もある。国内事件については、裁判所ウェッブサイト を参照。 [6] 最判昭和39年3月25日、民集18巻3号486頁。
|
|
|
「国際民事訴訟法講義ノート」のトップページに戻る