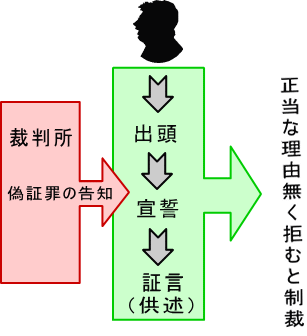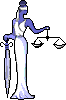 |
E. 訴 訟 の 審 理
|
6. 証明 6.1. 証明とは |
|
ある事実(主要事実)について、当事者間に争いがない場合、裁判所はそれをそのまま採用し、判決の基礎にしなければならない(弁論主義の第2テーゼ)。例えば、売買代金の支払いを求める訴訟において、被告が買ったことを認めるとき(売買契約の締結にかかる自白)、裁判所は売買があったと認定しなければならない。これに対し、被告が「買った覚えはない、プレゼントされた」と主張し、売買の存在を争うときは(否認)、証拠に基づく証明を必要とする(証拠裁判主義、第247条参照)。 通常、裁判所は当事者が提出した証拠(証拠方法)に照らし判断しなければならない。つまり、裁判所が職権で証拠を収集し、それに照らして判決を下してはならない(弁論主義の第3テーゼないし職権証拠調べの禁止)。ただし、職権探知主義が適用される特別なケースでは、職権で証拠を収集し、裁判の基礎にすることができる( (1) 証明と疎明
これに対し、迅速な処理を必要とする事項や派生的な手続問題については、一応、確かであるという程度の蓋然性があれば足り、これを 疎明(そめい)という(第35条第1項、第44条第1項、第198条など)。
(1) 事実 ① 主要事実 ( 権利または法律関係の発生・変更・消滅を基礎付ける事実を主要事実ないし直接事実と呼ぶ。例えば、売買代金を請求する訴訟では、a) 売買契約の締結やb) 商品の引渡し等がそれらに当たるが(参照)、被告がこれらの点について争うとき(否認)、原告は証明しなければならない。ただし、裁判所に顕著な事実については証明を必要としない(第179条)。また、相手方当事者が自白した事実についても証明を必要としない。
主要事実の証明が困難なときは、間接事実 を通じて、その真否を推認することになるが(参照)、このようなケースでは、間接事実についても証明しなければならない。
|
|
(例) |
特段の事情の無い限り、時価より著しく安い値段で売買が行われることはないと解される。このような経験側(取引上の通念)に基づき、最高裁は、建物の売買が実際に行われたかどうかが争われたケースにおいて(実際には売っておらず、登記の移転も仮装されたものであるとし、登記の抹消が請求されたケース)、時価約165万円の建物等を約10万円で売買することは、経験則上、是認できないと判断した。詳細には、確かに、持ち主が税金を滞納していたため、本件建物は差し押さえられていたという事実も存するが、滞納額は約13万円であり、それを差し引いても約152万円の価値がある建物を約10万円で売ることは、経験則上、是認できないため、特段の事情の有無について審理することなく、売買がなされたと判断した原判決は審理不尽、理由不備の違法があるとした(最判昭36・8・8、判例百選II
〔新法対応補正版〕420頁)。
|
|
経験則には、社会人なら誰でも知っている一般常識的なものや、専門家でなければ知りえないものがある。前者は証明を要しないが、後者は、当事者に攻撃防御方法を尽くさせ、公正な裁判を実現するために証明が必要と解されている。また、担当裁判官が個人的な研究や私的経験から知りえた経験則も証明を要する(第23条第1項は、裁判官が証人や鑑定人になり えないと定めているのも同趣旨である)。
裁判官が取り調べることができる有形物を 証拠方法 と呼ぶ。これには、証人、当事者本人、鑑定人 を対象にする 人証 と、文書、検証物などを対称にする 物証 がある。
(2) 証拠資料 証拠方法の取り調べによって裁判官が感得した内容を 証拠資料 という。
(1) 当事者による申出 当事者間で争いのある事実について証拠調べが行われるが、弁論主義 の第3テーゼに基づき、証拠調べは、原則として、当事者の申し出た証拠(証拠方法)について行われる(なお、例外的に 職権証拠調べ が可能な場合について、第14条、第207条第1項、第228条第3項、第233条等を参照されたい)。 期日における取調べを可能にするため、申出は期日の前に行うことができる(第180条第2項)。なお、裁判長は特定の事項に関する証拠の申出期間を定めることができる(第162条)。
相手方当事者の 証拠抗弁 を考慮したうえで、裁判所は証拠申出に応じ、証拠調べを行うべきかどうか決定する(第181条第1項参照)。これを 証拠決定 と呼ぶ。裁判所によって審査されるのは以下の点である。
証拠決定は、相当と認められる方法で告知すればよい(第119条)。なお、この決定に対し、当事者は直ちに独立の不服申立てを行うことができず、判決が下された後に上訴しうるに過ぎない(第283条)。
人証には、証人、当事者、鑑定人があり、裁判官はそれらを取り調べることができる。 証人尋問とは、証人となる者に口頭で質問し、その経験した事実を供述(証言)さ せる形で行われる証拠調べを指す。 ② 証人義務(第190条)
省略
省略
物証の対象となるのは、① 契約書や文書記録などの文書や、② 売買の目的物や事故現場などの検証物であるが、①の取調べを 書証、また、②の取調べを 検証 と呼ぶ。以下では、書証について説明する。
|
|
(例) |
契約書、借用書、医師の作成したカルテ |
|
⇒ |
図面、写真、録音・録画テープは、思想が表現されていないので文書にはあたらないが、文書に準じて書証の対象になる(準文書、第231条)。 フロッピーディスクや光ディスク は、プリントアウトし、文書に準じた取り扱いがなされる。 |
|
文書は、真に作成名義人によって作成され、その内容が正しくなければならない。真に作成名義人によって作成されている場合、成立が真正 であるという(第228条第1項参照)。この場合、文書は 形式的証拠力 を有し、記載内容がどの程度、要証事実の証明に役立つか(実質的証拠力) 、裁判官によって判断される。 |
|
成立の真正 → 形式的証拠力 → 実質的証拠力の調査 |
|
|
例外的に提出が義務付けられない文書(第220条第4号)
なお、上例のケースに該当し、文書提出義務が否認されるかどうかを調べるため、文書の提出を命じることができる(第223条第6項、イン・カメラ手続)。 |
|
文書を所持する当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書に記載された事項に関する相手方の主張が正しいと擬制される(第224条第1項)。当事者が相手方の使用を妨げる目的で文書を滅失させたり、その他の方法により使用できなくした場合にも、同様に、当該文書に記載された事項に関する相手方の主張が正しいと擬制される(第2項)。さらに、これらのケースにおいて、相手方が当該文書の記載について具体的な主張をしたり、当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる(第3項)。 文書提出命令の申立ては、以下の事項を明らかにして書面でしなければならない(第221条第1項)。 |
|
・ |
文書の表示(→ 特定が著しく困難なケースについて、第222条参照) |
||
|
・ |
文書の趣旨(→ 特定が著しく困難なケースについて、第222条参照) |
||
|
・ |
文書の所持者 |
||
|
・ |
証明すべき事実(要証事実) |
||
|
・ |
|
|
証拠抗弁 とは、当事者の一方が行った証拠申出について、相手方が、① 申出手続が違法であること、または、② 証拠適格、証拠能力、もしくは、証拠力に欠けることを理由とし、裁判所に証拠申出の却下を求めたり、または、すでに行われた証拠調べの結果の不採用を求める陳述を指す。 |
|
|
証拠共通の原則 とは、口頭弁論において適法に行われた証拠調べの結果は、どちらの当事者によって証拠調べが申し立てられたかを問わず、事実認定の基礎に用いることができるとする建前を指す。例えば、裁判官は、原告が申し出た証拠より、同人に有利となる事実だけではなく、相手方(被告)に有利な事実を認定することもできる。これによって、事実認定が適切に行われるようになる。 |
|
|
「民事訴訟法講義ノート」のトップページに戻る