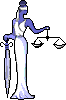 |
E. 訴 訟 の 審 理
|
8.証明責任 8.1. 証明責任とは 貸金の返済を求め提訴する原告は、以下の事実を主張しなければならない(民法第587条参照)。 |
|
① |
貸金の返済の約束(金銭消費貸借契約の締結) |
|
② |
金銭の授受 |
|
③ |
貸金返済期限 の経過 |
|
被告がこれらの事実(主要事実)[1] の真偽ないし存否を争うとき、原告はそれを証明するため、裁判所に 証拠調べ を申し出る必要があるが(→ 証拠申出)、裁判所がどのような証拠を調べても、その真偽ないし存否が不明な場合がある。このような状態を ノン・リケット(non liquet 〔ラテン語〕 )と呼ぶが、このような場合であれ、裁判所は裁判を拒絶してはならない。そのため、真相不明の事実を真実または偽り(ないし、事実の存在または不存在)と擬制する必要がある。例えば、上例の②の事実の存否が不明なとき、②の事実は存在しないと擬制される。そうすると、原告の貸金返済請求は認められなくなるため、原告に不利となる。このように、要証事実の真偽ないし存否が不明の場合、自己に有利な法律効果の発生が認められなくなる不利益を 証明責任 と呼ぶ。 |
|
|
上述したように、証明責任は、ノン・リケットによる裁判拒絶を回避するために導入されたテクニックであり、要証事実が証明されなかった場合の 結果責任 である点に着眼して 客観的証明責任 と呼ばれることがある。これに対し、要証事実を証明するために、証拠を提出する 行為責任 を 主観的証明責任 という。弁論主義 の下では、これらの2つの証明責任を負う者は同一である。つまり、ある事実について証明しなければならない者は、その真偽が不明なとき、不利な扱いを受ける。 |
|
|
8.2. 証明責任の分配 ある事実について、原告または被告のどちらが証明責任を負うべきであろうか。その定めを 証明責任の分配 と呼ぶが、これは予め決まっており、訴訟の途中で変更されることはない。 |
| (例) | |
|
・ |
|
|
・ |
雇用契約(民法第623条)に基づく報酬支払請求のケースでは、以下の事実について、原告が証明責任を負う。 |
|
|
① 雇用契約の締結 ② 契約で定めた労働の終了(民法第624条参照) |
|
これらの請求権の根拠条文である民法第587条、第623条や第624条は、権利の発生について定めているため、権利根拠規定 と呼ぶ。これに対し、一旦、発生した権利を消滅させる事由について定める規定を 権利消滅規定、また、権利の発生を阻害する規定を 権利障害規定 という。通説・判例は、このように法規を3つの類型に分けた後、それぞれの構成要件について、以下のように証明責任を分配する。
|
|
① 権利根拠規定 |
権利の発生を主張する者が、構成要件に該当する事実の証明責任を負う
|
||
|
② 権利消滅規定 |
権利の消滅を主張する者が、構成要件に該当する事実の証明責任を負う
|
||
|
③ 権利障害規定 |
権利発生の阻害を主張する者が、構成要件に該当する事実の証明責任を負う
|
|
なお、民法第95条や第715条第1項の但書きは、その適用を主張する者が構成要件該当事実の証明責任を負う。 (例) 売買代金の支払請求訴訟( |
|
・ |
売買契約の成立や目的物の引渡しなど |
→ |
原告が証明責任を負う |
|
・ |
錯誤による売買契約の無効(民法第95条本文) (抗弁) |
→ |
被告が証明責任を負う |
|
・ |
錯誤について、買主の重過失(民法第95条但書)(再抗弁) 重過失は障害事実(錯誤)の障害事実にあたる。 |
→ |
原告が証明責任を負う |
|
8.3. 証明責任の転換 権利行使を容易にするといった特別の政策的理由に基づき、証明責任が転換されている場合があるが、これは予め定められており、訴訟の途中で転換されるわけではない。
|
|
(例) |
自動車事故による損害賠償請求について、加害者の過失(自賠法第3条但書) 民法第709条に基づき、加害者に損害賠償を請求するときは、原告(被害者)が被告(加害者)の過失について証明しなければならないが(参照)、自賠法第3条但書に基づき損害賠償を請求するときは、被告が過失のなかったこと(無過失)について証明しなければならない。 |
|||
|
|
|
|
「民事訴訟法講義ノート」のトップページに戻る