|
|
EU内では、人、商品、資本、サービスの自由な移動が保障されている(参照)。域内経済活動の自由化というこの理念の下、例えば、ある企業が他のEU加盟国内で経済活動を行ったり、また、その一環として、 他国の企業を買収することは容認されるべきであるが、2006年春、外国企業による買収を規制する例が相次ぎ、保護主義の風がヨーロッパを吹き抜けている。その背景には、
近年来の企業買収ブームがある。€uro誌(2006年第4号10頁)によれば、2006年の買収額は、すでに3000億円に達しており、 「早春の経済的氷結」をクローズアップさせたのも、エネルギー部門における事例であるが、イタリアの大企業 ENEL がフランス企業 Suez の買収計画を発表したところ、フランス政府はこれを阻止するため、Suez を国営の Gas de France と合併させ、経営体制を強化した。総選挙を間近に控えたイタリア政府は、この方針を「経済ナショナリズム」として厳しく批判するとともに、3月23・24日の欧州理事会 (EU加盟国首脳会議)に向け、保護主義を批判する書簡をEU加盟国政府に送り、「経済ナショナリズム」を非難する声明の採択を目指した。もっとも、最大の同調国と目されていたオランダは、3月22日、審議期間が十分にとれないことを理由に、イタリアの急な提案を支持しなかった。自由主義を標榜するイギリスも慎重な態度を崩さなかった他、フランスとの協調路線をとるドイツも、イタリア案が採択される可能性は小さいとし、これを支持しなかった(Handelsblatt v. 23. März 2006, Seite 2)。もっとも、自らの行為はさておき、保護主義そのものを非難することで各国の見解はおおむね一致しているとみることができよう。 欧州理事会の約2週間後に開かれたEU理事会(経済相会議〔ECOFIN〕)は、経済的保護主義を明瞭に非難するとともに、保護主義が高い失業率の原因になっているとしている(参照)。
前述したケースの他に、E.on (ドイツ)による Endesa (スペイン)の買収をスペイン政府が禁じたり、Mittal Steel (インド)による Arcelor (ルクセンブルク)の買収をルクセンブルク政府が阻止したこと、また、Unicredit (イタリア)による BPH 銀行(ポーランド)の買収をポーランド政府が妨げたことも波紋を広げているが、各国政府は、外国企業による買収は国益に大きな影響を及ぼすと述べている。このような状況をイタリアの Giulio Tremonti 経済・財務相は、第1次世界大戦の開戦前夜に似ているとし、各国の経済ナショナリズムを批判している。この発言は、4月初旬に実施されるイタリア国内総選挙をにらんだものであるが、批判の対象である各国の行為は、国内企業ないし国内における雇用の確保を主たる目的としている。前述したように、保護主義は、むしろ経済発展の妨げとなることが一般に認識されているが、芳しくない国内経済情勢の下、多くの加盟国はEU統合の理念を実現しきれていない。政権基盤の弱いフランスは、東方拡大 や経済統合に対する国民の不満をさらに助長させないようにするため、自国企業の買収を阻止する必要があったが、各セクターにおける national champions の育成という国家方針もその背後に横たわっている。
|
| 買収者 | 買収された | 総額(10億ユーロ) |
| GdF (F) | Suez (F) | 47.5 |
| E.on (D) | Endesa (ES) | 29.1 |
| Mittal (india) | Arcelor (Lux) | 18.6 |
| Merck (D) | Schering (D) | 15.0 |
| (参照) |
€uro, 2006 Heft
4, Seite 10 (Europa ist Tot) Capital 2006 Heft 6, Seite 16-20 (Eins zurück, zwei vor) Handelsblatt v. 23. März 2006, Seite 2 (Im Ziel einig, im Weg nicht) FAZ v. 9. April 2006 (EU-Finanzminister gegen Protektionismus)
|

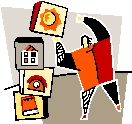 これは前年の3倍に相当する。特に、エネルギー部門では、2007年 中旬に予定されている自由化をにらみ、企業買収が加熱しているが、近時の原油高やロシア・ウクライナ間のガス供給問題
によって、エネルギー源確保の重要性が再認識される中、加盟国は国内企業の買収に神経を尖らせている。
これは前年の3倍に相当する。特に、エネルギー部門では、2007年 中旬に予定されている自由化をにらみ、企業買収が加熱しているが、近時の原油高やロシア・ウクライナ間のガス供給問題
によって、エネルギー源確保の重要性が再認識される中、加盟国は国内企業の買収に神経を尖らせている。