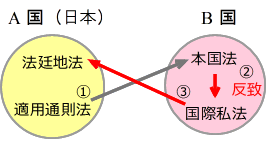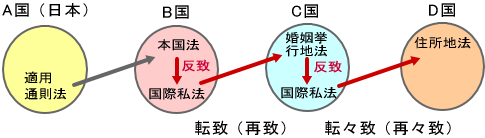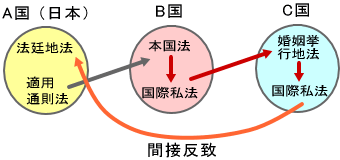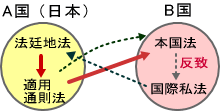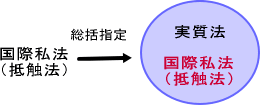1.反致とは 渉外事件に適用される準拠法(実質法)は、国際私法(抵触法)に従い決定されるが、各国はそれぞれ独自の国際私法を制定している。例えば、我が国では法の適用に関する通則法(適用通則法)、ドイツではEinführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB[民法施行法])という名称の法律が制定されている。他方、スペインは特別法を制定せず、民法典の中に国際私法規定(抵触規定)を置いている。
ところで、各国の国際私法は統一されておらず、それらを同時に適用すると、準拠法が定まらない(存在しない)ように見える場合がある。これを国際私法の消極的抵触とよぶが、例えば、以下の事例を検討されたい。 (1) フランス破毀院のフォルゴー事件判決[1] ドイツ・バヴァリア(現在のバイエルン州)出身のフォルゴーは、5歳の時にフランスに移住し、68歳で死亡するまでフランス国内で生活した。彼の死後、彼がフランス国内に残した財産(動産)の相続について争いが生じたが、フランスの相続法によると、彼には相続人がいないため、遺産は国庫に帰属するものとされた。これに対し、バヴァリアに居住する彼の親族が、バヴァリアの相続法によれば、相続人に当たるとして、財産の返還を求める訴えを提起した。
フランス法とバヴァリア法のどちらによるかは、渉外事件であるので、国際私法に基づき決定される。両者の国際私法は次のように定めていた。
これらの国際私法によると、準拠法は次のように決定される。
破毀院は、②のように考え、フランス法が準拠法になるとし、フォルゴーの親族の主張を退けた。
(2) 反致の定義 このように、法廷地国(前掲の事例でいえば、フランス)が、準拠法国(バヴァリア)の国際私法による準拠法の選択に従うことを反致とよぶ。適用通則法第41条は反致を認めているが(詳しくは こちら)、認めない国もある[5]。
反致にはいくつかの形態がある。フォルゴー事件で、フランス破毀院が判示したように、準拠法国の国際私法に従い、自国法(法廷地法)を準拠法に指定することを狭義の反致というが、その他の類型について、以下の事例を通し説明する。
① 狭義の反致 法廷地であるA国(日本)の国際私法によると、準拠法はB国法(本国法)になるが、B国(準拠法国)の国際私法に従い、日本法を準拠法に指定する場合を狭義の反致と呼ぶ。前掲のフォルゴー事件もこれに当たる。なお、後述するように、適用通則法第41条はこの形態の反致を認めている。
② 転致または再致 転々致または再々致 法廷地であるA国(日本)の国際私法によると、準拠法はB国法(本国法)になるが、B国(準拠法国)の国際私法によれば、C国法(婚姻挙行地法)が準拠法に指定される場合を転致または再致と呼ぶ。 さらに、C国の国際私法に基づき、D国法(住所地法)を準拠法とする場合を転々致または再々致と呼ぶ。
③ 間接反致 ②のケースで、C国の国際私法によれば、A国法(法廷地法)が準拠法になる場合を間接反致と呼ぶ。
④ 二重反致[6] ①のケースで、B国の国際私法も反致を認めており、それに従い、もう一度、反致を行えば、二重反致が成立する。すなわち、B国の国際私法に基づき、A国法を準拠法に指定することによってまず反致が成立するが、さらに、A国(最初の反致による準拠法国)の国際私法に基づき、再び反致させることを二重反致と呼ぶ。
⑤ 隠れた反致[7] 訴えが提起された国が国際際裁判管轄を有すれば、同国の法令(法廷地法)を準拠法とすることを隠れた反致と呼ぶ。例えば、XY間の婚姻の成立に関する訴えの管轄権がA国に与えられるとすれば、A国法が準拠法となる。 (4) 反致の理論的説明 国際私法(抵触法)は、ある渉外事件は、どの国の法令に従って解決されるかを決定する法令であるが(準拠法の指定)、指定されるのは実質法であり、これには抵触法は含まれないと解される(通説)。しかし、反致は、準拠法国の国際私法(抵触法)をも考慮する。これは、理論的にどのように説明すればよいであろうか。 反致の理論的根拠は、以下のように説明される。 ① 総括指定説 これは、国際私法は、外国法全体(すなわち実質法だけではなく、抵触法も含む)を準拠法として指定すると解する見解である(ドイツ法的見解)。また、指定された外国法(準拠法)は、その外国の裁判所と同じように適用されなければならないとする立場もある(イギリス判例上の外国裁判所追従説)。
もっとも、準拠法所属国もこの見解に従うとすれば、準拠法は決定されえないこと(例えば、前掲のフォルゴー事件において、バヴァリア法も反致を認めるとすると、また、フランスの国際私法を適用しなければならなくなる)、また、我が国では、一般に、国際私法によって準拠法と指定されるのは、あくまでも実質法である(抵触法は含まれない)とされているため、我が国では、この見解は支持されていない。 ② 棄権説 準拠法として指定された法令を持つ国(準拠法所属国)が、自国法の適用を放棄している場合にはこれに従うべきであり、あえてその国の法令を適用することは主権の侵害にあたると解する見解も主張されれている。この理論は、「王に勝る王党なし」(Ne soyez pas plus royaliste que le roi)と表現されることもある。 もっとも、準拠法所属国の法令を適用をしても、同国の主権に触れることはないため、このような理論は現在では支持されていない。 従って、反致は理論的に説明できないとするのが我が国の通説である。 (5) 反致の実質的根拠 前述したように、反致は理論的に説明しえないが、それでもなおこれを認めるのはなぜであろうか。反致を成立させると、どのような利点が生じるであろうか。反致の長所として、以下の点が指摘されている。 ① 内国法適用の拡大 狭義の反致を認めると、内国法(法廷地法)が準拠法になるため、法の解釈・適用に関する裁判所の負担が軽減される。このような内国法優先の考えは、国際私法の基本原則に反するが、実務では強く支持されている。適用通則法の制定の際にも、反致の是非について審議されたが、反致条項に従い日本法が準拠法とされれば、在日外国人の相続に関するケース等において適切な解決が図られるとする実務運用を考慮し、規定が維持された[8]。 ② 国際的判決の調和 例えば、XとY(ともにA国に常居所を持つB国人)の婚姻の成立が争われるケースにおいて、A国の国際私法によれば当事者の本国法が準拠法となり、B国の国際私法によれば当事者の常居所地法が準拠法となるものとする。
また、A国の民法によるとXとYの婚姻は成立するが、B国の民法によれば成立しないものとする。 訴えがA国に提起される場合、A国の国際私法によれば、準拠法はB国法(本国法)になるが、反致(狭義の反致)を成立させると、準拠法はA国法(常居所地法)になる。また、訴えがB国に提起される場合も、B国の国際私法に基づき、A国法が準拠法になる。すなわち、A国の裁判所であれ、B国の裁判所であれ、A国法に基づき判決を下すため、国際的に判決の内容が調和しうる。これに対し、反致を認めないと、A国の裁判所はB国法に照らし、他方、B国の裁判所はA国法に照らし判示することになるので、判決の内容が異なる。 もっとも、他国(準拠法所属国)が反致を認める場合には、この利点は生じない。すなわち、B国に訴えが提起され、B国も反致を認めるとすると、準拠法はB国法となる。
2. 我が国における反致 (1)狭義の反致(適用通則法第41条) 適用通則法第41条は、狭義の反致のみを認めるが、以下の点に注意を要する。 ① 反致は、本国法によるべき場合にのみ認められる。 具体的には、適用通則法第4条~第5条、第24条、第28条~第31条および第33条~第37条が適用されるか、または、これらの規定が準用される場合にのみ、反致は認められる。他方、例えば、行為地法が準拠法になる場合(例えば、第14条)は反致は行われない。 なお、第25条(同条が準用される場合を含む)および第32条も、本国法を準拠法にしているが、この場合、反致は認められない(第41条但書)。その理由は、これらの規定は、まず両当事者の共通本国法、それがないときは共通常居所地法というように(段階的連結)、当事者双方に関連する法を準拠法に指定しているため、例えば、夫が日本人、妻が韓国人という場合において、妻について反致を成立させ、日本法を共通本国法として適用するよりも、当事者双方に関連する法を適用すべきであること[9]、また、前掲の規定の適用事例(婚姻の有効性、離婚、親子関係等)に関しては、他国の国際私法の適用が困難であったり、不適切な結果を招くことに基づいている[10]。 無国籍者の本国法が問われる場合は、常居所地法が適用されることになるため(第38条第2項本文)、反致は認められない。また、扶養義務や遺言の方式については、「扶養義務の準拠法に関する法律」または「遺言の方式の準拠法に関する法律」に基づき、本国法が準拠法となる場合でも、反致は成立しない(第34条)[11]。
② 第41条本文の 「その国の法」とは、その国の国際私法を指す。 「日本法」とは、日本の実質法を指す。日本の国際私法(適用通則法)もこれに含まれるとすれば、二重反致が生じる。 (2)転致または再致(転々致または再々致) 適用通則法上、このような反致は認められない。 他方、手形法第88条第1項後段および小切手法第76条第1項後段は、このような反致も認める。 (3)間接反致 間接反致は一般に認められない。ただし、適用通則法によって準拠法と指定された国(準拠法国)の国際私法が転致(または再致)を認めることによって第3国法が準拠法に指定され、その第3国の国際私法が日本法を準拠法にしているときには、間接反致は認められる。なぜなら、この場合には「その国〔準拠法国〕の法に従えば日本法によるべきとき」(適用通則法第法第41条)にあたるからである。間接反致を認めることによって、国際私法の消極的衝突(準拠法が定まらない場合)が解消され、判決の国際的調和が達成されるといった利点がある。 (4)二重反致 二重反致の許容性については争いがある。適用通則法第法第41条の「その国の法」の中には、反致に関する規定も含まれるため、適用通則法上、二重反致を認めるべきとする見解が主張される一方で、「その国の法」も二重反致を認めるときは、準拠法が決定しない(国際私法の積極的衝突)などの問題点もある。例えば、上掲の設例において、A国もB国も二重反致を認めるとすると、循環論のような状況が生じ、準拠法が決まらない。それゆえ、一般に 、二重反致は認められていない。 (5)隠れた反致
(1)セーフガード条項が適用される場合にも反致が認められるか 養子縁組の準拠法は、養子縁組当時の養親の本国法によるが(適用通則法第31条第1項前段)、養子の立場を保護するため、養子の本国法上、ある一定の要件が必要となる場合には、その要件を満たすことも必要になる(同後段)。このような規定をセーフガード条項と呼ぶ(その他の例として、子(非嫡出子)の認知に関し、第29条第1項および第2項参照)。 このような場合には、子の本国法上の保護を確保する観点から、反致を認めるべきではない(反致を成立させると、子の本国法の代わりに日本法が適用される)とする見解が主張されるが、第41条の解釈論としては支持しえない[12]。 (2)準拠法が選択的に決定される場合にも反致は認められるか 適用通則法第24条第2項および第3項によれば、婚姻の方式に関する準拠法は、婚姻挙行地法か、当事者の一方の本国法になる(準拠法の選択的決定)。その他に、第28条第1項、第29条第2項、第30条第1項も、複数の準拠法の中から選択を認めている。 このような場合、反致を認めると、準拠法の選択の範囲が狭められることもあるので(例えば、アメリカ人男性と日本人女性がカナダで婚姻するとき、その方式は、男性の本国法(アメリカ法)によることもできるが、アメリカの国際私法に従い、反致を成立させるときは、アメリカ法は適用されなくなる)、反致を認めるべきではないとする見解が主張されているが、適用通則法第法第41条の解釈論としては支持しがたい[13]。
[1] 櫻田『国際私法』[第2版]104頁以下参照。 [2] これは、フォルゴーが、当時のフランス国内法上、外国人の住所所得に必要な政府の許可を得ていなかったことに基づく。 [3] なお、我が国の通説はこのように解していない。 [4] なお、この点につき、道垣内「ポイント国際私法総論」214頁も参照されたい。 [5] 例えば、ギリシャである。これに対し、ドイツやフランスの国際私法は反致を認める。 [6] 東京高裁昭和54年7月3日判決、渉外判例百選(第3版)10頁以下参照。 [7] 那覇家裁平成3年4月11日審判、渉外判例百選(第3版)8頁以下参照。 [8] 小出『一問一答 新しい国際私法』155頁参照。 [9] これとは異なり、両当事者の本国法が同じ場合には反致を成立させても、第14条ないし第21条の段階的連結の趣旨に反しないと解される(例えば、夫婦が共にA国法を本国法とする場合は、A国の国際私法に基づき、反致を成立させることもできよう)。 [10] 溜池『国際私法講義』[第2版]157頁参照。 [11] それぞれにつき、特別法である「扶養義務の準拠法に関する法律」および「遺言の方式の準拠法に関する法律」を参照されたい。 [12] この点につき、櫻田『国際私法』(第2版)112頁、道垣内「ポイント国際私法 総論」226頁以下参照。 [13] この点につき、道垣内『ポイント国際私法 総論』227頁以下参照。 |
|
|
「国際私法講義ノート」のトップページに戻る