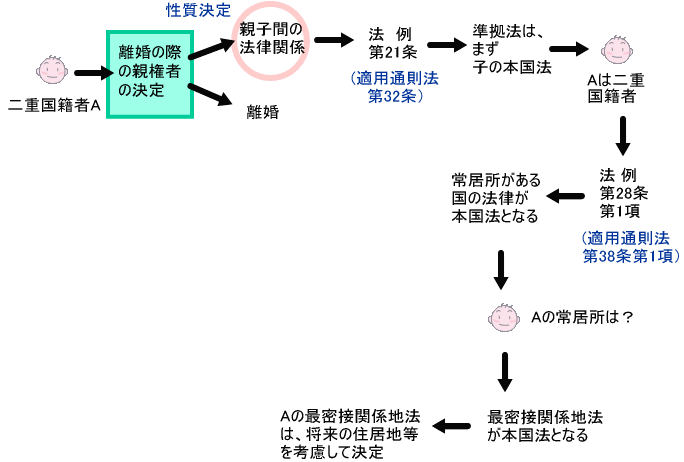|
�A �@���@ �_ |
1.�@�A���_�Ƃ� �@�K�p�ʑ��@�͖@���W�i�P�ʖ@���W�j�̉��炩�̗v�f��}��ɂ��ď����@���w�肷���B�Ⴆ�A��f�̃P�[�X�ł́A���ʔ����n����Ƃ��A�����@����܂�B���̂悤�ȏ����@�����肷��v�f���A���_�Ƃ�ԁB���̗�Ƃ��ẮA���łɎw�E�������ʔ����n�̑��ɁA�ȉ��̂��̂���������B�@ (1) ���� �@�l�̐g���E�\�͂Ɋւ�����͖{���@�ɂ��A�܂�A�����@�͍��Ђ���ɂ��Č��肳���̂���ʓI�ł����i��4���A��5���1���A��6���1���A��24���`��37���Ȃǁj�B����́A�{���@�������@�ɂ���ƁA�����҂̖{���̕����A�K���Ȃ����������f�����������\�ɂȂ�Ƃ̍l���Ɋ�Â��Ă���B�܂��A���Ђ͍P��I�ł��邽�߁A�����@����̈��萫�Ɏ����邪�i��ʂɁA����l�̍��Ђ��ύX����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�����@���ύX����邱�Ƃ͂Ȃ��j�A�ȉ��̂悤�ȏꍇ�ɖ�肪������B
(2) �틏�� �@��f�̃P�[�X�Ȃǂ̂悤�ɁA���Ђ�A���_�Ƃ����̂ł͏����@����܂�Ȃ��ꍇ�́A�����҂̏틏�����l��������i��8���2���A��19���A��25���Q�Ɓj�B �@�틏���Ƃ́A�u�Z���v�̊T�O���e���œ��ꂳ��Ă��Ȃ����Ƃ�萶��������������邽�߂ɑn�o���ꂽ���ێ��@��̊T�O�ł���B���ۓI�ɂ��̒�`�͂܂��m�����Ă��Ȃ����A��ʂɁA�l���������ԋ��Z���A�����ɐ������Ă���ꏊ���w�����A�����҂̈ӎv��K�v�Ƃ��Ȃ��_�Łu�Z���v�Ƃ͈قȂ�Ƃ����B�܂��A�ꎞ�I�Ȑ����̏ꏊ�ł͂Ȃ��_�Łu�����v�Ƃ͈قȂ�B �@ �@�@���Ȃ́A�ːЎ��������̎w�j�Ƃ��āA�ȉ��̓��e�̒ʒB�i�������N10��2���j���Ă���[4]�B�Ȃ��A���̒ʒB�͌�ɕ����I�ɉ�������Ă��邪�A������ɂ���A�@��i���s�A�K�p�ʑ��@�j�̓K�p�ɍۂ��A�ٔ������S��������͂͂Ȃ��B �@�@ ���{�ɂ�����틏���̔F�� �@���{�l�̏ꍇ�ɂ́A���{�����ŏZ���o�^�����Ă���A���{�ɏ틏��������ƔF�肳���B���O�]�o�̂��߁A�Z���[���폜���ꂽ�ꍇ�ł��A�o��1�N���ł���A���{�ɏ틏��������Ɣ��f�����B �@�O���l�̏ꍇ�ɂ́A�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�ɂ��ݗ����i�ɉ����āA�i�Z�ړI�ł����1�N�ȏ�A���̑��̖ړI�ł����5�N�ȏ�A�����ɍݗ����Ă���ꍇ�ɔF�肳���B
�@�A �O���ɂ������틏���̏ꍇ �@���{�l�̏ꍇ�ɂ́A��������̊O����5�N�ȏ�A�i�Z�ړI�Ȃǂ̓��ʂ̏ꍇ�ɂ�1�N�ȏ㋏�Z����ꍇ�A���̊O���ɏ틏��������ƔF�肳���B �@�O���l���A����̖{���ɋ��Z���A�Z���o�^���s���Ă���ꍇ�́A���̍��ɏ틏��������ƔF�肳���B��O���ɂ�����틏���̔F��́A���{�l�̊O���ɂ�����틏���̔F��̏ꍇ�ɏ�����B �@ �@�� �틏������̎w�j�i�@���ȒʒB�j
�@�틏�����A���_�ɂȂ�ꍇ�ɂ����āA�틏�����ǂ��ɂ��邩����ł��Ȃ��Ƃ��́A���� �ɂ�邪�i��39��{���j�A��25���i��26���1������ё�27���ɏ]�����p�����ꍇ���܂ށj���K�p�����ꍇ�ɂ́A�����҂ɍł����ڂȊW�̂���n�i�Ŗ��ڊW�n�j���A���_�ƂȂ�i��39��A���j�B �@�Ȃ��A�@��ł́A�Ƒ��@�̕���ɂ����āA�틏�����A���_�Ƃ���Ă������A�K�p�ʑ��@�́A���Y�@�̕���ł��p���Ă���i��8���2���A��19���Q�Ɓj�B���̓_�Ɋӂ݁A�]���̋K��i�@���31���2���j�͉��߂��Ă���i�K�p�ʑ��@��40���2���j�B
(3) �Ŗ��ڊW�n �@���ێ��@�̍ŏd�v�����̈�ł�搂��Ă���悤�ɁA�O�����́A����ɍł����ڂɊW����n�̖@��K�p���A�������ׂ��ł��邪�A�Ŗ��ڊW�n�Ƃ́A���̂悤�ȏ����@���w�肷�邽�߂̘A���_�ł���B�ǂ̒n���Ŗ��ڊW�n�ɂ����邩�͌ʁE��̓I�Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�Ⴆ�A�����҂̏]���̏틏����e���̏틏���A�����l���A�����E�Ƃ̏ꏊ�Ȃǂ������I�ɍl������邪[5]�A���ˉƍق́A�����̐����l�������d������[6]�B����́A�]���̏틏���₻�̑��̎����͍Ŗ��ڊW�n�����肷��d�v�ȗv�f�ɂȂ肦�Ȃ����߂ł���B
(4) ���ݒn �i��8���3���A��13���A��18���A��19���j (5) �s�גn �i��10���2���j (6) �������s�n�i��24���2���j (7) �������������n�i��14���j (8) ���ʔ����n�i��17���j (9) �����҂̈ӎv�i��7���1���j
�@��ʓI�ɁA��̒P�ʖ@���W�́A��̘A���_�݂̂�}��Ƃ��āA�����@�����肳��邪�A�����̘A���_���l�����A�����̏����@���w�肳��邱�Ƃ�����[1]�B 2.�@�A������i�A���_�̌��ߕ��j �@����@���W�̘A���_�����ɂ��邩�͗��@�����̖��ł��邪�A�Ⴆ�A����̌�ʎ��́i�s�@�s�ׁj�̃P�[�X�ł���A�@���Q�҂܂��͔�Q�҂̏틏���A�A���Q�҂܂��͔�Q�҂̍��� �A�������́A�B�@��n��A���_�Ƃ��ď����@�����߂邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�����Ƃ��A�O�q�����悤�ɁA�K�p�ʑ��@��17��{�� �́A���ʔ����n�A�܂�A�����N�Q�����������ꏊ��A���_�Ƃ��āA���ʔ����n�@�������@�Ɏw�肵�Ă��邪�A���̗��R�Ƃ��ẮA�ȉ��̓_����������B
�@���̑��ɁA��13�� �́A�@���W�i�@���s�ׁj�Ɠy�n�̌��т����d�����A�y�n��A���_�ɂ��Ă���i�ڂ����� �������j�B
3. ���l�@�̘A���_ �@�Ƃ���ŁA�l�̐g����\���Ɋւ���@�����́A���ێ��@��A�`���I�ɁA���l�@�ɏ]���ĉ��������ׂ��Ƃ���Ă����B���l�@�Ƃ́A����҂̑؍ݏꏊ�Ɋւ��Ȃ��A���̎҂ɓK�p�����@�߂̑��̂ł��邪�i�Ⴆ�A����҂�A���ɑ؍݂���ꍇ��A���@�AB���ɑ؍݂���ꍇ��B���@�Ƃ����悤�ɁA�؍ݏꏊ�� �����ĕύX�����̂ł͂Ȃ��A��ɓ��l�ɓK�p�����@�߁j�A������ɑ��l�@�����肷�邩�Ƃ����_�ɂ��Ă͏��O���œ��ꂳ��Ă��炸�A�ȉ��̂悤�Ȋ���̗p����Ă���B
�@���̐��ɂ��ƁA�����҂̖{���̕����A�K���Ȃ����������f�����@�����̉������\�ɂȂ邽�߁A�l�̐g����\�͂Ɋւ��鏀���@�����߂��i�A���_�j�Ƃ��č��Ђ͍ł��K�ł���ƍl������B�܂��A���Ђ͍P��I�ł��邽�߁A�����@����̈��萫�Ɏ�����Ƃ����i��ʂɁA����l�̍��Ђ��ύX����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�����@���ύX����邱�Ƃ͂Ȃ��j�B �@�����Ƃ��A���Ђ́A���Ƃƌl�����@���̌��ѕt���i�R���j�ł���A�l�����@���̖@���s�ׂɂ͖��ڂɊ֘A���Ȃ��B���̂��߁A���Ђ���ɂ��������@�̌���͕s�K�Ƃ��Ĕᔻ����Ă���B�܂��A �{���@��`�ɂ��ƁA�ȉ��̖�肪������B
�@�@�@ �i�Q�l�j EU�@��̖��_ (2) �Z���Ɋ�Â������@�����肷�� ����i�Z���n�@��`�j �@�Z���́A�����҂̐����i���@�s�ׁj�ɖ��ڂ����A���_�ł���A���Ђ�A���_�Ƃ����ꍇ�ɐ�������i�O�q�Q�Ɓj�����������邪�A�Z���̊T�O�͊e���ŕK���������ꂳ��Ă��Ȃ��i���@��21���Q�Ɓj�B���̂��߁A�틏���Ƃ����T�O���p������悤�ɂȂ������A���̒�`�����m�ɂȂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@���s�@�ł���K�p�ʑ��@�Ƃ͈قȂ�A�@��͏Z����A���_�ɂ��Ă���i�Q���j�A���̒�`�ɂ��āA�ȉ��̌������咣����Ă����B
�@���ێ��@�̓K�p�����ƂȂ�ꍇ�ɂ́A���ێ��@�Ǝ������Ó��ł��邪�A�@��́A�̓y�@���ɂ��Ƃ���Ă���i�����̏Z���̑��݂�F�߂�@���29���2���́A�̓y�@����O��ɂ��Ă���j�B �@
�@
[1] ���̓_�ɂ��A�Ⴆ�A�R�c�E���c�w���K���ێ��@�x�i�V�Łj�L��t20�ňȉ��Q���B [2] �K�p�ʑ��@�i����я]���̖@��j�́A�����I�ɁA�{���@��`���̗p���Ă���B [3] �Z���n�@�l�@�Ƃ��Ă���B [4] �@���ȒʒB�̏ڍׂɂ��āA���r�w���ێ��@�u�`�x�i��2�Łj117�`118�ł��Q�Ƃ��ꂽ���B [5] �@���Ȃ̊�{�ʒB�i�������N10��2���@���Ȗ�2��3900���A�O����S�I�i��3�Łj19�Łj�Q�ƁB [6] �O����S�I(��3��)18�ł����24�ňȉ��Q�ƁB |
�u���ێ��@�u�`�m�[�g�v�̃g�b�v�y�[�W�ɖ߂� |
�@�@