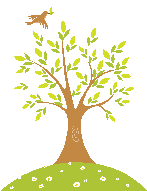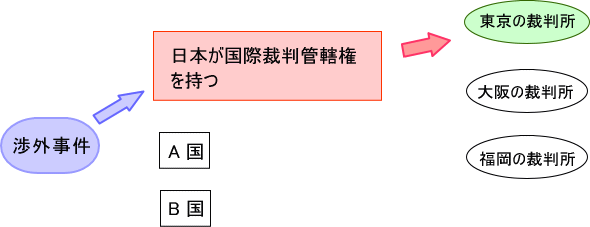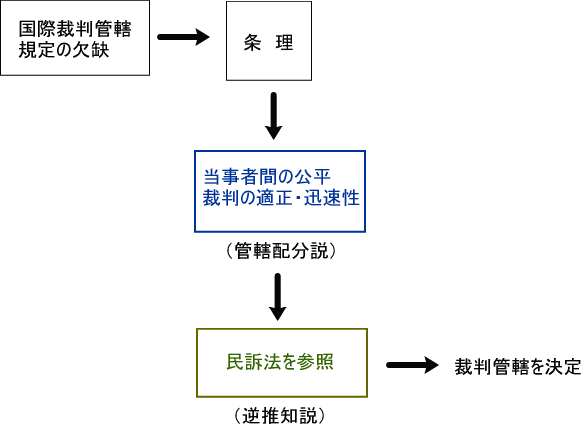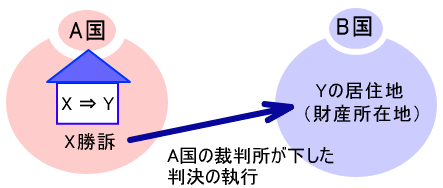|
|
�� �� �� �� �� �� |
|
1�D���_ 1.1. �ٔ��NJ�
�ٔ��NJ��Ƃ́A�ǂ̍ٔ������ٔ������s�g�����邩�ɂ��Ē�߂���茈�߂̂��Ƃł���[1]�B�ٔ��NJ��ɂ��Ē�߂�K��Ƃ��āA�ٔ����@��33���1���E��24���1������і����i�ז@��4���ȉ�����������B �E�ٔ����@��33���1���͊ȈՍٔ����̊NJ����ɂ��āA�܂��A��24���1���́A�n���ٔ����̊NJ����ɂ��Ē�߂Ă���B �E����ɑ��A�����i�ז@��4���ȉ��́A�ȈՍٔ����ł���ƁA�n���ٔ����Ƃł���Ƃ��킸�A�ȉ��̂悤�ɋK�肵�Ă���i��4���ȉ��́A���ٔ����ɓK�p�����j�B �@ �@(1) ���ʍٔ��Ђɂ��NJ��i��4���j
�@ (2) ���ʍٔ��Ђɂ��NJ��i��5���ȉ��j �@�O�f�̕��ʍٔ��Ђɂ��ٔ��NJ��̑��ɁA�ȉ��̓��ʍٔ��Ёi�܂��� �Ɨ��ٔ��� �ƌĂԁj�ɂ��NJ����F�߂���B�����́A�����̊NJ��ٔ����̒�����A����ɗL���Ȃ����X�ȍٔ����ɑi�����N���邱�Ƃ��ł��邪�A�����Ƃ��A����̎����ɂ��āA�����̑i�����N���邱�Ƃ͋֎~�����i�d���N�i�̋֎~�A���i�@��142���Q�Ɓj�B
(3) �퍐�̓��ӂ�����ꍇ �������I�������ٔ����i��12���j
�@�����̋K��́A�������������ł͂Ȃ��A�O�����ɂ��K�p�����Ƃ��錩�������邪[2]�A�ō��ٔ����́A���[�f�B���O�E�P�[�X�ł����u�}���[�V�A�q���v[3]�ɂ����āA�䂪���ɂ́u���ۍٔ��NJ��ڋK�肷��@�K���Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B�Ȍ�A���Ⴈ��ђʐ��́A���̔��|�ɂ��������A�����i�ז@���̋K��͍��������ɓK�p����邱�Ƃ�z�肵�Ē�߂��Ă���A���ۍٔ��NJ��ɂ��Ē��ړI�ɒ�߂���̂ł͂Ȃ��Ɖ����Ă���B
�@ ���ۍٔ��NJ��́A���ɂ���Ē�߂��邱�Ƃ�����B�䂪�������̂悤�ȏ���������Ă��邪[4]�A���̓K�p�͈́i�����I�K�p�͈́j�͌��肳��Ă���B���̂��߁A���K�肪�K�p����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ǂ̂悤�ɂ��č��ۍٔ��NJ������肷�邩�ǂ��������ɂȂ�B
�@ (1) ���ۍٔ��NJ������肷��K�v�� �@�O�q�������������̏ꍇ�́A�������ǂ��ٔ������NJ��ٔ����ƂȂ邩�ǂ��������肷��悢���A���ێ����i�O�����j�̏ꍇ�ɂ́A�ǂ̍����ٔ������ٔ����Ȃ�������L���邩�ǂ����ɂ��Č�������K�v������[5]�B �@�ٔ����͍��Ǝ匠�̈��p�ł���B���̂��߁A�䂪���Ɗ֘A�����Ȃ�������A�����̎匠�s�ׂɊւ�鎖���ɂ��āA�䂪���̍ٔ������ٔ����s���Ƃ���A�����̎匠��N�Q�Ȃ������邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂��A���ۖ@�ɔ����鎖�Ԃ���������B�܂��A�䂪���Ɋ֘A���Ȃ������ɂ��āA�����ٔ������������邱�Ƃ́A�i�ד����҂̗��v�A�i�o�ρA�܂��A�ٔ��̓K���Ƃ������_�����肪������B ����ɁA�i�ד����҂ɂƂ��āA���ۍٔ��NJ��̌���́A�����ٔ��NJ��̌�����d�v�Ȗ�� �ƂȂ�B����́A�ȉ��̗��R�Ɋ�Â��Ă���B
(2) ���ۍٔ��NJ����[���Ɋւ��鏔���� �@�@�i���ۍٔ��NJ��Ɋւ���K��j�̌�㞂�萶������́A�𗝂ɏƂ炵�Ĕ��f����悢�ƈ�ʂɉ�����Ă��邪�A�𗝂̋�̓I���e�͂ǂ̂悤�ɂ��Č��肷�邩�Ƃ�����肪������B���̕��@�ɂ��ẮA�l�X�Ȋw�����咣����Ă��邪�A��Ȍ����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(a) �t���m�� �@����́A�����i�ז@�̓y�n�NJ��Ɋւ���K���K�p���A���{�����ɍٔ��Ђ����鎖���́A�����Ƃ��āA���{�̍ٔ������ٔ����s���Ƃ��錩���ł���[7]�B���̊w���́A�����i�ז@�̋K��Ɋ�Â��A�𗝂̓��e���m�肷��Ƃ�����̂ł͂Ȃ����A���ʂƂ��ẮA���i�ז@�̋K��ɏ]���A���f���邱�ƂɂȂ�[8] (b) �NJ��z���� ����́A�@�����ҊԂ̌����A�A�ٔ��̓K���A�B�葱�̐v�����Ȃǂ��l�����A���ۍٔ��NJ��ɂ��Č��肷��Ƃ����l���ł���B���Ȃ킿�A���ۍٔ��NJ��́A�𗝂ɂ���đ����I�ɔ��f���ׂ��Ƃ��錩���ł���[9]�B
�@�@�@ (c) ���̑��̊w�� �@���̑��Ɂu���v�t�ʐ��v��u�V�ތ^���v������Ă���[10]�B (3) ����@ ���ۍٔ��NJ��Ɋւ��郊�[�f�B���O��P�[�X�ƂȂ����u�}���[�V�A�q�������v[11]�ɂ����āA�ō��ق́A�܂��A�����ҊԂ̌�����ٔ��̓K���E�v�����Ɋӂ݁A�𗝂̓��e�����肷�ׂ��Əq�ׂĂ����Ȃ���A���i�@�̋K��Ɋ�Â����ۍٔ��NJ��ɂ��Ĕ��������B���Ȃ킿�A�NJ��z�������o���_�Ƃ��A�t���m���ɏ]���A���ۍٔ��NJ������肵���B
���̌�A�����R�́A�����|�ɏ]���A���i�̎���̑�����ꍇ�ɂ́A��O��F�߂Ă�����[12]�A���̂悤�Ȏ戵���́A����9�N�̍ō��ٔ���[13]�ɂ���ď��F����Ă���i�C���ސ����A�ڂ����� �������j�B �@ �@�ȉ��ł́A�ō��ق��}���[�V�A�q�������ɂ��Đ�������B
�@ �@ (4) �𗝂̓��e�̊m�� �@�䂪���ɂ́A���ۍٔ��NJ��ɂ��Ē��ړI�ɒ�߂�@�K�͂Ȃ����߁A���ۍٔ��NJ��́A�𗝂Ɋ�Â����f���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�O�f�̃}���[�V�A�q�������ɂ��A�ȉ��̓_���l�����A�𗝂̓��e���m�肷��K�v������B �@�@ �@ �i�ד����ҊԂ̌��� �i�ד����ҊԂ̌����Ɋւ��ẮA�܂��A�퍐�̕ی��i�퍐�̖h�䌠�̕ی�j�ɂ��čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�����̍ٔ����錠���ɂ��Ă��\���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@��F ���������̍��ۍٔ��NJ� �A �ٔ��̓K�� �ٔ��̓K���́A�����F��̓K���A�@���߂̓K������ѓ����҂̑i�����̏[���Ƃ������ϓ_���猟�������B
�B �ٔ��̐v�����A�i�o�ς���є����̎����� �Ⴆ�A���Ẳ𖾂ɕK�v�ȏ؋��i�؋����@�j��A���ɂ���ꍇ�ɂ́A�ٔ��̐v�����i�܂��A�ٔ��̓K���j�̊ϓ_����AA���ōٔ����s�����̂Ƃ��A�䂪���̍��ۍٔ��NJ��͔ے肳���ׂ��ł���B�܂��A���{��A���Ƃ̊ԂɊO���W���Ȃ��A�~���ȍ��ێi�@�������s���Ȃ��ꍇ�����l�ł���B �@ �܂��A���t�����i�Ⴆ�A�퍐��1000���~�̎x�����𖽂��锻���j�̏ꍇ�ɂ́A�����̎������ɂ��čl������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B�܂�AA���̍ٔ��������̔������������Ƃ��Ă��A�퍐���C�ӂɔ����ɏ]�킸�A�������s�̑ΏۂƂȂ���Y��B�����ɂ���Ƃ��́AB�����ōٔ����s���������悢�Ɖ������B�Ȃ��Ȃ�AA���̔����́AB�����ł����R�Ɍ��͂����Ƃ͌���Ȃ����߂ł���i�O�������̏��F�E���s�̖���j�B
�@ �C ���̑��̗v�f ���̑��ɂ��A���ɐg���W�����ł������҂̍������l������K�v������Ƃ�����i�Q���j�B �܂��A�������̍��ői�����邱�Ƃɑ��A�퍐���\���\�ł��������ǂ����i�퍐�̗\���\���j���������ׂ��ł���B�Ⴆ�A��ʎ��̂Ɋ�Â����Q���������̑i���́A���̒n�̍ٔ����ɊNJ������^������Ƃ���A�퍐�i���Q�ҁj�̊��҂ɔ����Ȃ��i���i�@��5���9���Q�Ɓj�B����ɑ��A�������ӔC��₤�i���́A�N�Q�����n�i�Ⴆ�A�^�C�����̏Ⴕ�A���̂����������y�n�j�̍ٔ����̊NJ�����F�߂�Ƃ���A�퍐�i�^�C���̐����ҁj���S���\�������Ȃ��������̍ٔ����ɑi�����W�����邱�ƂɂȂ�A�퍐�ɕs���ɂȂ�B �@ [1] �ΐ얾���������i�ҁu�V�����i�ז@�v�я��@�i1997�N�j35�ňȉ��Q�ƁB [2] ���c�O�u���{�ٔ����̍��ۋ������ߏ�(5)�v���^249��45�ŁB�Ȃ��A���ꌛ�u���㍑�ێ��@�i��j�v262�ňȉ����Q�Ƃ��ꂽ���B [3] �Ŕ����a56�N10��16���A���W35��7��1224�ŁB [4] ���̗�Ƃ��āA�ȉ��̏��������B �@�E1929�N�́u���ۍq��^���ɂ��Ă̂���K���̓���Ɋւ�����v�i�u�����\�[���v�j �@�E1957�N�́u�C��q�s�D���̏��L�҂̐ӔC�̐����Ɋւ��鍑�ۏ��v �@�E1969�N�́u���ɂ�鉘�����Q�ɂ��Ă̖����ӔC�Ɋւ��鍑�ۏ��v �@�E1971�N�́u���ɂ�鉘�����Q�̕⏞�̂��߂̍��ۊ���̐ݗ��Ɋւ��鍑�ۏ��v �@�@�����̏��ɂ��āA���c���O�u���ɂ��C�m�����ɂ��Ă̊NJ����v���K���a���i�ҁj�w���ۖ����i�ז@�x�i�я��@�A2002�N�j118�ňȉ��A���u�ӔC�����葱�̊NJ����v���K���i�ҁj�E�O�f��123�ňȉ����Q�Ƃ��ꂽ���B [5] ���̏ꍇ�ɂ́A�Ⴆ�A���{���ٔ��NJ�����L���邩�A�܂��̓A�����J���O�����ٔ��NJ�����L���邩�Ƃ������Ƃ����ɂȂ�A���{�̂ǂ̍ٔ����i�Ⴆ�A�����n�فj�A�܂��́A�A�����J�̂ǂ̍ٔ����i�Ⴆ�A�A�M�n�فj���NJ�����L���邩�ǂ����́A���ɂȂ�Ȃ��B �@�@�Ȃ��A���鍑�ۏ��i�Ⴆ�A���������������j�Ɋ�Â��V���ȕ��������@�ւ��݂����A���@�ւɊNJ������^�����邱�Ƃ����邪�A���̊NJ������ꑮ�I���ǂ����A�܂��͍����ٔ����̊NJ����̕����D�悷�邩�ǂ����ɂ��Č�������K�v�����邪�A���̖��ɂ��āA�����ł͐[���������Ȃ����Ƃɂ���B [6] �i�����NJ��Ⴂ�̍ٔ����ɒ�N���ꂽ�ꍇ�A�ٔ����͑i�����p�������A�E���ŊNJ��ٔ����Ɉڑ�����B����ɂ���āA�����͍đi�̎萔���p��Ƃ�A�܂��A�N�i�ɂ�鎞���̒��f����ԏ���̗��v�����킸�ɂ��ށi���@��149���Q�Ɓj(�ڂ����͂������j�B [7] ���q��u�V�C�����i�ז@�̌n�v66�ŁA�]��p���w���ێ��@�ɂ�����ٔ��NJ����i�R�E���j�x�@��60��3��374�łȂǁB [8] �ΐ얾���������ҁu���ۖ����i�ז@�v35�Łi�����E�����j�B [9] �R�c���V�ؕҁu���ێ��@�u�`�v231�Łi�O�Y�j�A���ێ��@�̑��_149�Łi�n�Ӂj���Q�ƁB [10] ��f�̊w���ɂ��A�ΐ얾���������ҁu���ۖ����i�ז@�v36�ňȉ��i�����E�����j���Q�Ƃ��ꂽ���B [11] �Ŕ����a56�N10��16���A���W35��7��1224�Łi�}���[�V�A�q�������j�����i����S�II�i�V�@�Ή���Łj40�ňȉ��i�n�Ӂj���O����S�I�i��3�Łj196�Łi���K�j�B [12] �Ⴆ�A�����n�����Ԕ������a61�N6��20���i��p�����q���j����1196��87�Ł����^601��65�ŎQ�ƁB���̃P�[�X�ɂ��āA������ ���Q�ƁB [13] �Ŕ�����9�N11��11���A���W51��10��4055�Ł��W�����X�g1133��182�ŁB�{���ł́AX�i�����ԓ���A�����Ă�����{�@�l�j��Y�iX���ϑ�����A���B�e�n�Ŏ����Ԃ��t����҂ŁA�h�C�c�E�t�����N�t���g�ɖ{����u�����{�l�j������K�i�a�����j�̕Ԋ҂����߂��i���̍ٔ��NJ�������ꂽ�B���i�@��5���1���i�`�����s�n�j�ɏƂ炵�A���{�̍��ۍٔ��NJ���F�߂邱�Ƃ��\�����i���@��484���Q�Ɓj�A�ō��ق́A�@XY�Ԃ̌_��̓h�C�c�Œ�������AY���h�C�c�ŋƖ����s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��邱�ƁA�A�`�����s�n����{�Ƃ��A�܂��A���{�@�������@�Ƃ���|�̖��m�ȍ��ӂ͌`������Ă��Ȃ����ƁA�B20�N�ȏ�ɂ킽��AY�̓h�C�c�ɐ����̖{����u���Ă��邱�ƁA�CY�̖h��ɕK�v�ȏ؋����@���������ɏW�����Ă���Ƃ��������i�̎���Ɋӂ݁A���{�̍��ۍٔ��NJ���ے肵���B [14] �ڂ����́A�}���[�V�A�q��iY�j�̍��s���s�ɂ�蔭������A�̑��Q������������X��͑��������Ƃ��āAY�ɑ���1,300���~�]�̎x���������߂�{���i�����N�����B [15] �Ⴆ�A���i����S�II�i�V�@�Ή���Łj40�ňȉ��i�n�Ӂj�Q�ƁB [16] ���i����S�II�i�V�@�Ή���Łj41�Łi�n�Ӂj�Q�ƁB
|
|
|
�u���ۖ����i�ז@�u�`�m�[�g�v�̃g�b�v�y�[�W�ɖ߂�