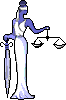 |
E. �i �� �� �R ��
|
5. �����҂̎咣 �@�����i�葱�͌����̒�i�i�i��̒�o�j�ɂ���ĊJ�n����A�����ґo���������٘_ �ɂ����Ď���̌������咣����B���������鎖���ɂ��Ă͏؋����o������A�ؐl�q������{����K�v�����邪�A������҂����ɑi������艺������i��261���j�A�a���i��267���j�ɂ��葱�����I�������邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ɁA�i�ז@��̌��ʂ������铖���҂̍s�ׂ�
�i�s�� �ƌĂԁB |
�@
|
|
5.2. �咣�Ƃ� �@�咣�Ƃ́A�����҂̐\���Ă���b�Â���i�s�ׂ��w���B���ȂɗL���Ȓq�Ƃ����_�ɂ����āA���� �Ƃ͈قȂ�B�܂�A�����Ƃ́A������̎咣��F�߂�A����ɕs���Ȓq���w���B
�@�咣�ɂ́A�@ �����E�`����@���W�Ɋւ���q��@�̓K�p�E���߂Ɋւ���q�i�@����̎咣�j�ƁA�A �����̑��ۂɊւ�����́i������̎咣�j�����邪�A���҂̏ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@��q�����悤�ɁA�@����̎咣�Ƃ́A�����҂� a. �����E�`����@���W�̗L���ɂ��āA�܂��́Ab. �@�̉��߁E�K�p�ɂ��Ēq���邱�Ƃ��w�����Aa
�����`�̖@����̎咣�Ab ���L�`�̖@����̎咣�ƌĂԁB�B |
|
�i��j |
��������x�������̑i���ɂ����āA�퍐���A |
| a. | �x���`���͂Ȃ��Ǝ咣����i���`�̖@����̎咣�j�B |
| b. | �{���ł͉䂪���̖��@���K�p����A����173���ɂ�����2�N�Ŏ������ł���Ǝ咣����i�L�`�̖@����̎咣�j�B |
�@
|
�@�Ȃ��A�u�ٔ����͖@��m��v�Ƃ����@���������Ƃ���A�@�߂̉��߁E�K�p�͍ٔ����i�ٔ����j�̐E�ӂł���A�ٔ����͓����҂̖@����̎咣�ɍS������Ȃ����i�Q���j�A���̓_�ɂ��āA�ȉ��̖�肪������B |
|
�@ |
�����̖@����̎咣��퍐���F�߂�ꍇ�i���������j�A���̓_�ɂ��čٔ����͐R�������Ȃ����B �@�@�@�@ |
|
�A |
�����҂̖@����̎咣�ƍٔ����̖@�߉��߂��قȂ�ꍇ�A�ٔ����͂��̂��Ƃ��҂ɓ`����ׂ����i�ٔ����̖@�I�ϓ_�w�E�`���j�B |
|
(2) ������̎咣 �@������̎咣�Ƃ́A�Ⴆ�A�擾��������b�t���邽�߁A�u20�N�ԁA��L���Ă���v�A�܂��A�u�������X�N�ȏ�ɂ킽��A�������Ă��Ȃ��v�ȂǁA�����ɂ��Ď咣���邱�Ƃ��w���B
�@�Ȃ��A�Ⴆ�A�O�f�̇B�̎����ɂ��āA�{���͌������咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ����i�܂�A�������咣�ӔC���j�A�������咣���Ȃ��ɂ�������炸�A�퍐�������I�ɔF�߂邱�Ƃ�����B���̂悤�ȏꍇ�ł���A�����҂ɂ���Ď咣����Ă��邱�Ƃɂ����Ȃ�����A�ٔ����͇B�̎������̊�b�Ƃ��邱�Ƃ��ł���i�咣���ʂ̌����j�B |
|
|
�@���铖���҂��咣���������ɂ��āA��������ے肷�邱�Ƃ� �۔F �ƌĂԁB�Ⴆ�A���ԊҐ����i�ׂɂ����āA�u2005�N1��10���A�퍐��100���~��݂����v�Ƃ��錴���̎咣�ɂ��āA�퍐���@�u��Ă��Ȃ��v�܂��́A�݂��肪���������Ƃ�ے肷���|�Łu�肽�o���͂Ȃ��v�ƒq������A�A�u2005�N1��10���́A1�����A�Q�Ă������ߎ�Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ邱�Ƃł��邪�A�@���P���۔F�A�܂��A�A�� ���R�t�۔F�i�Ȃ����Ԑڔ۔F�j�ƌĂԁi���i�K����79���3���͗��R��t���邱�Ƃ�v�����Ă���j�B�܂��A�u�m���ɂ�������������A����͑��^���ꂽ���̂��v�ƒq���邱�Ƃ��A���R��t���đ�����̎咣��۔F���Ă��邽�߁A���R�t�۔F�i�Ȃ����Ԑڔ۔F�j�ɂ�����B�Ȃ��A���̏ꍇ�ł���A���K�݂̑��肪���������Ƃ�F�߂Ă���킯�ł͂Ȃ����߁A��q���鎩���ɂ͂�����Ȃ��B �@����ɑ��A�u�肽���ǂ���������Ȃ��v �܂��́u�m��Ȃ��v���Əq�ׁA������̎咣���^�������Ȃ��m��Ȃ��ƒq���邱�Ƃ� �s�m �Ƃ������A����͔۔F�Ɛ��肳���i��159���2���j�B
�@�O�f�̃P�[�X�ŁA�퍐���u�����̎咣�ǂ���A���K��������v�Əq�ׂ邱�Ƃ� ���� �ƌĂԁB�������ꂽ�����ɂ��āA�����͏ؖ�����K�v���Ȃ��B����͓����ҊԂɑ������Ȃ����߂ł��邪�A����䂦�A�ٔ����͎������ꂽ���������̂܂܍ٔ��̊�b�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�٘_��`�̑�2�e�[�[�j�B�������A�E���T�m��` ���K�p�����P�[�X�ł́A���̌���ł͂Ȃ��B�܂�A�l����������v���̋����P�[�X�ł͐^��������K�v�����������߁A�ٔ����͐E���ŏ؋������W���A�����҂̎������^���ɔ�����Ɖ������ꍇ�ɂ͂�����̊�b���珜�O���邱�Ƃ��ł���B �@�@�@
|
|
�@ |
�����̓��e���^���ɔ����A���A����Ɋ�Â��Ă���ꍇ�i�唻��4�9�29�A�S�I�i��3�Łj64�����j |
|
�A |
���\�⋭���ȂǁA�Y����A�����ׂ����l�̍s�ׂɂ�莩������Ɏ������ꍇ�i�Ŕ���33�E3�E7�A���W12-3-469�j�i��338���1����5���j |
|
�B |
������̓��ӂ�����ꍇ�i�Ŕ���34�9�17�A���W13-11-1372�j |
| �@�Ȃ��A�����̑ԗl����ʂɂ��āA�ȉ��̓_�ɒ��ӂ��ꂽ���B
�� �ٔ��O�̎��� �@�����҂��ٔ��O�Ŏ������邱�Ƃ����邪�i�ٔ��O�̎����j�A�����i�ז@��A����ɂ͏�q���������̌��͂͗^����ꂸ�A�P�ɓ����҂��������������������邱�Ƃ𐄔F������ɉ߂��Ȃ��B |
�ٔ��O�̎��� �� ���������������Ƃ𐄔F
|
�� �Ԑڎ����̎��� �@�O�q�����悤�ɁA�Ԑڎ����ɂ��āA�ٔ����͓����҂̎咣�E�q�ɍS������Ȃ��B���̂��߁A�Ԑڎ����͎����̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B�܂�A�Ԑڎ����ɂ��āA�ٔ����͓����҂̎咣�ɔ���ꂸ�A���R�ɔ��f������i�ʐ��E����j�B �@�����҂��A������̎咣���鎖���i��v�����j�ɂ��Ăł͂Ȃ��A�����̑��ۂ�@�����ʂ̔����ɂ��Ď������邱�Ƃ��A�ʏ�̎����Ƌ�ʂ��A�������� �ƌĂԁB
�@�����̑��ہi�����E�`���W�̐����j��@�����ʂ̔����ɂ��Ĕ��f����͍̂ٔ����ł��邽�߁A�ٔ����͓����҂̌��������ɍS������Ȃ��B�O�f�̗�Ō����A�ٔ����́A������퍐�̒q�ɔ���ꂸ�A����ݎ،_���90���~�ɂ��Đ������Ă���Ɣ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����҂����������ɍS�����ꂸ�A����A���e�I�ɈقȂ�咣�����Ă��悢�Ƃ���Ă���B�܂�A���������ɂ��ẮA�O�q���������̓P��Ȃ�������Ɋւ���@���i�����̕s�P����j�͓K�p����Ȃ��B�����Ƃ��A�ߎ��́A�i��̐M�`�� �Ȃ��� �֔����̌��� �Ɋ�Â��A���̍S���͂�F�߂錩�����L�͂ł���B�܂�A����A�������锭�������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B |
|
5.5. �R�� �@�������A����̐����𗝗R�t���鎖���i��v�����j���咣���A�܂��A������ؖ������ꍇ�A�퍐�͂���ɔ��_���Ȃ���Δs�i����B�Ⴆ�A��������x�������i�ׂɂ����āA���������ׂĂ̎�v�������咣�E�ؖ������ꍇ�A�퍐�́A������͎����ɂ�������ł��Ă��邱�Ƃ�A�_��͍���ɂ���Ē����������̂Ŗ����ł��邱�Ɠ����咣�E�ؖ����Ȃ���Δs�i����B���̂悤�Ȍ����̐����������ł�������i���Ŏ����j�A�������̔�����W����i���떳���j�咣�� �R�� �ƌĂԁB�퍐���ؖ��ӔC���_�ŁA�۔F�Ƃ͈قȂ�B �@�܂��A�퍐���R�َ��������ׂĎ咣���A�ٔ����ɂ���Đ������ƔF�肳���A�����͔s�i����B���������邽�߁A������ �čR�� ���o���A�퍐�̎咣�𑈂����Ƃ��ł���i
|
|
(��j |
��������x�������i�ׂɂ����āA�����́A�ȉ��̎����i��v�����j���咣�E�ؖ�����Ώ��i����B |
|
�@�@ |
�����_��i���蔃���̍��Ӂj�̒��� |
|
�A�@ |
���i�̈��n�� |
|
�B�@ |
����x���������o�߂��Ă��邱�� |
|
�����̐�����r�˂��邽�߁A�퍐�́A�Ⴆ�A�ȉ��̍R�ق��o������B |
|
�E�@ |
����͂��łɎx�������B |
|
�E�@ |
�����_��͍���ɂ�薳���ł���i���@��95���j�B |
|
�퍐�����떳���̍R�قɂ��ďؖ������Ƃ��A�����́A�Ⴆ�A�ȉ��̓_���w�E���A���_������i�čR�فj�B |
|
�E�@ |
�퍐�́A�d�ߎ���Ƃ��Ă��邽�߁A���떳�����咣�����Ȃ��i���@��95��A���j�B |
![]()
|
�@����x�������i�ׂɂ����āA�����ł��锄��́A����x���������o�߂��Ă��邱�Ƃ��咣�E�ؖ�����悭�A���̊������o�߂��Ă���̂ɁA�퍐�ł��锃�傪������x�����Ă��Ȃ����Ƃ܂Ŏ咣�E�ؖ�����K�v�͂Ȃ��B�܂�A����̎x���i�ٍ��j�́A�����̌��������ł����鎖�R�Ƃ��āA�퍐���咣�E�ؖ�����ӔC���i�Q���j�B
|
|
�Ȃ��A�v���������̂��̂ł͂Ȃ��A����ɊY�������̓I�Ȏ�������v�����Ȃ������ڎ����Ƒ����錩��������B |
�@
|
|
�u�����i�ז@�u�`�m�[�g�v�̃g�b�v�y�[�W�ɖ߂�