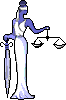|
なお、高等裁判所が第3審となるケースでは、同裁判所の終局判決が憲法に違反することを理由に最高裁判所に不服申立を行うことができる。これを特別上告(または違憲上告ないし再上告)と呼ぶが、憲法第81条は最高裁を違憲審査の終審裁判所として規定しており、最高裁による違憲審査を受ける機会を保障するものである。なお、本来の上告ではないため、特別上告を提起しても、原判決の確定は遮断されないが(参照)、裁判所は申立てにより、原判決の執行の停止または取消しの仮処分を命じることができる(第398条第1項)。
(2) 上告の提起
上告は判決書が送達されてから2週間以内に上告状を原裁判所(第2審)に提出して行う(第313条、第314条)。上告人は、上告理由を述べなければならない。上告状に上告理由が記載されていないときは、最高裁判所規則で定める期間内(上告提起通知書の送達を受けてから50日以内)に上告理由書を提出しなければならないが(第315条第1項)、これがなされなければ、上告は不適法として却下される(第316条、第317条参照 →
控訴の場合と比較せよ)。
(3) 上告理由
上述したように、上告人は上告理由を述べなければならないが、同理由は以下の通りである。
① 憲法解釈の誤りおよび憲法違反(第312条第1項)
憲法解釈の誤りや憲法違反がなければ原判決の内容が異なっていたかどうかは問わない(これに対し、法令違反を理由とする上告(第3項)は、法令違反がなければ、おそらく異なった判決が下されていたであろうとの蓋然性がなければならない(後述参照))。
② 高等裁判所に対する上告は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であってもよい(第3項)
つまり、最高裁判所に対しては、法令違反を理由に上告しえない(最高裁の負担を軽減するため、平成8年の民事訴訟法改正によって、原判決の法令違反は上告理由から削除された)。ただし、原審が最高裁の判例に相反する判決を下したこと、また、法令解釈に重要な事項が含まれているときは、最高裁判所に上告を申し立てることができる(上告受理の申立て、第318条)。
法令には、法律、公権力を行使して発せられた命令・規則、条例、条約、外国法や慣習法などが含まれる。他方、判例法は含まれない。
なお、経験則 は法令にはあたらないが、その解釈を統一する必要性は法令と異ならないため、通説は経験則違背を理由とする上告を認める。つまり、裁判官が経験則に基づき法令を解釈・適用しているケースでは、経験則違反があると法令の解釈・適用にも誤りが生じるため、第312条第3項が定める法令違背を理由に上告を提起しうる。他方、事実認定の段階で経験則が用いられている場合、経験則違反は自由心証主義違背(第247条)、つまり、法令違背と捉えることができるため、同じく、第312条第3項に基づき上告を提起しうる。
③ 原審が法律に従い構成されていなかったこと(第312条第2項第1号)
例えば、欠格事由のある者が判決裁判所を構成していた場合(裁判所法第41条~第46条)、任命方式の違法(憲法第80条第1項)、合議体の構成員数の違法(裁判所法第9条、第10条、第18条、第26条、第35条等)が挙げられる。
④ 法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与したこと(第312条第2項第2号)
例えば、除斥・忌避されなければならない裁判官が判決に関与していたことや、破棄差戻しになった判決に関与した裁判官が判決に関与したことが挙げられる。なお、「判決に関与」するとは、判決の評議や原本作成に関わることを指し、判決の言渡しへの関与は含まれない(これは単なる法令違背にあたる)。
⑤ 専属管轄違反(第312条第2項第3号)、代理人の代理権の欠缺(第4号(なお、追認がある場合を除く〔第312条第2項但書〕)、口頭弁論の公開規定違反(憲法第82条および裁判所法第70条違反)(第5号)、判決理由の欠缺および判決理由の齟齬(第6号〔第253条第1項第3号違反〕)
上掲の①、③~⑤を理由とする上告は、それらの理由が判決の内容に影響を及ぼしたかどうかを問わず認められる。そのため、①、③~⑤の事由を絶対的上告理由と呼ぶ。これに対し、②の事由は、それがなければ判決が異なっていたであろうとの蓋然がある場合にのみ認められる(相対的上告理由)。
(4) 審理
上告審は原審が適法に確定した事実に拘束され(第321条第1項)、原判決の憲法・法令違反ないし解釈の誤りについてのみ審査する。この観点から、上告審を法律審と呼ぶ。
上告審は不服申立てがあった事項についてのみ審査する(第320条)。ただし、職権調査事項については、不服申立てがなされなくとも審査しうる(第322条)。
審理は原則として書面(上告状、上告理由書、答弁書など)で行われる。その結果、上告理由がないと判断されるときは、口頭弁論を経ないで上告を棄却してもよい(第319条)。
(5) 終局判決
上告審の終局判決には以下の3通りある。
① 上告却下判決
上告が不適法なとき、判決で却下される。
② 上告棄却判決
上告に理由がないとき、棄却判決が下される。
③ 上告認容判決
上告に理由があり、認容されると、原判決は破棄されるが、上告審は事実審理を行わないため(→ 法律審)、原則として事件は原審に差し戻されるか(破棄差戻)、同等の裁判所に移送される。ただし、原判決で確定された事実に基づき、上告審が判決を下すことができるときは、そうしなければならない(破棄自判、第326条)。
3. 再審
3.1. 定義
終局判決が確定すると、通常、当事者はもはや裁判のやり直しを要求しえないが、第338条第1項で定められた特別の理由があるときは、再審理や確定した判決の取消を求めることができる。これを再審の訴えと呼ぶ。終局判決が確定した以上、それが尊重されなければならないが、判決に重大な暇疵がある場合においてまで確定判決の効力を維持することは正義に反し、司法への信頼性も低下させるため、認められている。
なお、再審の訴えは確定判決についてだけでなく、確定判決と同一の効力を持つ 訴訟上の和解 や 請求の放棄・認諾 についても提起しうる。
3.2. 再審事由
再審は第338条第1項が列挙する事由(再審事由)を理由とする場合に許される。従来、それらは制限列挙と解されてきたが、今日の通説・判例は、一定の限度で拡張・類推解釈を認める。例えば、第3号の手続保障の趣旨より、訴状の送達が適法になされなかったため、敗訴当事者が手続に関与することができなかったことも再審事由になる(最判平成4年9月10日、民集第46巻第6号553頁)。
再審事由
| ① |
法律に従い判決裁判所が構成されていなかったこと(第338条第1項第1号)
|
| ② |
法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与したこと(第2号)
|
| ③ |
代理権の欠缺(第3号)
|
| ④ |
判決に関与した裁判官が事件について、その職務に関する罪を犯したこと(第4号)
|
| ⑤ |
他人の犯罪行為により自白をするに至ったこと、または他人の犯罪行為によって判決に影響を及ぼすべき攻撃防御方法の提出が妨げられたこと(第5号)
|
| ⑥ |
判決の基礎となった資料が偽造または変造されていたこと(第6号)
|
| ⑦ |
判決が証人や当事者等の虚偽の陳述に基づいていること(第7号)
|
| ⑧ |
判決の基礎となった裁判または行政処分が後に変更されたこと(第8号)
|
| ⑨ |
判決に影響を及ぼすべき重要事項に関し、裁判所が判断していないこと(第9号)
|
| ⑩ |
既判力の抵触(第10号) |
①~③は絶対的上告理由(第312条第1項および第3項)と同じであり、絶対的再審事由として捉えられている。つまり、これらの事由が判決の内容に影響を及ぼしていたかを問わず、再審を提起しうる。
なお、上訴審手続で当事者が再審事由を主張していたときや、再審事由があるのを知りながら主張しなかったときは、再審の訴えは許されない(第338条第1項但書)。
3.3. 再審の申立て
再審の申立ては原判決の確定後、当事者が再審事由を知った日から30日以内に、原判決を下した裁判所に提起されなければならない(第342条第1項)。この申立ては訴えの形式によらなければならない(再審の訴え)。
再審原告となりうるのは、確定判決において全部または一部敗訴した当事者である(原則)。
3.4. 申立ての効果
再審は、上訴と異なり、遮断効や移審効 を持たない。
3.5. 審理
再審の訴えは原判決を下した裁判所の専属管轄に属する(第340条第1項)。審級の異なる裁判所が同一の事件について下した判決が対象になる場合は、上級の裁判所によって併せて審理される(第2項)。
再審手続には、その性質に反しない限り、各審級の訴訟手続に関する規定が準用される(第341条)。
3.6. 決定・判決
再審の訴えが不適法であれば、却下される(第345条第1項)。
適法であれば、再審事由が審査されるが、これが存在しないと判断されれば、訴えは棄却される(第2項)。再審事由があると判断されれば、裁判所は再審開始を決定し(第346条)、不服が申し立てられた点について、本案の審査が行われる(第348条第1項)。その結果、原判決が不当であるとされれば、裁判所は原判決を取り消し、新しい判決を下すが、原判決の結論が正当と判断されれば、再審の訴えを棄却する(第2項・第3項)。
|