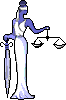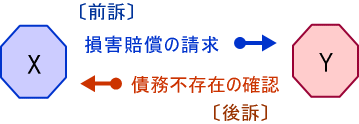|
2. 訴訟上の請求 ~ 訴訟物
2.1. 訴訟物を特定する必要性
民事訴訟は原告の提訴によって開始されるが、原告はどのような内容の判決を求めようとしているのか、つまり、審判の対象を確定する必要がある。例えば、①原告は給付の訴えを提起し、どのような給付を求めているのか(原告は何を請求しているのか)、②確認の訴えの場合には、どのような権利・義務ないし法律関係の確認を求めているのか、また、③形成の訴えでは、どのような法律関係の変動を求めているのかが特定されなければならない。
審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係を「訴訟物」と呼ぶ。つまり、訴訟物とは、訴訟当事者(原告)が相手方(被告)に対し主張する実体法上の権利・義務や法律関係にあたるが、その主張を訴訟物と捉える立場もある。
訴訟物が定まらないと裁判管轄や申立手数料の額(印紙額)も決定されず、訴えを適法に提起することができない。そのため、訴えの提起ないし訴訟の開始にあたり、訴訟物を特定することが極めて重要である。
|
・裁判管轄
|
裁判管轄(土地管轄や事物管轄)は裁判の対象や訴額によって決定される(詳しくは こちら)。
|
|
・印紙
|
訴状には訴額に応じて印紙を貼らなくてはならない。
|
また、民事訴訟法第246条によれば、裁判所は、原告が申し立てた事項についてしか審判しえず、他方、第258条第1項によれば、訴えが適法である限り、裁判所は、全ての申立て(請求)について判断しなければならない。そのため、審判の対象、つまり、訴訟物が原告によって特定されなければならない。これは被告にとっても重要である。なぜなら、審判の対象(つまり、訴訟物)が特定されていないと、被告は裁判で何が争われるかを的確に知ることができず、十分に防御しえないためである。
その他にも、以下の点で問題が生じる。
|
・
|
原告が複数の請求を主張するような場合、それらを同一の裁判の中でまとめて審理しうるか(請求の客観的併合)(第136条)。
|
|
・
|
すでに裁判上で争われている法律問題について改めて訴えを提起することは重複起訴として禁止されるか(第142条)。
|
|
・
|
訴訟中、原告が請求を変更したとき、それは訴えの変更にあたるか(第143条)。
|
|
・
|
判決の効力はどの範囲まで及ぶか(既判力の客観的範囲)(第114条)。
|
このように、種々の観点から、審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係(訴訟物)を特定する必要性が生じる。
2.2. 訴訟物の特定に関する理論(訴訟物理論)
(1) 給付の訴えの訴訟物
審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任であり、同人は、訴状 内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う(詳しくは こちら)。例えば、売買代金を請求するケースのように、売買契約上の権利・義務が問題になるような場合、訴訟物は容易に特定されるが(この場合は、売買代金の請求が訴訟物となる)、以下のように、複数の異なる権利・義務ないし法的根拠に基づき提訴しうる場合には検討を要する。
| ① |
ある特定物(例えば自動車)の返還を請求する事例において
|
a.
|
原告は自らの所有権に基づき返還を請求する場合
|
|
b.
|
原告は賃貸借契約の終了を理由に返還を請求する場合
|
|
| ② |
飛行機の墜落によって乗客が死亡し、その遺族が航空会社に損害賠償を請求する事例で
|
a.
|
遺族が航空会社の債務不履行(運送契約上の債務不履行)を理由に損害賠償を請求する場合(民法第415条)
|
|
b.
|
遺族が航空会社の不法行為(乗客を死亡させたこと)を理由に損害賠償を請求する場合(民法第709条)
|
|
我が国では、伝統的に、原告が被告に対して主張する実体法上の個々の権利が訴訟物として捉えられている(実体法説〔通説・判例〕)。したがって、①のように、同一の物を請求する場合であれ、その根拠となる実体法上の権利(ないし根拠規定)が異なっていれば、訴訟物は異なることになる。そのため、原告は、a
の訴えとは別個に b の訴えを提起することが許される(第142条が定める二重起訴として禁止されない)。また、a と b の請求が一つの訴えの中で主張される場合には、訴えの客観的併合となる。
なお、実体法上は2つの請求権が認められるとしても、a の権利に基づき、すでに物を返してもらっている場合には、bの権利に基づき、再度、請求しうるわけではない。それゆえ、原告は、a
と b の請求のどちらかを優先させ、その請求が認容されれば、もう一方の請求は消滅するという条件に基づき併合されているという考え(訴えの選択的併合)や、aの請求を第1位請求とし、それが認められないときは、bの請求を行うという形で両者を併合(予備的併合)すべきであるという理論が提唱されている。
上述したように、訴訟物を実体法上の権利の主張とみる立場を実体法説と呼ぶが、この考えによれば、a の訴えで敗訴しても、bの訴えを提起することが許されるため、裁判所や被告の負担を不必要に増大させることになると批判されている。この欠点を補うため、被告から特定の給付を受けることのできる法律上の地位(受給権)を訴訟物と捉える学説が主張されている。この見解は、訴訟物を実体法上の権利から切り離し、訴訟で請求しうる包括的な権利と捉えるので、訴訟法説と呼ばれる。また、伝統的な理論である実体法説(旧訴訟物理論)に対比させ、新訴訟物理論と呼ばれる。
訴訟法説によれば、前掲のa と b の請求は、一つの法的地位(被告から給付を受ける権利)に包括され、a や b の主張は、この法的地位を基礎付けるための異なる理由として扱われる。そのため、a
の訴えの後に、bの訴えを提起することは、二重起訴 として禁止される(詳しくは こちら)。従って、訴訟法説によれば、紛争が一回の訴訟で解決されるといったメリットがあるが(紛争解決の一回性)、原告は裁判でさまざまなことを主張しなければならないといった短所もある。そのため、我が国では実体法説が通説・判例となっている。
(2) 確認の訴えの訴訟物
確認の訴えの訴訟物は、原告が主張する特定の権利・義務ないし法律関係の存否である。この点については、学説はほぼ一致しており、旧訴訟物理論によるか、新訴訟物理論によるかで訴訟物は異ならない。
例えば、ある建物の所有権の確認を求める訴え(原告が所有者であることの確認を求める訴え)においては、同建物に関する原告の所有権が訴訟物となる。なお、旧訴訟物理論によっても、所有権の取得が売買契約に基づくか、相続や取得時効によるかで訴訟物は異ならない。
XがYに損害賠償の支払いを求め提訴したところ、Yが支払義務は存在しないことの確認を求め提訴することがあるが、これらの訴えの訴訟物は同一であるため、後訴は二重起訴として禁止される(第142条)。
(3) 形成の訴え
実体法説は実体法上の権利(法律関係)や根拠規定が異なれば訴訟物も異なるとする。例えば、離婚の訴えの場合は、民法第770条第1項が掲げる離婚原因ごとに訴訟物が異なる。
- 第1号:不貞行為を理由とする離婚の訴え
- 第2号:悪意の遺棄を理由とする離婚の訴え
これらの訴えは別個の訴えとされるため、個別に提起することができる。また、第1号に基づく訴えが認められなかった場合、新たに第2号を援用し、訴えることも、二重起訴として禁止されない。
これに対し、訴訟法説は権利関係の変動を求めることのできる法的地位を訴訟物と捉えるため、上掲の2つの訴えの訴訟物は同一となり、同時に提起することは許されない。
|